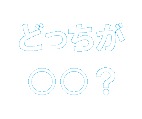大阪府チャレンジテスト結果分析

大阪府チャレンジテスト結果の傾向を分析します。
テストは基本的に中1,中2は三学期のはじめ、中3は二学期のはじめに行われます。
平均点…すべての受験者の点数を足して受験生の人数で割った値です。
中央値…すべての受験者の点数を小さい順に並べたときに真ん中に来る値です。
最頻値…最も取っている人数が多い点数です。
標準偏差…受験者の点数のばらつき度合いです。
仮説
【国語】部分点が多く標準偏差が小さい
【社会】受験勉強で詰めている中3の最頻値が高い
【数学】簡単な問題の配点が高いので平均点が高い
【理科】範囲の広い中3の平均点が低い
【英語】積み上げした科目なので学年が上がるにつれて標準偏差が大きくなる
結果
テスト結果の傾向を分析するために、平成26年度〜令和5年度のテスト結果(平均点、中央値、最頻値(階級値)、標準偏差)の10年分の平均値(ただし中3は平成28年度〜令和元年度、令和3年度〜令和6年度のテスト結果8年分の平均値)を求めました。
標
平 中 最 準
均 央 頻 偏
値 値 値 差
中1国語 60.9 62.6 66.5 18.8
中2国語 59.2 61.3 68.0 19.0
中3国語 59.8 62.0 70.1 19.6
中2社会 51.3 51.0 48.8 20.6
中3社会 51.4 50.9 47.0 20.2
中1数学 54.8 55.9 58.5 22.7
中2数学 54.7 55.9 66.0 23.8
中3数学 51.9 51.9 54.5 22.8
中2理科 51.8 51.7 51.1 21.8
中3理科 48.5 47.4 42.2 20.9
中1英語 63.8 65.8 81.2 21.8
中2英語 55.2 54.6 55.1 23.9
中3英語 53.4 53.0 41.4 24.1
まとめ
【国語】
どの学年においても平均点が高い傾向があり、中央値、特に最頻値は更に高い傾向がある。平均点は中1が最も高いが、最頻値は中1が最も低くて中3が最も高いことから、中1から中3にかけて国語力が向上する生徒は多いと考えられる。また、どの学年においても標準偏差が小さくなる傾向があり、仮説は正しい。 ただし、学年が上がるごとに標準偏差は大きくなっており、学年が上がるにつれ国語力の高い人と極端に低い人に分かれると考えられる。
【社会】
どの学年においても平均点が低くなる傾向にある。平均点や中央値は中2と中3で殆ど変わらないものの、最頻値は中3の方が低く、仮説とは異なり、テストが行われる時期にはまだ社会科の高受勉強に取り掛かっていない受験生が多いと考えられる。
【数学】
中3の平均点が低く、他学年の平均点もやや低いため、仮説は誤り。平均点や中央値の割に最頻値が高い傾向もある。ただし、積み上げ式の科目なのにもかかわらず、中3の標準偏差が中2より小さいことから、夏期講習などで苦手分野の復習をしている生徒が多いと考えられる。
【理科】
どの学年においても平均点は低くなる傾向にある。特に、中3の平均点がかなり低く、仮説は正しい。同じ平均50点前後でも、最頻値が高くなる中3数学などと比べて最頻値が低くなりやすい。
【英語】
学年が上がるにつれ平均点が下がり、標準偏差が大きくなるため、仮説は正しい。特に、学年上がるにつれ最頻値が極端に下がっているため、学年が上がるにつれて英語が苦手な人の割合が増えていると考えられる。また、2021年頃から中2・中3の標準偏差が急に大きくなっている傾向があり、学習指導要領の変更により英語ができる人と英語ができない人の間で更に差がついたと考えられる。
さらに
各教科において平均点と中央値が一致する点数を、各テスト結果からエクセルの単回帰分析というものを用いて求めてみました。
国語 48.8
社会 53.4
数学 51.2
理科 52.8
英語 56.2
※今後のテスト結果が単回帰分析結果どおりの結果になると仮定すると、今後のテストではこの数値より平均点が高い場合は中央値>平均値となり、低い場合は平均値>中央値となります。
平均点が60点のときの中央値も求めました。
国語 62.0
社会 61.4
数学 62.6
理科 61.7
英語 60.9
同じ平均点60点でも、国語や数学は上位層に点数が集中して一部の人が平均点を大きく下げていると考えられます。
このトピックは、名前 @IDを設定してる人のみコメントできます → 設定する(かんたんです)