イヴのショートケーキ
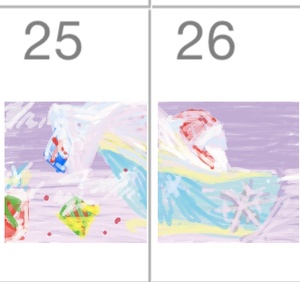
僕は昔、孤児院で育てられた。
ハロウィンやクリスマスの行事なんてなく、酷く横暴な院長に、口の悪い雇われ、粗末な食事。
孤児院とは名ばかりで、町では子供の収容所として有名だった。
そんなある日だった。
「おいお前ら!!今日の晩飯だ!」
僕たちは一瞬目を疑った。
「いいからさっさと食え!!!」
そこにはいつもの粗末な食事の他に僕たちの憧れとも言える、小さいながらもショートケーキがちょこんと皿に乗っていた。
「い、いただきます…」
「いっただっきまーーす!!」
本当に食べても良いのか、とチラチラと雇われ、通称マザーを見ておずおずと食べ始める者。
ここぞとばかりに勢いよく食べ出す者。
「「美味しい…!!」」
食事開始から20分。
ほぼ全員がショートケーキを食べ終えていた。
まだショートケーキが皿に残っているのは僕と斜め向かいの女の子だけ。
僕はなんとなくこの白いふわふわを食べる気にはなれなかった。
粗末な食事は変わらないのに今日に限ってケーキなんて高級なものを出してくる。
気味が悪くてとても食べられなかった。
「ね、ねえ…誰か僕のケーキ食べてくれないかな、?」
そう呼びかければすぐに人が集まってきて僕のケーキを賭けた盛大なジャンケン大会が開かれる。
「もういいや、ご馳走様。」
僕は椅子を引いて席を立った。
————————————
この孤児院は確かに環境は劣悪だが、2人で一部屋をあげるくらいの余裕はあった。
食後から1時間以上経った頃、僕は相部屋の子と話し込んでいた。
「それでね!明日から、は、ゆき…が……。」
僕の視界から突如として相部屋の友人が消える。
僕は慌てて友人の腕を取って脈を測る。
「…!!起きて、ねえ、起きてよ!!!」
脈はあった。
でも呼吸はとんでもなく浅くて、すぐにでも死んでしまいそうだった。。
「あ…大人、大人を呼びに行かなきゃ!!」
そう言って廊下を走っているとふと思い立つ。
「院長は本当に助けてくれるのかな、」
そう思った瞬間、この孤児院に味方がいない気がしてきた。
そこて僕は隣りの部屋の子に助けを求めることにした。
「ねえ!入ってもいい!?」
ドンドンドンとどれだけドアを叩いても返事がない。
嫌な予感を感じつつも僕は扉を開ける。
「…倒れている、!」
「2人とも、脈がない……」
その時、僕の頭に一つの仮説が思い浮かんだ。
決してそうあってほしくない、そんな仮説。
「まさか、あのショートケーキが…??」
そう思って呆然と立ち尽くしていると背後から足音が迫ってきた。
「まだ坊やが1人残っていたのか。」
「マザー、!?」
「欲に打ち勝ち、生き残った坊やには特別に教えてやろう。」
そう切り出し、マザーはにこりと微笑む。
「今日出たショートケーキ。あれはある種の毒だな。孤児院特製のショートケーキだ。」
「どく、…??じゃあもしかして皆んなの脈が無かったのって、、」
「ああそうだ、毒の効果だろうな。」
さもなんでもないことのように話すマザーに僕はどこか殺意に似たような感情を持った。
「お前、今日はなんの日か知っているか。」
今日は12月24日。
「クリスマスいぶ?」
「そうだ、クリスマスイヴだ。この孤児院に入る時、お前はこんな言葉を言われたはずだ。」
『この孤児院では牛乳や生クリームといった乳製品は食べられない。』
「そういえば…。」
「言ったはずだ、この孤児院は通称『子供の収容所』だと。この孤児院では生まれつき牛乳アレルギーのある子供を集めている。」
牛乳アレルギー?
「……なんで?」
「ここの院長は数十年前、妻と子供がいた。だが2人とも重度の牛乳アレルギーを持っていた。ある日訪れたレストランで不覚にも乳製品を口にしてしまった2人はそのまま呼吸困難で死んでしまった。」
「そこで院長は過度な牛乳アレルギーを持つ孤児を片っ端から集めた。」
「思い出せ、生き残りの坊や。昨日、やけに体調不良を訴えるやつが多かっただろう?」
「うん、確かにみんな頭痛いとか吐き気がとか、しょうはバラバラだったけどみんな言ってたよ。」
「それは一昨日の料理に仕込まれた伏線さ。わざと料理に細菌を繁殖させ、それをお前らに食わせた。」
菌?きのこだろうか。
いや違う。
これは…
「見事に体調を崩したお前らは今日、生クリームを食っちまった。そのまま呼吸が出来なくなってここにいるやつらは死んだ。」
エデンの園。
策略にハマり、言いつけを守れなかった僕たちはこの世から追放された。
このトピックは、名前 @IDを設定してる人のみコメントできます → 設定する(かんたんです)

