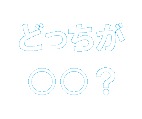川口市(かわぐちし)は、埼玉県の南東部に位置する市。中核市・保健所政令市に指定されている。
人口は約60万人であり、県庁所在地であるさいたま市に次いで県内2位。古くから鋳物や植木の街として有名である。旧北足立郡。
埼玉県の南東部に位置し、北はさいたま市、南は東京都足立区と北区に接する。さらに西は蕨市と戸田市、東は越谷市と草加市に接する。
江戸時代に日光御成道が整備され、川口宿と鳩ヶ谷宿が置かれていた。古くから農閑期を利用した鋳物が地場産業として盛んで、荒川のほか市内を縦断する芝川の舟運によって大消費地である江戸に運搬していた。明治時代の富国強兵政策により工業都市として急激に発展し、1910年に国鉄川口町駅(現:JR川口駅)が開業すると全国に鋳物が貨物輸送されるようになり、「東の川口、西の桑名」と言われるようになった。戦時中も鋳物の需要は高く、1940年に県内で唯一の新興工業都市に指定された。1958年に開催されたアジア競技大会は市内の鋳物師により製造された聖火台が使用されたが、その聖火台は1964年の東京オリンピックでも使用された。