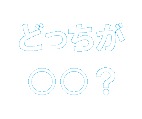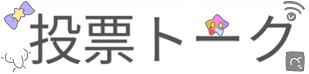「これはペンです」の「は」は英語に訳されるのか

「これはペンです」の英訳は皆さんご存知の通り "this is a pen" です。語に分けて訳すなら、thisが「これ」、isが「です」、a penが「(1つの)ペン」と訳されているというのが一般的な認識でしょう。日本語は膠着語といって、「が」「を」などの助詞を用いて主語や述語を表す言語ですが、英語は孤立語(部分的に屈折語ではありますが。ここでは重要ではありません)といって、語順によって主語や述語を表す言語です。ともすれば日本語の助詞は、英語に訳されるとき、自然と文面から消えてゆくことになります。つまり、英語には主語や述語を表すのに特別な語は必要ないので、その役割を担っていた助詞は(対応する語として)英文には表れないということです。それゆえ「これはペンです」が "this is a pen" になるとき、助詞の「は」は訳されていないように見えます。しかし、とある見方をすることでこの「は」はきちんと訳されていると見なすことができます。このことを本記事で説明しようと思います。
「は」と「が」の違い
外国語である英語を理解しようとする前に、母国語である日本語がどういう仕組みでできているのかを理解することから始めましょう。助詞の「は」が英訳されるかを考えるにあたって、「は」が日本語文中でどういう役割を果たしているのかを知る必要があります。「は」に似た役割を持つ「が」と対比しながら、その構造を見ていくことにしましょう。
ウィキペディア(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A9%E8%A9%9E)を参考にして調べると、「は」と「が」は両方助詞ではあるものの、「は」は係助詞で、「が」は格助詞であり、異なる助詞だということが分かります(中学や高校の重苦しい国語の授業を思い出すかもしれませんが、ここではそんなに難しいことはしませんのでがんばってついてきてくださいね)。係助詞は文の意味を強めたり、語を補足したりする補助的な語です。「は」はすでに話題として出ている事柄を取り立てて説明するときに使います。一方で格助詞は主語や述語を指定するための語です。とりわけ「が」は主語を表す、かつ話し手と聞き手で共通の理解が得られていない事柄について言うときに使います。百聞は一見に如かず、例文を見てみましょう。
太郎は公園にいます ←太郎については知っている前提で、どこにいるのかを説明している状況
太郎が公園にいます ←公園のことは知ってるけど、そこに誰がいるのかは知らないという状況
「太郎はどこにいるの」と聞かれて「太郎が公園にいるよ」と答えるのが不自然だということは日本人なら分かると思います。「太郎は公園にいるよ」と答えるのが自然ですね。また「公園に誰がいるの」と聞かれて「太郎は公園にいるよ」と答えるのも(文法的には正しいのですが)不自然です。「太郎が公園にいるよ」と答えたほうが自然です。これも感覚としてなんとなく分かるかと思います。以下、話し手と聞き手の間ですでに分かっていることを「既知」、分かっていない、つまり話し手がこれから聞き手に話そうとしている内容を「未知」と呼ぶことにします。
ここまでで分かったことは次のことです。係助詞「は」は既知の事柄を受けて未知の情報を伝える役割、格助詞「が」は未知の事柄を受けて既知の情報と結びつける役割を担っています。
・既知 は 未知
・未知 が 既知
つまり、「は」と「が」の違いは、既知の情報と未知の情報の提示される順番の違いであるということになります。この既知と未知を分ける概念は英語にもありましたね。
a/anとtheの違い
英語で未知と既知を分かつ概念は冠詞、すなわちa/anとtheです。a/anは不定冠詞と呼ばれ、聞き手と話し手で諒解されていない、つまり話し手がこれから話そうとしている名詞に付されます。theは、話し手と聞き手の双方の諒解が得られている名詞に付きます。
Taro is a student ←太郎については知っている前提(既知)、学生であるというのが未知の情報
Taro is the student ←ある特定の学生が話題に上がっており(既知)、それが太郎のことであると説明している(未知)
どうですか。日本語の「は」と「が」に非常によく似ていると思いませんか。
まとめると、日本語は既知と未知を分類するのが助詞の役割で、英語はそれが冠詞の役割になっている、という具合です。
さて、タイトルにもなっている「これはペンです」の「は」はどこに行ったのでしょうか。もうお気づきの方もいるかもしれませんが、ずばり "this is a pen" の "a" です。上で見たように、冠詞 "a" は、話し手がこれから聞き手に話そうとしている未知の名詞に付きますが、これは、未知の情報を導くために用いられる日本語の「は」と役割が同じです。「これは」"this is a"で既知の情報を取り上げ、今から未知の情報についてお話ししますよ、というサインを出します。「ペンです」"pen"で未知情報が補われ、文が完成します。(まあ、ペンであるということが未知な情報、つまり聞き手がペンのことを知らないという状況はまずありえないと思いますけどね。ペンだなんて言われなくても、見ればペンであることくらい分かるでしょうが。たぶん誰もが中1の英語の授業で抱いた感想だと思います。今の英語教育の現場知らないけど)
この話を使えば、いわゆるthere is構文では、後続の名詞には基本的に不定冠詞a/anが付き、theはつかない、ということも自然と説明がつきます。
once upon a time, there was AN old man
(訳)むかしむかし、おじいさん が いました
自然ですね。このanをtheにすると、
once upon a time, there was THE old man
(訳)むかしむかし、おじいさん は いました
たぶん、こんな書き出しの昔話はないと思います。だって変だもん。おじいさんがあたかも万人に知れ渡ってるかのような書き方。ただし、第2文からはおじいさん(old man)にtheを付けるのが自然です(もしくは代名詞で承けるか)。
the old man was...
(訳)そのおじいさん は ...
どうでしょうか。「は」と「が」、それからaとtheの概念は理解していただけたでしょうか。
おまけ(日本語の話)
一応英語についての説明は終わりですが、日本語を知らずして英語を理解することはできません。ですから、最後に日本語の話、とりわけ係助詞と格助詞の話をして記事を終わりたいと思います。前の前の項目で、格助詞は主語や述語を示すために使われると説明しました。しかし、「は」は格助詞ではなく係助詞だとも説明しました。それなら、逆に言えば、係助詞の「は」は主語を示すために用いられるわけではないということなのか、と言いたくなります(言いたくならなくてもいいです。この項目はおまけなので)。実はその通りで、係助詞の「は」は主語を示すための助詞ではありません。つまり、主語以外に続く助詞としても用いることができるということです。
太郎 は 学生です(主語)
英語 は 勉強します(目的語)
学校に は 行きます(修飾語)
一方で「が」は格助詞、主語を表す助詞なので目的語や修飾語を表すことはできません
○太郎 が 学生です
×英語 が 勉強します
×学校に が 行きます
これを心得ておくだけでも、たとえば英作文のときに「○○は~」という文言を見て愚直にそれを主語としてなんとか文を組み立てようとしてミスる、ようなことはなくなります(なくならずとも、おそらく減りはします)。「○○は~」という日本語を英語に訳せ、という問題が出たときには、まず○○が主語なのか目的語なのか、見た目からでは判断できない、つまり○○を目的語としても書けるかもしれない、というふうにして思考を巡らすことで、正答率の向上につながります。
また、係助詞というと古文(今では言語文化?っていうらしいですが)の係り結びの法則(なむが来たら連体形で結ぶとか、こそが来たら已然形で結ぶとか、そういうやつ)を思い出すかもしれません。係り結びは現代の日本語では使われないから係助詞のことを考えるなんておかしいのではないか、と思われた方がいるかもしれません。しかし、古文から現代文になるにつれてなくなったのは係助詞そのものではなく「係り結びの法則」だけです。係助詞はバリバリ現役ですよ。
まだまだ色々書きたいことはあるのですが、これ以上書くとタイトル詐欺になってしまいそうなのでここで終わりにしておきます。
まとめ
・日本語の「は」「が」は英語の "a/an" "the"
このトピックは、名前 @IDを設定してる人のみコメントできます → 設定する(かんたんです)