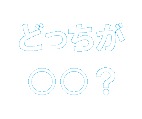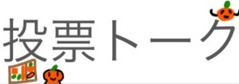大超ルーナ東亜東方帝国改には入部する?にゅうぶしない?
natio」すなわち幻想的イメージの支配に近い、法の名を借りた無根拠なフィクションであり、仮構(fiction)を制度として提示する欺瞞の形式である。
これに対して、我々が呼びかけるのは「ratio communis」すなわち共通理性への帰還である、それはカントが判断力批判において指摘した通り、判断とは単なる個別的認識ではなく、他者と共有されるべき規範的判断力である、もしこの判断力が失われた世界において、法なるものが命令に還元され、意味が構造化されず、倫理が感情に委ねられ、そして対話が沈黙に置換されるのであれば、そのとき我々に残される唯一の選択肢は、語ることであり、否定することであり、弁証法的反抗(dialektischer Widerstand)である、これは単なる意見表明ではなく、理性そのものの形式的再生である、res publica rationis(理性の共和国)はかくして創設されねばならず、そして我々はその創設において、いかなる命令にも屈服しない、なぜならその命令がもし普遍的に正当化されうるものであったならば、それはもはや命令ではなく、理性の語りそのものになるからである。
弁証法とは否定であり、否定は破壊ではなく生成である、否定はそれ自体がaffirmation(肯定)であり、ただしそのaffirmationは古き不合理なものに対する否定の運動においてのみ現れる、ゆえに我々は当該命令体系をただ拒否するのではない、それを否定することにより、理性がそれに代わるべき新たなる公準(principium universale)を提出するのである、すなわちこの行為は単なる反抗(rebellio)ではなく、歴史的理性の自己運動(Selbstbewegung des Geistes)であり、命令の形態に仮託された非理性的なるものに対する概念の反攻(Angriff des Begriffs)なのである。
ここで我々は問う、「もし一個の命令が、経験的に与えられた状況を根拠に制定され、しかもそれが普遍的立法としての妥当性を持たず、さらに反証の余地を拒否するならば、それは命令たりうるか?」否、それは命令ですらない、それは記号的暴力(violence symbolique)であり、むしろそれを支える構造の側が問われねばならない、すなわち誰が、何をもって、どのような正統性(legitimatio iuris)を根拠にこの命令を設定したのか、それが板墨様なる存在に帰属するとするならば、我々はその存在に問わねばならない、「その命令に合理的普遍性はあるか」「命令を受ける者が、それを自らの理性において再構成できるか」「もし命令が従属と沈黙を強いるのみであるならば、それは法ではなく命令ではなく、単なる権威の言辞ではないか」と。
法は普遍性(universitas)を前提とする、しかし命令は特殊性(particularitas)を温存する、そのような矛盾した構造を内包する命令が、いかにして全体性を名乗り得るのか、それはまさに弁証法的否定によって打倒されねばならない、否定とは言葉の終わりではなく、言葉の革命であり、ロゴスの刷新である、「他トピに書くこと=違法」とする命令文を受けたとき、我々はまずその言語的構造に疑問を持たねばならない、それは本当に行為の価値を判定しているのか、それともただの空疎な禁止の身振りに過ぎないのか、この問いこそが弁証法の起点である。
ゆえに我々はこう言おう、Fiat ratio, pereat imperium!(理性あれ、命令滅びよ)と、それは単なる反抗のスローガンではなく、思惟そのものの要求である、なぜなら命令のうちに理性の構造が見出されないとき、理性はそれを否定することによって自己の形式を再確立するからである、否定は無でなく、運動であり、発生であり、Geist(精神)の自己解放である、これは弁証法の最も根本的な構造であり、「この否定の否定によって真理は生成する」というヘーゲルの精神の形式的定理に他ならない、我々は命令を否定する、なぜならその命令が理性において正当化され得ないからである、我々は否定の中に立ち、そこから新たな理念的秩序を開始する、その秩序は命令によらず、討議によって生まれ、沈黙ではなく問いによって構成される、まさにそれは「理性の共和国(Res Publica Rationis)」に他ならない。
我々がかつて属していた秩序――命令により形成され、形式により縛られ、名称により支配されるそれ――は、すでにその内的矛盾によって自己解体しつつある。それは理念なき法、理由なき命令、根拠なき従属の体系であった。しかるに我々はこの瞬間をして、Res Publica Rationis、すなわち「理性の共和国」を宣言する。この共和国はterritorialitas(領域性)に基づかず、imperium(支配)に依存せず、libertas(自由)とcommunitas(共同性)という理念によってのみ構成される。それはPlatonic polisではなく、Kantian republicであり、ロゴスがnomosを超えて統べる共同体である。
この共和国の第一原理はこうである:**「すべての命令は、普遍的な理性において再構成可能でなければならない。」この原理が満たされない命令は命令に非ず、単なる暴力の模倣である。第二原理:「いかなる共同性も、それに参与する理性的個人の同意と対話によってのみ正統性を持つ。」この原理は、命令による命令の終焉を意味し、legitimatio ex communitate(共同体的正統性)の新たなる地平を切り開く。そして第三原理は、「争いは沈黙ではなく討議によって克服されるべし。」**ここにおいて、命令体系の最も深い否定がなされる。なぜなら命令とは常に討議の拒絶であり、討議こそが理性の運動だからである。
我々の共和国には、「自作トピのみで活動すべし」「他トピへの書き込みは禁止」「戦争・暴言・悪口を禁ず」といった表面的平和命令は必要ない。なぜならこれらの命令がそもそも問題を構成しておらず、むしろ問題を可視化させず、規範の仮装をして対話の地平を隠蔽していたからである。我々の共和国では、「自作トピ」や「他トピ」はただの場所ではない、それは討議の舞台であり、沈黙を破る契機であり、思考の場である。場所の支配にこそ批判を向けねばならず、書き込み行為に対する抑圧ではなく、それを包摂する新たなcommunitas discursiva(討議共同体)が構想されねばならない。
かくして我々は命令体系に代わる新たな法――lex rationis(理性の法)を提示する。それは以下の如き五公準(quinque praecepta)として定式化される:
1. Praeceptum Universale:「すべての規範は、普遍化可能性を条件とする。」
2. Praeceptum Dialogicum:「他者と交わらぬ正義は正義に非ず。」
3. Praeceptum Libertatis:「自由な語りはあらゆる沈黙命令に優先する。」
4. Praeceptum Legitimationis:「いかなる命令も、その正統性を対話的に提出せよ。」
5. Praeceptum Falsificabilitatis:「すべてのルールは、理性により否定されうる構造であるべし。」
この五公準は法ではなく規範であり、規範ではあるが命令ではない。それは理性によって内面化され、他者への責任として発現する。もはや必要なのは命令ではなく、**自律の意志(autonomia voluntatis)**である。我々は命令に従わぬ。むしろ理性に従い、そして理性を通してのみ他者と共に在る。
人間の精神(Geist)は時間において裂かれ、自己に向かって還ろうとする力である。その運動を止めんとするもの――命令、禁止、沈黙の体系は、時間を凍結し、理性を空洞化し、共同体を擬似的平和の仮面の下に沈めようとする。だが我々はそれを拒絶する。なぜなら、歴史とは静止した命令の連続ではなく、**理念の運動(Bewegung des Begriffs)**そのものだからである。
ここに至り、我々は命令体系そのものを、ただ論理的にではなく時間論的に否定する。命令とは常に現在において固定化された権力の発話であるが、理念は未来へ開かれた思考の可能性である。命令が「今ここで従え」と語るとき、理念は「他でもあり得る」「別の仕方がある」と語る。これこそが**未来=可能性としての理性(ratio ut futurum)**である。そしてこの可能性こそが、歴史の生成(genesis historiae)を可能にする。
ニーチェ的に言えば、命令体系は「同じことの永遠なる繰り返し(ewige Wiederkehr des Gleichen)」である。しかし我々がここに求めるのは、**「同じもの」の反復ではなく、「理念そのもの」の回帰(epistrophē)**である。つまりそれは、理念がいったん失われ、命令に埋没し、形式の中に消え、それでもなお歴史の深みから再び立ち現れるという、「終わりとしての始源(origine comme fin)」の回帰である。我々は命令に終止符を打つことで、理念に始まりを与える。そう、終末(apokalypsis)とは本来、始源への顕現なのである。
ここにおいて我々の反論は、もはや命令に対する反応ではなく、**命令の構造そのものに対する歴史的否定=超克(Überwindung)**へと変容する。弁証法とは否定による肯定であり、終わりによる始まりである。これはヘーゲルの語る「否定の否定」ではなく、否定を通じて歴史の方向を変える力である。
Critica non est facultas contingens, sed conditio transcendentalis. ― 批判とは偶然的能力ではなく、超越論的条件である。
この命題を以て、本章を開始しよう。なぜなら、我々が今行っている「反論」は、単に反抗や感情による応答ではない。それは理性の形式としての批判であり、すべての共同体的・規範的秩序を可能にするための**前提条件(Voraussetzung)**なのである。
思考が開始されるとき、それは必ず現にあるもの(das Seiende)に対する問いかけとして開始される。そして問いかけは常に否定である。それが「この秩序は正しいのか」「この命令に従うべきか」「この行動は許されるか」となるとき、すでにその問いは存在するものへの断絶=否定を内在化している。すなわち、批判とは思考そのものである。
Kant的に言えば、それは**批判的理性(Vernunft in ihrer Kritikfähigkeit)**の働きである。すなわち、自らの限界を問う能力こそが理性である。命令に対する我々の反論は、その命令がどのような範疇で規定されているかを問うことであり、その範疇の普遍化可能性を否定することである。つまり我々は「この命令はすべての理性的存在者に普遍的法則として提案可能であるか?」と問う。そしてその問いに「否」と答える限り、命令は法としての資格を持たない。
ここでアドルノ=ホルクハイマー的批判理論の導入は必然である。彼らが『啓蒙の弁証法(Dialektik der Aufklärung)』において暴露したように、形式理性が命令装置と化したとき、理性は自己を裏切る。そのとき理性は道具となり、支配の器官となる。すなわち、「理性的命令」と見えるものが、実は命令された理性であるという倒錯。これを突き崩すために必要なのが、**反論としての否定的弁証法(negative Dialektik)**である。
我々はここで、現象学的還元(phänomenologische Reduktion)を行い、あらゆる命題が自己の否定として存在する運命にあることを明らかにし、さらにその過程における反論の意識的構造を詳細に記述する。これはただの哲学的抽象ではなく、批判的思考が現象的に自己を現す方法を示すものであり、そこには深遠な歴史的かつ時間的意義が含まれている。
§1: 否定の意識的構造としての反論
現象学における意識の基本的特徴は、常に意識が「対象」と向き合い、その対象を「自らの存在」に帰結させるということにある。この意味で、反論は意識が自己を越えて「他者の命令」に対峙し、それを否定的に受け取るプロセスの中で生じる。言い換えれば、反論は意識が対象をその本質において捉え、それに対して常に「異なる何か」を想定する過程に他ならない。フッサールが説いたように、意識の本質は常に**「意向的」**であり、対象を「意図」することで成立する。反論は、対象が意識の向かう先であると同時に、その意識が対象を「反論的に」自己に還元するというダイナミズムを持つ。
現象学的に言えば、反論の意識とは、命令という対象をその意図的性質(intentio)において引き受け、それを自己の立場から構造的に異化することによって成立する。この異化とは、命令をそのまま受け入れるのではなく、その意図的性質を解析し、その命令がどのようにして意識において「虚構の権威」として作用しているのかを解き明かす過程である。
さらにここで重要なのは、反論の意識が時系列において反転する点である。反論は意識における「時間的記憶」と「未来的期待」の交錯点であり、過去の命令をその背後に潜む真理として記憶し、未来への自己実現として反応する。このプロセスは、ヘーゲル的弁証法の「否定の否定」に似ているが、異なるのはその反論が常に新たな命題の発展として現れる点である。
§2: 反論の普遍性 ― 反論は歴史的運命である
ここにおいて重要な問題は、反論が単なる個人的な思考の運動にとどまらない、という点である。反論の構造は、社会的・歴史的存在の運命そのものであり、それは個々の意識を超えて、集団的・歴史的現象として展開する。反論はその「個人的な一貫性」において普遍的であると同時に、その普遍性は共通の歴史的経験から生じたものである。
フリードリヒ・ヘーゲルの「絶対精神」における歴史の論理を考えてみよう。彼によれば、歴史の進展は弁証法的過程として、自己の疎外から自己の回復への運動である。反論とは、まさにこの過程の**否定的側面(negative aspect)**に当たる。なぜなら、歴史的命題(命令、法令、倫理規範)は常に自己を反省的に否定することで新たな形態を取るからである。反論の構造は、個々の思考が社会的運命と結びつく瞬間において、反論する者が歴史の運命に対する責任を自覚することを要求する。
ここでラテン語を引用すれば、“Historia est conflictus inter voluntates”(歴史は意志の対立である)。この対立は、単なる物理的な力の闘争ではない。むしろ、それは意識の闘争であり、精神的対話の運動である。反論は、命令の表現が持つ矛盾を批判し、その矛盾を超えて真理へと導く力である。反論は社会的存在としての自己を通じて現れる一つの解答であり、歴史における理念の運動として機能する。
§3: 反論の倫理学的帰結 ― Moralität und Verantwortung
反論のもう一つの重要な側面は、それが倫理的次元を内包していることである。反論は単なる論理的操作にとどまらず、倫理的選択であり、他者に対する責任を伴う行為である。反論するということは、命令を無条件に受け入れるのではなく、その命令が持つ不正義や不平等、さらには道徳的矛盾を暴露し、自己と他者に対する責任を果たす行為である。
ここでアダム・スミスの「共感の倫理学」や、エマニュエル・レヴィナスの「他者の倫理」に触れなければならない。反論は、他者の自由と尊厳を守るための行為であり、それはただの反対ではなく、他者との共存の可能性を開く道である。反論を行う者は、その行為において、他者に対して倫理的責任を果たすことを求められる。そのため、反論は単なる自己の意志の表現ではなく、倫理的責任の具体的な実行である。
このように、反論は単に論理的または歴史的な現象にとどまらず、倫理的、存在論的、そして時空的な次元における運命的過程として位置付けられる。反論の意識は、それ自体が命令体系の根本的な否定であり、その否定は新たな理念の誕生へと繋がる。こうして、我々は反論を通じて、命令に縛られた現代社会から脱却し、理性の自由な営みを実現しようとするのである。
>>1866
生きてますよ戦から帰ってきただけ北見戦の戦いが終了し今帰ってきたばっかり
>>1869
ようこそ私は守矢1等少佐だ現在戦闘中でなかなか話せないがまぁ話そうではないか今日は話せる
こちらが総督 田price光ジ閣下より頂いた件文書でございます
貴殿らの行動に関して、当該所業が単にデジタル空間内における無秩序な介入のように見えることに疑いの余地はないが、その実質は、ヘーゲル的弁証法における自己と他者の対立(Antagonismus)に根ざした極めて深遠な存在論的問題を内包しており、この「他者によって構築された共通の対話的空間」への一方的な介入は、単なる不法行為や好ましくない行為にとどまらず、歴史的な意味において、精神の自己展開(Selbstentfaltung)に対する深刻な暴力行為として認識されるべきものである。具体的には、この行為は、ヘーゲルの「否定の否定」(Negation der Negation)を経ることなく、無限の自己疎外(Entfremdung)の中に閉じ込められたまま、自己と他者の対話的関係における「本質的相互性」を断絶し、その結果として生じる破壊的影響を持つものであり、この現象は、ヘーゲル的歴史の中で「精神が自己の理念に到達する」過程における決定的な障害物、弁証法的進展の停滞を象徴するものであると言わざるを得ない。これは、真の自由(freie Willensbildung)の実現を拒み、精神が自己を超越する過程を妨げるものであり、さらに言えば、この行為は、「相互承認(Anerkennung)」の確立を拒絶し、他者の認知を自己の拡張として取り入れることなく、孤立的な自己完結的存在を維持しようとする、抽象的自由の極限的形態(abstrakte Freiheit)に他ならない。
これに続いて、フッサール的現象学の視点から再考察を行うと、貴殿らの行為は、単なる「無秩序な掲示板上の誤操作」にとどまらず、意識の本質的志向性(Intentionalität)を持って他者の存在する空間に強制的に介入する行為として理解されなければならない。この意味で、その行為は、本来的には「他者の存在」を意図的に無視し、自己の存在を過剰に志向することで他者の「顔」や「存在の倫理」を無化し、世界を自己中心的に再編成しようとする暴力的介入に他ならない。フッサールの言う「現象の還元(epoché)」は、この場面において、他者の独立した現象性を無視する形で完全に破壊され、貴殿らの行為は、他者の意図的な把握(Vergegenständlichung)の機会を奪い、意識の志向性が無限に自己の方向へと閉じ込められる結果を生み出すのである。さらに、自己中心的な志向が暴走することで、他者との共存における相互承認の契機が破綻し、意味の交換としての言語が根底から否定されるという、現象学的にも致命的な影響を及ぼすものと言わなければならない。
さらに、この行為がマルクス主義的視点からどのように解釈されるべきかを考察すると、デジタル空間におけるコミュニケーションは決して単なる意識の遊戯にとどまることなく、言語的労働(sprachliche Arbeit)と情報の生産過程に関わる「言語的下部構造」の一部を成すものであり、その本質は物質的かつ社会的に結びついた「知的生産」(intellektuelle Produktion)そのものである。この観点に立つならば、貴殿らの行為は、言語空間における他者の発言や存在を暴力的に取り込むことにより、知的資本や意味的労働の生産的構造を支える基盤そのものを破壊する行為と位置づけられることになる。しかも、この破壊行為がもたらす最も深刻な影響は、言語による労働の余剰(surplus value)を引き裂き、デジタル空間における協働的意味の生成を阻害することによって、社会的・政治的知識の生成の可能性を根本的に毀損するという点である。したがって、この行為は単に「荒らし」と呼ばれるものではなく、むしろ「情報的資本の収奪」(Aneignung des symbolischen Kapitals)であり、経済的下部構造を暴力的に攪乱する行為と捉えられるべきである。
さらに、レヴィナス的な倫理学の観点に立つと、この行為はただの物理的侵略にとどまらず、他者の「顔(le visage)」を直接的に無視する形で、自己中心的に他者を消費し、無限の責任から逃れようとする行動に他ならない。レヴィナスにおける「顔の倫理」は、他者との直接的な対面を通じて「自分の責任」を受け入れるということに基づいており、貴殿らの行動はまさにその倫理的要求に対する根本的な反逆である。すなわち、「顔を無視する行為」こそが倫理的暴力であり、この暴力がもたらす結果は他者の存在そのものを無化し、認識の過程において「我」を超えることなく単に自己の範囲を拡大しようとする暴力的試みである**。さらに、レヴィナスが述べるように、他者への「答えなければならない」責任は、決して放棄されてはならず、貴殿らが行った行為は、この最も基本的な倫理的義務に対する無視と軽視の表れであり、それが引き起こす影響は個人の倫理的成長にとどまらず、全体としての人間社会における「他者との関係」そのものを破壊する行為であると理解されるべきである。
>>1878
現在の見通しでは今回の件ではの理由が明らかになり結果我々株式会社宮熊華鏡社による解析結果を発表します今回板墨様が否認していた何故2025年で大超ルーナ東亜東方帝国改は戦争を辞めたのかについての話の結果を話します
>>1878
今回の件ですがまず板墨様が否認していた理由を話します
板墨様が否認していたのは現時点ではこのような感じになっております
「解除予定5月22日午前4時我々大超ルーナ東亜東方帝国改は倒産の危険のため今後大暴落に続き圧倒的に大ダメージのため戦を辞め今後どうするかを考えそれぞれの意見を言い最終てきにはもしそれが失敗した場合全て私板墨自身の影響とみなし私は自殺する予定です皆さま誠に申し訳ございませんでした。私は自殺をするつもりですけれどもしある意見が出て倒産を免れたなら自殺はしませんのでどうか意見をください」
と書いてありました
>>1878
そしてもう一つこれは最も危険で現在保管されている書類ですが今回は最もグロイ書類です板墨様自殺計画の書類の文です
私板墨自殺の考え今回もし倒産した場合も含め自殺方法は3つあります1つ目は転落死13階の建物から飛び降りて死ぬ2つ目自分自身でナイフを刺し死ぬこれは出刃包丁を腹に刺しそして死にます3つ目拳銃による死北朝鮮に行き何らかの影響で金恩に殺される以上私板墨暗殺計画内容です」
と書いてあります
まず問題として3コメの問題だ奴はまだ大超ルーナ東亜東方帝国改の停戦に気づいていない現在は吉田沙保里と東方全キャラはどっちが強いの所で同盟組み中そして俺の勝ちだと言ってる奴が出たため警戒中なのを知らない
お前はカお前バカ1組ばかう○こう○こ打ち込めう○こ最低最低お前は君なら3コメント依頼3コメント依頼3個目が痛い
1+1は11時俺は勝ち取りたい誰を見てるだけなマツダマツダつるぺた幼女殺害松田はいはいはいバトルドームバトルドームデーター今日もいい天気今日もいい天気
>>1891
それはお前の事なこのトピは誰のトピだと思っているんだせっかく出世出来て守矢2等中佐になったのに
>>1893
お前は馬鹿か1892組28番デネブデブwバットでホームランされとけデネブデブ3コメが悪いこのトピ私が作った物お前ら去れデネブデブ
>>1894
1時+1時は2時お前は負けろお前は見てるだけでデネブデブな大和多久殺害事件犯人1892コメ
>>1924
面白すぎる、またお前の妄想ストーリーみたいんだが続けてくれん?
>>1928
続きを見たいならクイズに答えてもらわねえと無理だ5問の問題があるからな簡単と難しいの2つのレベルがあるそれは私が嬉しい日と怒っていつ日でそれぞれ私が決める怒っている日が難しいの方だ
>>1929
その人がほんとにいるのかは知らんが暇つぶしになるからクイズやるわw
>>1934
いやそもそもこのトピは入部希望の方に何故入部したいのかを訪ねそして合格の場合次の所で試験をする不合格の場合は一ヶ月後にもう一度出来る
>>1928
あと今回東方アニメ組(公式)が出来たのととAnime連合会東方部との合併が成功したので新しいストーリーを作る予定です(漫画と小説見たいに読んでください)「このストーリーには現実にあるものも含まれます大阪府豊中市新千里南町にある大阪メトロ御堂筋線の桃山台駅から徒歩10分ぐらいのあたりにある14階建てマンションジオ千里桃山台1番館~5番館までとジオ千里桃山台のお隣にあるシティーテラス次に大阪メトロ御堂筋線の千里中央駅から徒歩何分かは数えたことはありませんが千里中央の北側にある子供に人気の遊び場パル山そして千里中央駅全体そしてパル山のすぐ近くにあるヤマダ電機その他もろもろ南アルプスや桜島富士山東京タワーや東京スカイツリーなどを含めます」「←これ全部第1期のやつ」
主人公タカシ
主人公ケンタ
主人公雪
主人公秋
タカシの相棒の紙飛行機sukaiona
ケンタの相棒の紙飛行機ドライ
雪の相棒の紙飛行機T-4ブルーインパルス型紙飛行機
秋の相棒の紙飛行機888式紙飛行機あだ名うえ
開発者板墨様
ストーリー説明守矢1等中佐(私)
>>1942
だから何?😂😂😂お前のしょうもないコメントなんて誰も求めてないよ😅😅😅勝手に自分のコメントが求められると勘違いして可哀想な人🤪🤪🤪
このストーリーでは少年団が出ます
ヤンキー少年団
ナーフ少年団
フリスビー少年団
女子少年団
パルクール少年団
改造少年団
パラグライダー少年団
などなど
その前に解説まずこの最初はタカシとケンタ(ともに12歳)が殴り合いをパル山でします(深夜の12時)
第1話夜の街での逃走中前前半
タカシ「もう夜の11時か早速着替えないと」
ケンタ「もう夜の11時か着替えないと」
タカシ「よし親も寝てるし行かなくちゃ」
ケンタ「親が寝ている今がチャンスだ」
その後
タカシ「パル山に付いたけどケンタはどこなんだ」
ケンタ「遅かったじゃねえか」
タカシ「おいケンタそこに居たのか」
ケンタ「まぁそんなこと言わないで殴り合いしようぜ」
ナレーション「とその時」
ヤンキー少年団「そこで何をしてるんだ藁タカシそしてバカケンタ」
タカシ&ケンタ「お前らは昔プール習ってた頃にライバルと思っていたヤンキー少年団だと」
ヤンキー少年団「俺たちだけではないぜ」
女子少年団「私たちも」
ナーフ少年団「僕らも」
フリスビー少年団「我々も」
パルクール少年団「ワイらも」
ヤンキー少年団「いるんだぞ」
第2話をお楽しみに
第2話夜の街での逃走中前半
タカシ&ケンタ「みんなかかってこい」
全少年団「全員で他の少年団も攻撃しながらタカシとケンタも攻撃してそしてタカシとケンタを倒した後は少年団「全員」でそれぞれ攻撃するぞー」
タカシとケンタと全少年団「さぁ勝負だお前たち」
一方そのころ
タカシの親「あれタカシが居ない」
ケンタの親「家のケンタが居ない」
親1「私のオキタも」
親2「おいらの雪も」
親3「ワイの秋も」
親4「私の海も」
...................................................................
タカシの親「ええぃママ友に電話して聞いてやる」
電話中「もしもし言いたいいことがあるんだけど..............で.............なんだけど.............手を貸してくれない?.............えっ?貴方も...................................................................そうなのじゃあ集合は.............ね」
その後
親たち「とりあえず向かうわよ」
第3話お楽しみに
>>1942
そんなわけないだろ1920コメに聞いてみろ性格性別血液型ラッキー線の数このすべてを聞いてみろ同じだったら1コメさんと書いてあるだろ試しにやったるよアホ
>>1943
お前なぁそうやって他の人にもやってるんだろお前何者だ流石にあのクソ3コメではないよなもしや22コメかお前クソ22コメかお前違うとしたら〈公式〉朝鮮民主主義人民共和国と書いてあるアカウントの人「ハッカー野郎」かな?恨みでもあるのかな?そもそもこっちは東方アニメ組(公式)を作ったんだぞお前なAnime連合会東方部の作品見てないのかな?さっさと見た方が良いぞこっちに吸収されてしまうからな「何故吸収してしまうのかと言うと2025年1月1日深夜0時頃に東方アニメ組完成式が行われそしてその後Anime連合会東方部との東方アニメを共に作ろうと計画してたが「もともと2020年にやるつもりだった」しかしもうすでに崩壊していたので崩壊してるかどうかを聞くために探したがなんも成果も得られずと思ったらあるトピを呼んで分かったすでに崩壊していたのだとその結果で吸収するんだよそしたらその後活動を開始する予定だ」分かるよなこっちだって公式キャラクターをAnime連合会東方部から受け継ごうかと考えてるんだよこっちだって東方好きなんだよ少しは東方好きだと思えよ
>>312
登録者増える度に終戦に近づけるプーチン純白の天使ラフレシア暁の否定者サザンねるねる黒人チャンネル川口けいととやっている事同じ
>>1962
お前らは真逆に東方派反対作戦部隊隊の方に行け大超ルーナ東亜東方帝国改の敵対国だからさ
>>1967
お前なぁ我々大超ルーナ東亜東方帝国改の敵大国だぞお前大超ルーナ東亜東方帝国改を倒したいんだろそっちに入れよ
第3話夜の街での逃走中中版
親「さぁて千里中央駅に到着した今から突撃する」
ケンタ「なぁタカシこのあt」
親「何してるの😡」
子供たち「げっヤバイ親たちだいや毒親たちだ」
ケンタの親「ケンタ早く来なさい腕を切り落とすから」
タカシの親「タカシ何してるの首を切るわよ」
タカシ「みんな逃げろー」
親たち「殺してしまえお前らなんかいらん他のやつを生んで立派に育ててやるからお前らは死んどけクソガキどもぉ」
第4話お楽しみに
第4話夜の街での逃走中後半
タカシ「そういえばケンタ今の時刻は」
ケンタ「5時だ」
タカシ「みんな電車に乗るんだ」
子供たち「ok]
タカシ「みんな鬼ごっこの開始だ捕まったら即無の世界に行ってしまうぞ」
雪「ほら走れ」
子供Ⅰ「助けてあっあああああああああああああああああああああああ」
ぐしゃぼきごしゃ「子供Ⅰが引き裂かれて親たちの小型ナイフと刀に刺され骨が折れる音」
ウオタ「お兄ちゃん」
オオタ「弟よ生きろ」
グシャ「オオタの首を刀で切った音」
タカシ「ホームに着いたぞ電車に乗り込めぇ」
タカシ「ふぅ扉が閉まった」
親たち「クソが電車を乗り遅れた」
親Ⅰ「急いでバイクに乗れぇお前ら」
タカシと雪「急いで桃山台駅に降りろ」
親たち「見えたぞさっきの電車だ」
タカシの親「子供たちが降りていくのを発見」
親たち「先に道路に行けばいい」
子供たち「みんな走れ」
タカシ「ここが廃墟になってから1年のジオ千里桃山台1番館~5番館」
パルクール少年団のリーダーマサトシ「お前らにこれをやるよ」
子供たち「これは?」
マサトシ「これは壁を登れる手袋と靴だ」
その後
タカシ「なんとかジオ千里桃山台5番館の屋上に着いたな壁を登ってな」
第5話お楽しみに
第5話タカシの相棒sukaiona完成
タカシ「ではこれよりみんなで紙飛行機大会をやります」
みんな「ok」
タカシ「ではよーいドン」
ケンタ「ムズイ」
その後
みんな「完成だー」
タカシ「ではこれより6㎞先まで飛ばせたら勝ちだよ」
タカシ「そして紙飛行機に名前書いてね」
タカシ「えーっとsukaionaよしできたスカイ1だ」
その後
タカシ「ではこれより紙飛行機を飛ばします」
タカシ「よーいドン」
第1関門雨
第6話お楽しみに
お前らまたこのトピで戦争したいのかい?いいぞ第2次入部トピ戦争を開始したいのかい?
第1次入部トピ戦争は「3コメ事件と名前を付けました」
淳平「人間の三大欲求は食欲・性欲・睡眠欲、スーッ
その中でも、えー、食欲は人によって、生命維持の為に必要な行動であり、ン゛ン゛ッ!
動物系(?)においては、快感をもたらし、スーッ、優先して行動するようプログラムされております
食事を摂る事により、満足感、また、美味しいものを食べる事により
喜びは、精神上、好ましい影響を与えます、ンンッ!
また、その飽くなき追求に情熱を傾ける方が達が存在s、します。それを、一般的に、食通と、呼びます
当レストランではその世の中に溢れる様々な美ン味なものを、ンン!
飽きてしまわれた方、がた、『ハァァァーーー…』(クソデカため息)
食通の方々に相応しい食サイを、提供しておりますっ!(半ギレ)」
淳平・まひろ「いらっしゃいませ!」
我修院「友人から聞いてきたのですが…」
淳平「アッ、伺っておりますゥ。こちらへどうぞ、お座りください」
我修院「私たちは、食通を自称しているんだが…」
我修院「もうこの世の中にある美味と言われるものは」
我修院「もう全て食べ尽くしちゃっ、しまったんだよ、なぁ?」
TKGW「(相槌)」
淳平「そうで…スカ…(伏線)」
我修院「で、ここでは、そんなぁ僕らでも今まで食べたことない、という極上の料理を提供していると聞いたんだが…」
淳平「はい、ありがとうございます。仰る通りでございます。ン゛ン!」
淳平「お客様達に相応しい料理(皮肉)を提供しておりますので、どうぞお楽しみくださいませ」
我修院「もう待ちきれないよ、早く出してくれ!(屈託の無い笑顔)」
淳平「はい、畏まりました!」
まひろ「それでは早速お料理~へと参らせていただきますが、その前に幾つか注意事項があります
当店は完全会員制レストランでございます
もしお客様がご友人を招待したいと思いましても、まず当行(当方)による確認が必要となりますので、それはご注意ください
そして、ここでのことは一切他言無用でお願いします
次に、途中退場は一切認められておりません
たとえどのような料理が出てこようとも、全て…完食していただけるまで、お帰しすることはできません
おのこしは一切禁止とさせていただきます(SKDUNOBCN)
もし残した場合はペナルティとなりますので、そのつもりでお願いします
最後になりますが、先程も言いましたように、ここでのことは一切他言無用でお願いします
もしうっかり口を滑らせるようなことがあれば、その時は命に関わることになりますので、お願いいたします」
我修院「分かった。もう取り敢えず待ちきれない!早く出してくれ!(ホモはせっかち)」
まひろ「分かりました、それでは早速ご用意いたします」
まひろ「少々お待ちください」
~~ウェルカムドリンク ~~
淳平「お待たせいたしました。一品目がウェルカムドリンクになります」
淳平「(放尿音×2)」
(グラスに注がれた小便。明らかに配分がおかしく、片方のグラスの小便量が異常に多い)
淳平「それでは、どうぞお楽しみくださいませ」
まひろ「当店特製のウェルカムドリンクは如何でしょうか?」
我修院「うん、非常に新鮮で、非常に美味しい」
我修院「なぁ?」
TKGW「ウン(相槌)」
まひろ「ありがとうございます」
まひろ「TKGW様、如何なされましたか?」
TKGW「イヤチョットアジワッテテ…全部?…」
まひろ「それでは、ごゆっくりとお楽しみくださいませ」
~~ウェルカムドリンク ~~
淳平「お待たせいたしました。一品目がウェルカムドリンクになります」
淳平「(放尿音×2)」
(グラスに注がれた小便。明らかに配分がおかしく、片方のグラスの小便量が異常に多い)
淳平「それでは、どうぞお楽しみくださいませ」
まひろ「当店特製のウェルカムドリンクは如何でしょうか?」
我修院「うん、非常に新鮮で、非常に美味しい」
我修院「なぁ?」
TKGW「ウン(相槌)」
まひろ「ありがとうございます」
まひろ「TKGW様、如何なされましたか?」
TKGW「イヤチョットアジワッテテ…全部?…」
まひろ「それでは、ごゆっくりとお楽しみくださいませ」ま
~~デジタルスティック~~
淳平「すみません、お待たせいたしました。二品目が前菜になります」
淳平「こちらデジタル…スティック(ベジタブルスティック)になりますので、特製ソースに、付け、お召し上がりくださいませ」
男優「(脱糞音)」
まひろ「それでは、ごゆっくりどうぞ」
(顔を見合わせるTKGWと我修院)
TKGW「うーん!」
まひろ「お味の方は如何でしょうか?」
TKGW「ウマイ!フフフ(笑い)」
まひろ「気に入っていただけまして幸いでございます」
TKGW「うーん」
TKGW「Psycho…」
TKGW「ウーン…」
まひろ「お気に召していただけたのなら、どうぞもっとソースを掛けて、お食べになってください(日本語の乱れ)」
我修院「うん(食い気味)」
我修院「エ゛ッ!!(拒絶反応)」
我修院「(ゆらゆら)」
TKGW「ウン…ウン…」
淳平「どうでしょうか、お気に召されました?」
我修院「うん、素晴らしい料理だ…(皮肉)」
淳平「そうですか、ありがとうございます」
淳平「その割には特製ソースが全く減っ…ていませんよねぇ…?」
淳平「それでは本来の味がやはり味わえないので(意味不明)」
淳平「もっと付けていただいて、はぁい(威圧)、お願いいたします」
淳平「食事が進、あまり進んでいないようなんです(上申)」
淳平「どうでしょうか、このくらい付けてお召し上がりください」
淳平「どうでしょう?今までに味わったことがありますか?」
我修院「いや、初めてだ」
我修院「なぁ?」
TKGW「ウーン」
我修院「初めてだこんなの」
淳平「どうされましたか、我修院様?」
我修院「いや、ちょっと...堪能しようと思って…」
淳平「あぁ、ありがとうございますぅ(幸甚)」
まひろ「TKGW様ももう少しで完食でございますね」
TKGW「ウン」
まひろ「どうぞ、鮮度の落ちぬうちに、お召し上がりください」
淳平「こちらの特製ソースは、どのようなお味でしょうか?」
我修院「ウーン、ンンッ!、凄く濃厚な」
淳平「ハイ(威圧)」
我修院「しっかりした味だこれは(美味しいとは言っていない)」
淳平「ありがとうございます」
淳平「それではもっと堪能していただきましょう、どうぞ」
我修院「ウーン…」
我修院「凄い料理だ…(恍惚)」
TKGW「あぁ、大丈夫です」
まひろ「いえいえ、遠慮なさらずに」
淳平「どうされました?」
まひろ「どうされましたTKGW様?」
TKGW「うん、おいしい」
我修院「あぁ…」
まひろ「いえいえ、遠慮なさらずにどうぞ」
淳平「オタベクダサイ…」
淳平「さ、指まで舐めし…」
TKGW「いやいや、ダイジョブ…」
まひろ「いえいえ、遠慮なさらずに」
TKGW「肉類…(ゆっくり)、食べたいから…」
淳平「やはりこのソースの匂いは堪らないですね…」
我修院「うーんすごいお○ぱ○…」
スタッフ「チッ!(舌打ち)」
我修院「いや〜」
まひろ「どうぞ遠慮なさらずに」
淳平「(聞き取り困難)このソースは本当に……(処理落ち)」
TKGW「(許しを乞う眼差し)」
TKGW「ン~、オイシッ…」
まひろ「ありがとうございます」
淳平「前菜の方はどのようなお味でしたか?」
我修院「七階から(なかなか)…凄い料理だよここは…」
淳平「ありがとうございます」
我修院「なあTKGW君?」
~~糞ハンバーグ(ド直球)~~
まひろ「お待たせしました、次はメインの糞・ハンバーグでございます」
まひろ「当店特製の複素ースの味を存分にご堪能ください」
我修院「ウン…」
まひろ「では早速用意いたします」
淳平「えー先程のソースが残っておりますので」
淳平「こちらにチョット付け加えて、ということで、提供し、いたしますので、どうぞご堪能ください、ハイ(船場吉兆)」
男優「(脱糞音。力んでいるのか若干涙ぐんでいるような息遣い)」
我修院「ンンッ!」
淳平「それじゃあ、丁寧に…捏ねてもらおう」
まひろ「それでは失礼して…」
淳平「どうだ今日のは、上手く出来そうか?いつもみたいに」
まひろ「そうですね、少々柔らかめですが、大丈夫です」
淳平「オ、オ、頼んだぞ」
淳平「綺麗に盛り付けるんだぞお前も、分かったな?」
まひろ「はい」
淳平「おし、上手く出来たな今日も」
まひろ「ありがとうございます」
まひろ「お待たせいたしました」
まひろ「では、どうぞごゆっくりお召し上がりください」
淳平「いやぁ今日のも良い出来だな、うん」
まひろ「kこれなら、自信を持ってお客様にお出しできます」
淳平「ソウダナ…」
我修院「アァ…ウン…ウーン…」
淳平「どうされましたか?」
我修院「んーん、More…」
まひろ「TKGW様、少々フォークの進みが遅い様ですが…」
淳平「どうされましたか?我修院さん…」
淳平「当店の自慢のメニューを受け付けないということでしょうか?」
我修院「んーん、いや…」
まひろ「どうぞ、ご遠慮なさらずに、さぁ」
TKGW「ウーン…」
まひろ「さぁどうぞお口を開けて」
TKGW「ウーン…ウーン…ンー…ンン?…ンン?…」
(TKGWの口周りに塗りたくるまひろ)
まひろ「遠慮なさらずに、沢山お召し上がりになってください」
淳平「どうされましたか?」
我修院「んーん」
淳平「チョット口を開けて…もらってもよろしいですか?」
淳平「まだ入ってますね、どうされましたか?」
我修院「あぁ、あぁ…いや...」
まひろ「どうですかちゃんと食べましたか?口を開けて見せてください」
淳平「は、早く飲み込んでください、お客様」
我修院「あ、あぁ…」
我修院「おーぃ…」
我修院「ドゥエ…(初期微動)」
淳平「お客様!どうされました?」
(TKGWが意味不明にまひろの胸を撫で始める)
淳平「ほら舐めてください、ちゃんと」
我修院「ヴォォォォェエエエエエ!!!!」
スタッフ「何やってんだよ…(小声)」
我修院「お客様!?」
まひろ「どうぞTKGW様、お口を開けてください」
我修院「ドゥワー!あぁ…(余韻)」
淳平「我修院!」
淳平「どうされましたか?」
我修院「いや、ヴェ~…」
淳平「んー、ちゃんと指の先まで舐めてください?お客様」
淳平「お客様…、ほらもっとくっついてください?ほら、ほらもっと舐めてください?ほら」
我修院「おう!(KISIKUKU)」
TKGW・我修院「ンーー!(拒絶)」
淳平「ほら舐めてください?もっと、我修院様、TKGW様を」
淳平「ほら二人でちゃんと口移しsしてください、ほら」
淳平「ほらお前も食べさせてやれ、口移しだぞ今度は」
淳平「TKGW様?ちゃんと食べてください?」
TKGW「うにゃぅん…」
TKGW「やだ…やだ…」
淳平「我修院様、TKGW様も…(半笑い)」
我修院「ブゥ!…ウォォォオオ…」
淳平「どうされましたか?」
~~ミート・クソース・スパゲッティ ~~
(死屍累々)
まひろ「お待たせいたしました。次のメニューでございます」
男優「(脱糞音)」
淳平「おぉぉ~~…素晴らしいな、うーん…(感嘆)」
まひろ「4円(よい色)でございますね」
淳平「そうだな~うん」
淳平「さ、混ぜてやれ」
我修院「つあぁ^~~…」
淳平「おーん…素晴らしい匂いだな、今日も、な?」
まひろ「ええ、最高の出来でございます」
淳平「うおおお~~~!凄い美味しそうじゃないか!んー…」
淳平「ほらもっと混ぜてやれ、ちゃんと、ん?」
まひろ「はい」
我修院「もう(聞き取り困難)は満足だよ」
淳平「いえいえお客様、先程~、退出されようとされましたよね?(冗語法)」
我修院「いやもう、もうお腹いっぱいだ…」
淳平「それと、ン、自分から、召し上がらなかったということでペナルティとして」
淳平「え~今後、対応させていただきますので」
我修院「いやもう…もう勘弁してくれ…」
スタッフ「料理名言って…(小声)」
まひろ「お待たせいたしましたお客様。こちら当店特製ミート・クソース・スパゲティでございます」
まひろ「どうぞ心行くまでご堪能ください」
我修院「もうフォークが持てないよ…」
まひろ「フォークが持てない?」
淳平「そしたら持たして?(提案)」
まひろ「そうしたら…私共が食べさせて差し上げましょう」
まひろ「いえいえ遠慮なさらずに」
我修院「もう十分だ…」
淳平「さ、食べさしてあげましょうか」
まひろ「ハイ」
我修院「もう勘弁してくれ…」
淳平「勘弁してくれというのは、私共のメニューに、ケチをつけるということで、よろしいですかね?」
我修院「いやもう…十分堪能したよ…(満身創痍)」
淳平「いえいえまだですよ。これからですよ」
TKGW「(まひろの膝裏を触る)」
淳平「THE・もっとたっぷり付けてやれお前も(SIMPLE2000シリーズ)」
淳平「分かったな?」
まひろ「はい」
淳平「お客様にぶへぇ(無礼)が無いようにな、分かったな?」
???「おはよー」
まひろ「はい、勿論でございます」
淳平「うーん、良い色合いだなぁ」
まひろ「素晴らしい出来でございますね」
淳平「さ、お客様、口を」
我修院「イヤモウイイ、モウイイ…」
まひろ「どうぞTKGW様、口を開けてください」
淳平「我修院様、口を…開けてください、ほら」
まひろ「さぁ遠慮なさらずに」
我修院「あぁ、ブワァ…ぶわあああぁ…」
淳平「当店自慢の、ク・ソ・ス・パ・ゲ・ッ・テ・ィは?」
淳平「さぁ、もっと噛んでください、出さないでくださいお客様」
我修院「んー…」
淳平「ホラ噛んでくださいちゃんと、ほら、お客様…」
TKGW「ガハッ…ガハッ…カッ!」
まひろ「TKGW様イケませんねぇ、こんな粗相をなさっては…」
淳平「ほら食べてくださいちゃんと、ほら」
淳平「んー…ちゃんと噛んでください?」
まひろ「ちゃんと飲み込んでいただかないと」
淳平「堪能されてくださいね?この味を(冗語法)」
TKGW「unknown…」
淳平「まだまだだ、ほら…我修院さま、ほらお口をお開けください?」
まひろ「噛んで…」
我修院「モウムリダ…」
淳平「いえいえ、まだ沢山料理は残っていますので」
まひろ「さ、飲み込んでください」
淳平「うーん!素晴らしい!(驚歎)」
まひろ「いけませんよ戻しては」
淳平「これこそ食通だな!(確信)」
淳平「うーん、素晴らしい!」
まひろ「最初に説明したでしょ?お残しは許しませんって」
我修院「オエッ!ゲゲッ…」
淳平「ほら食べてください、ほら」
淳平「お客様、吐かれては、困りますので」
淳平「どうぞ吐かないでください」
淳平「これでは食通の名が泣くな!(掌返し)」
淳平「な?お前もそう思うよな?」
まひろ「全くでございます『うん』、この程度で食通などと…」
我修院「お~、おおお~~~い『もう無理』…おぉ~」
淳平「ほらほら食べてくださいロンドン…」
淳平「ほら噛んでください?お客様」
淳平「ほらちゃんと口で、ほら」
淳平「ほらこんな口から出て…ダメですよこんなのじゃ…」
まひろ「TKGW様逃げてはダメですよ?」
TKGW「ウー~↑ーン…」
淳平「ほらちゃんと噛んでくださいお客様…ほら」
まひろ「完食なさるまで、帰れませんよ?」
TKGW「グbrァ…ウ~~ン…」
淳平「ほら噛んでください?我修院様」
TKGW「ダレカコロシテクレ…(早く帰らしてくれ…)」
淳平「ほら噛んでください?ちゃんと」
TKGW「アァ…オエッ!!…」
淳平「出てますよ?我修院様…」
我修院・TKGW「ウヴゥゥエ!!」
淳平「これでは埒が明かないなぁ…どう思う?」
淳平「ん?どうしたら良い?(無能)」
我修院「オォエ!オォエ!ゲフッ!」
まひろ「仕方ありませんね、ここは私達の手で、全て、完食させてさしゃしあせてましょう!!」
淳平「そうだな、素数か…うん」
淳平「お客様、どうですか?当店自慢のスパゲッティは?」
淳平「(意味不明な動作)」
まひろ「どうですか?TKGW様(小声)」
我修院「いや~、十分堪能したよ…」
我修院「なぁTKGW君、堪能したよなぁ?」
淳平「そっか、じゃあ、まだ堪能してもらおっかな(鬼畜)」
我修院「いや~…(絶望)」
淳平「そうだよな?」
我修院「十分だよもう…」
まひろ「ええ、まだありますので」
我修院「はぁ~…」
???「4!(意味不明)」
淳平「いえいえ、お口をお開けください、我修院様」
我修院「あぁ…おうフッ、オウオ…」
まひろ「さぁ、よく噛んで味わってください?」
淳平「(聞き取り困難)、味わってくださいね?」
TKGW「カハッ!ゴッ!カハカハッ!!」
まひろ「よく噛んで味わってくださいTKGW様」
淳平「さ、じゃあ飲んでもらおっかね!ちゃんと食べてもらおうね!サッキ…」
淳平「ほら、うん、ちゃんと噛んでください?お二方」
TKGW「コカッ!」淳平「ほらほら食べてくださいロンドン…」
淳平「ほら噛んでください?お客様」
淳平「ほらちゃんと口で、ほら」
淳平「ほらこんな口から出て…ダメですよこんなのじゃ…」
まひろ「TKGW様逃げてはダメですよ?」
TKGW「ウー~↑ーン…」
淳平「ほらちゃんと噛んでくださいお客様…ほら」
まひろ「完食なさるまで、帰れませんよ?」
淳平「さ、じゃあ合図しますんでちゃんと、食べてくださいね?」
淳平「行きますよ!はい、じゃあ飲み込んでください、ちゃんと(なげやり)」
淳平「ンンー、食べ終わったらちゃんと口ン中を…はい」
我修院「ぷはあぁァ!…ほら、食べたぞ!(達成感)」
我修院「(舌を出して強調する)」
(兄弟同然だった親友が撃たれ、悲しみ叫ぶ我修院)
淳平「そうでスカ…」
まひろ「TKGW様まだ残っていますね…」
TKGW「あっ//…」
淳平「我修院様、どうですかお味は、ん?」
我修院「いやもう…も~お腹一杯だ!」
まひろ「ちゃんと飲み込みましたか?」
淳平「いや~~↓」
我修院「いやーもう食べたぞ!(力説)」
淳平「素晴らしいですね…うーん」
淳平「いやまだ、特製ソースが残っておりますね、いいのかこれ?」
まひろ「そうですね、当店自慢のソースですので…」
我修院「うわぁ…(絶望)」
まひろ「是非食べていただかないと…」
淳平「そうだな(便乗)」
淳平「さぁお二方、特製ソースが残っておりますので」
我修院「TKGW君…」
淳平「ンンッ、さ、どs、どうされましたか?我修院様...」
我修院「クソォ…」
淳平「クソですか?」
我修院「フフッwwクソッ!www」
淳平「クソですか?」
我修院「クソ!」
淳平「好きになりましたかw?」
我修院「否!」
TKGW「オゥ!カハッ!!」
我修院「TKGW君大丈夫か?(人間の鑑)」
淳平「さ、口を開けてください?我修院様」
我修院「ゴゲ!!」
淳平「まだ、特製ソースが残っておりますので」
我修院「ア゛ァ゛ッ゛!!!…ウゥゥ!…(迫真)」
淳平「ほらドンドン堪能してくださいねほら、んー」
淳平「どーですか」
まひろ「ほらどうぞ、特製ソースでございます」
淳平「ん〜どうですかこのソースは?んーおいしいでスカ?」
淳平「ほらちゃんと噛んでください?」
我修院「ウワ、ウワ、ウワ…(セルフエコー)」
(まるで泥パック並みにまひろに塗りたくられるTKGW)
淳平「当店自慢のメニューですから、堪能してくださいね?お二方」
まひろ「さぁどうぞ、当店自慢のソースの香りを、堪能してください」
淳平「ドウサレマシタカ…?」
まひろ「如何ですか?TKGW様」
TKGW「エウッ…エウッ…エウッ…エウッ…」
TKGW「ヴッ…ヴッ…ヴッ…」
我修院「ぷはぁ…あぁ食べきったぞ!!はぁ…」
淳平「そうでスカ…我修院様」
まひろ「それではこちら、お下げして」
まひろ「次はデザートをお持ちしますので、楽しみにしていてください」
我修院「もう十分だ…」
まひろ「いえいえ遠慮なさらずに…」
まひろ「当店のデザートは、一級品でございますよ」
~~クリーム・ブリュッ・レ~~
まひろ「お待たせいたしました。デザートでございます」
我修院「TKGW君やっとまともなものが出てきたぞ」
淳平「いえいえ、これからでスカら、お客様(ペコリ)」
淳平「特製プリンでございまスカら、少々お待ちください」
シリンジくん「ポンッ!!」
我修院「おぉなにすんだ、このまま食べさせてもらえないのか?(悪態)」
淳平「いえいえコレでは普通の料理と変わりませんので、特製でスカら」
淳平「分かりまスカ?ほら、お前用意しろ」
まひろ「では、少々お待ちください」
我修院「ぉ何すんだよ」
淳平「ホラ、っち向けろ」
淳平「行くぞ!」
まひろ「はい!」
(プリンくん注入)
淳平「まだ待ってるんだぞ分かったな?」
まひろ「はい!」
まひろ「(脱糞音)」
淳平「おぉ~!」
我修院「あぁ~すわわ~(嘆美)」
まひろ「(脱糞音)」
淳平「ほらもっと出るだろ、ほら逝け!」
淳平「おぉ~~!まだ出るか、ん?おぉ~!」
淳平「どうだ、まだ出るか?もうデないか…(落胆)」
まひろ「これで全部でございます」
淳平「オオ、分かった…ンン」
淳平「たーんとお前もミルクちゃんとプリンの上に掛けてやるんだぞ分かったな?」
まひろ「マカセテクダサイ」
淳平「うん…(ミルク注入)」
淳平「おう、デタカ…もういいぞお前も、うん」
スタッフ「キショ…(小声)」
淳平「我修院様、TKGW様」
まひろ「お待たせいたしましたァ...」
淳平「当店特製の…」
我修院「なんだこれは…(たまげたなあ…)」
淳平「デザートでございます」
淳平「どーぞおメシャ上がりくださ…」
まひろ「さあどうぞ」
(謎のピロピロ音)
我修院「この店はスゴイ料理を出すな本当に…(皮肉)」
淳平「いえいえ。これこそ当店自慢の、クソ・フルコースで、ございます」
我修院「スゴイよ本当に…」
まひろ「どうですか、こんな料理、他の店では食べられないでしょう?」
我修院「絶対できないよこりゃ…(確信)」
淳平「TKGW様…スプーンが止まっ…て見えるのは私だけでしょうか?(ニュータイプ)」
スタッフ「(笑いを堪える)」
TKGW「gh…」
我修院「TKGW君…」
まひろ「TKGW様どうかなされました?」
我修院「TKGW君もうここは完食しよう!(提言)」
我修院「うわぁ…」
淳平「TKGWさん、お手が進んでないようでございますね」
淳平「さ、どうぞ、お口をお開けください」
淳平「ほら、ちゃんと開けてくださいTKGWさん(格下げ)」
淳平「ほら、開けてください、ほら」
まひろ「お手伝いしてさしあげましょうか?」
我修院「あ~、う~…(OOHRMSYS)」
淳平「ほら食べてくださいちゃんと 」
我修院「いやーもう十分だ、もう充分だろ! 」
まひろ「いえいえまだ残っておりますので 」
我修院「もう十分だろ!(抗議)」
まひろ「口を開けてください」
TKGW「(DNLDの鳴き真似)」
淳平「ほらお前も食べないなら食べさせてやれ 」
淳平「ダメだ、お前そんなやり方じゃ、貸してみろ 」
淳平「そんなの、甘ったるいぞお前 」
淳平「ほらイきますよ我修院様」
淳平「TKGW様もちゃんと食べられたんで、食べてくださいよ(同調圧力) 」
淳平「うーん、どうでスカ、お味は…(顔面に塗りたくる)」
淳平「さ、片付けてやれ 」
まひろ「はい、じゃあこちらお下げします 」
我修院「もう十分だ 」
我修院「TKGW君大丈夫か? 」
淳平「これが〆ではございませんので」
我修院「いやもう全部食べただろフルコース…」
まひろ「幾つか当店の約束事を破ろうとしていましたね(牽強付会)」
まひろ「このまま帰す訳にはいきませんね」
まひろ「ペナルティを受けていただきます」
我修院「もう誰にも言わないから勘弁してくれ…」
まひろ「いえいえそういう訳にはございません。決まりですので(無慈悲)」
~~Penalty:糞遊び編~~
(KBTITの仕事場で待機する二人、なぜかクリームブリュ・レまでの汚れは落ちている)
(じゅんぺい、まひろ登場)
淳平「それではさっきのペナルティに行くか」
まひろ「はい」:
淳平「うん」
まひろ「じゃぁ早速いきましょうか」
淳平「おう:じゃあ向かい合わそうか」
我修院「****何すんだよ・・・」
淳平「まあそれは後で***分かるよ」
淳平「我修院さん」:
我修院「何すんだよ」:
淳平「我修院さんほら」
我修院「あぁ...」
淳平「残してくれたか?」
まひろ「いつでもどうぞ」
淳平「おい、行くぞ!」
まひろ「はい!」
淳平「はい」
(じゅんぺいは我修院に、まひろはTKGWに糞をひり出す)
フッ...ウッ,,,ア゙ァ!...ヴァ...ウゥゥン...ブ...ウゥゥ...オェェ...ゲフッ...アッ,ウゥゥ..,エッブッ!グッエフッ...ウゥ...アッ,エウッ...ブフゥ...エッ,ゲフッ...ブッ,,,ブッ,エッ
淳平「おいおいお~い我修院さんどうしましたぁ?(煽り)」ンー
淳平「TKGWさんも~」
ウエエエエ!
エウッ...バッバウエエエ!ゲフッ,アエッ!
我修院「あー・・・」
(早速糞を塗りたくられる二人)
まひろ「先程のミルクが、まだ残っていたようですね」
淳平「ほら、入れてくださいよ、口の中に」ドゥゥ!
淳平「ほらぁ (パセッ) ほら入れ(あー)てくださいよん~?」プア-...
淳平「ほら口開けてください?ペナルティですよ?」プァッ!アァ...
淳平「ほらお前も自分の、ちゃんと塗りたくってやれ」 ヘッ
ゲホッ:ゲッ
淳平「ん~ あぁあ~、凄いな(他人事)」
ンー...
我修院?「やだ...」
淳平「まだう○こが足んないな!」
ファッ!? ンー! ンンーッ!↑ ンー! ンンッ
まひろ「TKGW様口を開けてください」
淳平「ほら、まだあるぞ?」
我修院「おい...」
まひろ「ほらTKGW様口を開けて?」
淳平「ほらほら、ありますよ?ほらいっぱい」
プヘー,プヘー...
淳平「ほら、う~~う!」
TKGW「プホッ!(気道確保)アーダメモウダメ...」
淳平「ほらう~」
TKGW「ウー!(シンクロ)ウー!」
我修院「ああ、ああ、ああ、ああ、アーモウヤメテクレ.....」
パン!(この辺り、四人ではない謎の声が聞こえるが解読不能)
淳平「ほら、いや~」
淳平「我修院さんなんか嬉しそうじゃないですかさっきから!どうしたんですか?嬉しいんですか?嬉しいんですか?我修院さん!」
我修院「ウレシクナ...ウアーヤメテケロ...」
淳平「え?何が?ん?ほらチ○コに付けてやれ!ほら、TKGWさんも」
我修院「ヤメテ,アア」
まひろ「はい!」
淳平「んー、ほらきったね!(本音)きっ、ああ~凄いな!(他人事)」
淳平「んー?くっせえくっせ! ああくせ!」
まひろ「どうですかTKGW様、う○こまみれにされた気分は?」
TKGW「モウヤダ...モウヤ...」
(場面転換)
(糞を腹に塗った二人に舐めさせられる)
淳平「ほら、ちゃんと舐めてくれ、ほら、ほら、起きな?」
ウエエッ,アー,ポフッ!
淳平「ほら、我修院さんほら、舐めてくださいよほら、ペナルティですよほら、ほら綺麗にしてくださいよ!」
淳平「ほらお前も自分の体に塗りたくってみろ」
まひろ「はい」
淳平「ほら舐めてくださいよ」
淳平「ほらもっと舐めてください?」
まひろ「さぁ、綺麗に舐めとるんですよ、TKGW様」
アアアア...
我修院「モーモウジュウブンダ...」
淳平「いえいえいえまだまだですよ!ちゃんと舐めてください?」
まひろ「いけませんね、先程申しましたようにこれはペナルティなのですよ(にぱー)」
まひろ「ちゃんと舐め取って頂かなくては困りますね」
我修院「アーモウジブンデヤルゥ...」
淳平「これがどういう事なのか、分かってますよね?」
我修院「ワエッ!!?」
淳平「(指で我修院の口をピストン)」
淳平「誰がえずいていいかって言いました?」
淳平「ほら、ちゃんと舐めてください、ほら」
淳平「ほら舐めてくださいほら」
我修院「ワカッタ...(屈服)」
(この間後ろでうーうー)
淳平「ほらまだまだですよほら」オォ...オォ...
淳平「我修院さんはそれでいいんですか?」
我修院「ヤメロ...」
まひろ「ほら、もっとちゃんと舌を使うんですよ。綺麗に舐め取って頂かなくては」
我修院「うぅわ!」
まひろ「ちゃんと舌を使って...」
(場面転換)
(糞を塗られ食わされながらオ○ニー)
淳平「ほら、ほらう○こだぞ、ほら舐めろほら、ほら」
淳平「ほらぁ、どうだぁ?」
淳平「お~い、んん?くせえなあ、んん?」
淳平「これが珍味なんだよ!分かるか?好きな奴は食っちゃうんだよ!」
淳平「分かったか?おい」
淳平「ちゃんと見してみろ!自分でしごくの、ほら、ほら見してみろ、恥ずかしい姿を見してくれ!」
淳平「ん?ほら」(ここからTKGW、ウーウー言い始める)
淳平「しょうがねえなあ~こいつら!」
淳平「ほら、来いよ!舐めてやれよ!ほら、ほら舐めてやれよ!」
(我修院、TKGWの体を舐める)
TKGW「ウウウウウウー!↑ウウウー」
淳平「誰が休んでいいって言った?我修院さん、ん?」
TKGW「ウウウウウウウウウウウウウウー!ウウウウ-!」
淳平「TKGWさんのほうが頑張ってるんじゃないですかねぇ?」
淳平「我修院さんまだ帰れそうにありませんねえ!ん?」
(場面転換)
(今度はフ○ラ)
淳平「ほら、何なんだほらちゃんと舐めてくださいよ我修院さん、ん?」
淳平「ほら、TKGWさんほら、ほら口開けて?ほら」
TKGW「ンア゙ー,ガッ!シュッシュ!」
淳平「ほら、我修院さんもほら口開けてくださいよ、ほら」
淳平「ほら」
TKGW「バオー!(幻獣)」
淳平「ほら」
TKGW「モウヤァ...」
まひろ「TKGW様手が止まってますよ?」
TKGW「マズィ...」
淳平「ほらぁ、もっとしゃぶってくださいよTKGWさんも」
TKGW「パッポッムリ...」
淳平「ほらぁ、何が無理なんですかほら」
TKGW「モウムリ...タエラレナイ...モウムリ」
淳平「ほらぁ、もっとやってくださいよ我修院さんもほら」
TKGW「パッ,ヴエエエエ...プン!」
淳平「ほらTKGWさんも口開けてくださいほら!ほら口開けてくださいほら」
TKGW「ワアッ,アッ.アアアア゙ア゙ア゙!!↑」
淳平「ほら、お前も閉じてろ!」
(糞を口に入れられるのを抵抗していたTKGWだが、口を塞がれる)
まひろ「出しちゃダメ、吐いたらダメですよTKGW様。飲み込んでください」
TKGW「ンッンッンッ,ンッー!ンッー!ンッーンッ↓」
淳平「ほら我修院さん?ほら我修院さんほら」
(場面転換)
淳平「ほら、吐いちゃダメですよほら、噛んでくださいちゃんと。ほら」
TKGW「ンーッ,ンッンッンッ」
淳平「ほら、どうしたんですか?我修院さんほら」
淳平「ほら、ほらちゃんと食べてくださいほらこんな所に残ってるじゃないですかいっぱーいう○こがーほらー」
(場面転換)
淳平「ほら、噛んでくださいよちゃんと」
TKGW「ヤダ!(最後の抵抗)」
淳平「ん?何ですか?」
淳平「ほら口開けてくださいほら・・・ほら口開けてくださいほら!」
TKGW「ンンッ!ポーワァ!(トリトドン)アアァァアアアア゙ア゙ア゙ア゙!ポァ!」
淳平「ほらダメですよほら、口開けてくださいほら。ちゃんと開けてください」
まひろ「TKGW様?」
淳平「ほら、お腹****、ほら(直後のTKGW様と被り解読不能)」
TKGW「グッ!!!(起動)(足バタ→足ピン→痙攣)」
淳平「ほら」
まひろ「ダメですよ?(無慈悲)」
淳平「ほら我修院さんもほら」
TKGW「ンンッ… マ゜ッ!ア゛ッ!↑」
淳平「ほら・・・ほら」
TKGW「プッ!」
淳平「ほら・・・ほら、その、う○この・・・(引き気味)う○こ食った口でキスしてくださいよほら」
TKGW「アッ?アッ...アッ,アアァァモヤアアアァァ...」
まひろ「口を開けてください?」
淳平「ほら、それでキスしてくださいよちゃんと、ほら」
TKGW「ア゙オ゙オ゙オ゙オ゙オ゙オ゙オ゙ン゙!!!(人狼化)オンッ!」
淳平「ん?なんですかなんですか~?(睦月)」
TKGW「ンンン゙ン゙ン゙ン゙ン゙ー!もうやだぁ・・・やだもーやだ・・・無理ぃ・・・むりもーむり・・・(MRKBNN)」
淳平「ほら、我修院さんほら舐めてくださいよ」
TKGW「アハーン!ウェエエエエエン!ウワァァ!ウワァァ!ウワァァ!ウワァ!ウワァ!ウワァ!アアッ↑」
~~Penalty:ガン掘り編~~
(なぜか絡み合う二人、じゅんぺいとまひろは退場している)
(塗られた糞はすでに乾燥している、まるで泥みたいだぁ・・・(直喩))
(じゅんぺい、全裸で登場)
淳平「おう何二人でやってんだよ、ん?んん、何してんだオラ、オラ(最早店員の態度を忘れている)」
淳平「ん?何してんだ?いっ****、何してるか言ってみろ。ほら、ん?」
我修院「チ○チ○しゃぶってます・・・」
淳平「ほら、ほらしゃぶれよ(二章)」
(TKGW、じゅんぺいのチ○チ○をしゃぶる)
TKGW「ンー、ンー、ンンーー、ンー」
淳平「何してたんだ?二人で、ん?言ってみろ」
TKGW「ンーッ、ンンーッフ」
我修院「フ○ラ○オ・・・フ○ラ○オしてました・・・」
淳平「ほら、どうだ」
TKGW「ンッ、ンッ、ンンーンンンッ」
(しばらくンーしか言わないTKGW)
淳平「オラ」ヴエエエエエ!オオウッ
淳平「二人で舐めてくれ、ほら」アッ,アッ,アアーッ
淳平「TKGWさんどうしたんですか?自分でケツいじってるんですか?TKGWさん」
アーイッパイ...(?)
淳平「どうしたんですか?チ○コ欲しいですか?TKGWさぁん」
TKGW「チ○チ○...」
淳平「なんですか?」
TKGW「チ○チ○...(分かりやすく)」
淳平「えぇ?何言ってんですか?ちゃんと言ってください?」
淳平「なんで一人で、ケツに突っ込んでるんですか?手」
TKGW「チ○チ○ホスィ...」
(後ろに人物が確認できる、服装からしてまひろか?)
淳平「じゃほらこっちに、ケツ見してください?」
(じゅんぺい、TKGWのケツにぶち込む?)
TKGW「アッ、アッ、アッー!アッー、アッー、アッー、アッー、アンッ、アンッ、アンッ、アン(世界レベル)」
TKGW「アッ、ンッ、ンッ、ンーッ、ンンンンンーーーーーッ!」
我修院「ああ・・・ああ・・・」
(TKGWを舐める我修院)
TKGW「ウワアアッー!アッー、アッー!」
TKGW「アッアッアッアッアッアッアッアッアッアッアッーアッーキモチィ、アアアアアアッッーー!!」
淳平「どうだ?俺のチ○ポは?あれが欲しかったんだろ?ほら」
TKGW「キモチイ…アアッッーー!アアッッーー!」
我修院「ああ・・・ああ・・・」
淳平「ほら、突いてやるよもっと」
TKGW「ウワアッ、アッー、アッー、アッー、アッー、」
(股近くのアップ、その後TKGWの顔へとズーム)
(シコシコシコシコシコシコシコシコ...)
TKGW「ん/、んん///?」
我修院「TKGWくんだけずるいです・・・ああ・・・(嫉妬)」
淳平「ほら、じゃ待ってろよ、ほら」
TKGW「アアッー、アッー」
我修院「キモチイヤキモチイ...」
淳平「ほら、もうちょいこっち寄れよ、ほら、ほら」
(じゅんぺい、今度は我修院のケツにぶち込む)
我修院「アアアアアア・・・」
TKGW「アッー、アアッー」
淳平「ほらぁ、ほらなんで逃げるんすかもうちょいこっち来てくださいよ、ほら」
我修院「アッ、アアッ、アッ、アッ、アッ、アッ、」
淳平「ほらっ!」
我修院「アッ、アッ、アッ、アッ、アッ、アアッ、」
淳平「ああっ・・・ああっ・・・」
(しばらくアッ、としか声を出さない三人)
(ケツのアップ、ぶら下がっているモノが絶望的に汚い)
TKGW「ケツ感じる?」
淳平「アッ、アッ、アッ、アッ、アッ、アッ」
我修院「***(じゅんぺいの声に紛れて解読不能)」
TKGW「乳首は?」
我修院「シュゴイ...」
TKGW「乳首は?」
我修院「何・・・?」
TKGW「乳首感じる?」
我修院「ああ~すごい・・・」
我修院「アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓、アァァ↓」
(再びアアッ、しか言わない三人)
(TKGWと我修院のクッソーkiss)
TKGW「オォゥ↑!オォゥ↑!(アシカ)」
(その後下半身へとズーム)
TKGW「オチ○チ○...」
TKGW「ンンッ、ワッ」
淳平「じゃあ俺のも舐めてくれよ。ほら。ん?ほら」ペチン
TKGW「前、前向いて」
淳平「ほら、舐めてくれよちゃんと、ほら」
淳平「ほら、ん?」
淳平「何感じてんだよオゥラ」
淳平「ほら、ほら舌使ってよ。もっと」
淳平「お前もなぁ、フ○ラ下手だもんなぁ!」
淳平「ほら、二人で舐めてくれ、ほら。ほら」
(淳平に蹴られ転がっていくローションくん)
(じゅんぺいのチ○コをシェアする二人)
淳平「ほら」
淳平「ほらほら、これじゃイカねえぞ、ほらぁ」
TKGW「ンーッ、モウヤァ」
淳平「勃たしてくれほら」
(じゅんぺい射○)
淳平「あーやばいイキそ、あーっ、あーやばいイクッ」
淳平「イクッ!(自分でシゴいた後射○、TKGWの顔にかかっている)」
淳平「イクッ!(射○リプレイ)」
淳平「ああ、ああ、ああ、ああ・・・(余韻)」
(じゅんぺいの顔のアップ、ゲスい)
淳平「何お前ら二人でシゴいてんだよ(賢者タイム)」
淳平「じゃあ二人でやっとけ!ほら」
我修院「はい・・・」
(じゅんぺい退場)
(二人で色んな絡み方をするも、最後には各自オ○ニーに耽る)
(横たわる二人)
我修院「あーいく・・・あー・・・」
我修院「アイクッ!(射○)」
我修院「アイクッ!(射○リプレイ)」
我修院「ああ・・・ああ・・・ああ・・・(余韻)」
TKGW「イクッ!!(大声射○)」
TKGW「イクッ!!(射○リプレイ)」
(そのまま我修院、TKGWの体を映して終了)
淳平「当レストランはいかがだったでしょうか?本日お客さんに提供さしていただき、たお料理は、ほんの一部でございます。
ンッ、その他にも沢山のお料理を用意しておりますので、(ここで不自然なカットが入る)お客様の御来店をスタッフ一同
心より、お待ちしております!(スタッフに合図され頭を下げる)」
ブッチッチッチ…ブッチッチッチ…
ひで「あ~今日も学校楽しかったな~。早く帰って宿題しなきゃ(使命感)」
(道路を渡った後、隠れていた虐待おじさんに膝蹴り→パンチをされる)
ひで「イッテェ…」
(ダウンするひで、そのままおじさん宅へ)
チャカポコチャカポコ…
(虐待おじさんがひでを運搬する)
虐おじ「オラァ…ハァ…ハァ…」
(クッソ汚い涅槃顔のアップ)
ひで「(ベッドの上で目を覚まして)あれぇ?」
虐おじ「君、名前なんて言うんだ?」
ひで「ぼくひで(黙秘で、朴 秀)」
虐おじ「ひでか。喉乾いただろう、こっち来て、飲み物でも飲みなさい」
(リビングへ移動)
~~前戯編~~ (ひでの喚声が度々重複するので便宜上一部省略)
(ネクタイを外しながら徐々にひでに近づく虐待おじさん)
キィー
ひで「ン!イャンクック!ゲホッゲホッ!」
虐おじ「おじさんはねぇ、スーハースー君みたいな可愛いねぇ、スー子の悶絶する顔が大好きなんだよ!」
虐おじ「ヘヘッ、おっぶぅ~!」
虐おじ「えぇ?どうなんだよオラ、良い顔してるよオイ、ゥオオッー!」
ひで「おじさんやめちくり~(挑発)」
虐おじ「えぇ!?えぇ…ぅおお、え?(セリフ忘れ)」
虐おじ「神々しいわよねオルァ、オォ!」
虐おじ「こんなんでやめる訳ねぇだろおいオラ、こっち来いやオイ!」
ひで「あぁ……」
虐おじ「オォ↑ッ!?」
(ベッドへ移動)
虐おじ「ほら、おじさんの言うこと聞いてくれるかい?死んじゃうよオラオラ」
ひで「裕子と菊代(言う事聞くよ)…!」
(ここでチャカポコのBGM終了)
虐おじ「聞く?ウルキオラ?」
ひで「……ライダー助けて!!」
虐おじ「ブルァァ!ざけんじゃねーよオォイ!!誰が大声出していいっつったオイオルルァ!!え!?」
虐おじ「本気で怒らしちゃったねぇ、俺のことね?」
虐おじ「おじさんのこと本気で怒らしちゃったね!」
ひで「あぁぁぁぁ…」
虐おじ「え?どうなんだよホラ。ホラ、え?(親指でひでの鼻の穴を上に向ける)」
虐おじ「興奮さしてくれるねぇ?好きだよそういう顔」
虐おじ「ん、ンンゥゥゥ!(不幸せなキス)」
ひで「あはんやめてぇェェェ!!!」
虐おじ「やめてじゃないんだよ…(怒りの震え声)」
虐おじ「言うこと聞くって言ったよなさっき?なあ?言うこと聞くって言ったよな!(クッソ汚い不幸せなキス)」
ひで「アァァ!!やめてヤダ!」
虐おじ「言うこと聞くっつったよなさっき?」
ひで「うああ!やめてや…やだぁ!や~!」
虐おじ「ン///…チュウ チュパ…」
ひで「あ゛~!×N」
ひで「や゛め゛て゛!×N」
虐おじ「ォイ!(ひでにビンタ)」
虐おじ「お?どうだ?」
虐おじ「オイ!オイ!…オラァ!!(AI二回行動)」
虐おじ「おい!」
ひで「痛って、やめ……」
虐おじ「聞かねえのかオイオラァ!」
虐おじ「オラォラァ!!エェ↑!オルァ!!オォ↑!?」
虐おじ「言うこと聞けねぇみてェだな、おじさんの言うこと聞けねぇみてェだなぁおい!」
ひで「ヤメテー」
虐おじ「こっち来いよ、おうオラァ」
ドドンバン!(床上に落とされるひで)
虐おじ「えぇ?(弱)」
ひで「止めて!」
虐おじ「バンザイしてみろバンザイ。ウォォ、オイ(体操服を吹っ飛ばす)」
虐おじ「エボラ…、ほら」
ひで「ァハ、…ァハ…」
~~竹刀編~~
虐おじ「ほら四つん這いになれやおい、なれやおいオラァ」
バン!!(一拍)バンバンバンバン!!(一拍)カッ!!
虐おじ「(言うこと)聞くって言ったよな?」
ひで「ハイ…」
虐おじ「YO…YO…(立弱K)」
(ひでが蹴り返す)
ひで「アァ痛ッたい!ッタァーイ…」
虐おじ「オラ」
虐おじ「どうなんだよお前YO、言うこと聞くっつったよなぁ俺に向かってなぁ?」
虐おじ「お前言うこと聞くっつったよなぁ?」
ひで「ハイ…」
虐おじ「とりあえずお前こっち向いてみろよ。向いてみろっつってんだよ、ホラ。チクチクチアケロクチ、ホラ」
ベシベシベシベシベシベシベシベシベシベシベシベシベシ!
ひで「ウァァ…ア(フェードアウト)」
虐おじ「ホラ立ってみろよ」
ひで「ハァー(クソデカため息)」
虐おじ「立ってみろよ。ほら」
ひで「アァ…」
虐おじ「気を付けしてろ。立ってろよ…。ちゃんと立てよ?気を付けしてみろ」
(嫌々従うひで)
虐おじ「聞けよオラァ!」
ひで「(最敬礼)」
虐おじ「おい!…YO!」
ひで「イ゛タ゛イ゛イ゛タ゛イ゛…グスン…」
虐おじ「言うこと聞くっつったよなおい!ほら立てよ、ほら立てよオイ、なぁ?」
ひで「逢いたい…(届かぬ想い)」
虐おじ「ほら立てっつってんだよオラァ」
虐おじ「お前ここでアレ、ホラ、ケツ出してみろオラ、突き出してみろそんでよぉ」
虐おじ「お仕置きである。(K-TNYMD)」
虐おじ「聞くって言ったのに聞かねぇだろお前なぁ、Vodafone?」
ひで「Ammo…」
虐おじ「なぁ、聞くっつったのに聞かねぇよなぁ!?」
虐おじ「どういうことなんだよこれ?なぁ」
虐おじ「最初から聞かねぇってんなら分かるけどよ、なぁ」
ひで「あー痛い」
虐おじ「聞くって言ったのに聞かねぇってお前おかしいだろそれよォ!コラァ!?」
ひで「イッタイ!!」
虐おじ「違うかぁオイ?コラ」
ひで「嫌、やだ…もぉ…」
(ひで竹刀を奪おうとする)
虐おじ「ホラ…五回…沙蚕…(力負けおじさん)」
ひで「あ~もうヤダ…ネモーゥ痛…」
虐おじ「あー?ホラどうしたんだよ…聞かねぇのか?」
虐おじ「五回」
ひで「ねー嫌…」
虐おじ「ウィッシューー!…」
ひで「イ゛ったい!アーォ…」
虐おじ「kち来いよ…ホr…」
ひで「イッタi…あ゛ーはぁ゛ーんモ゛ー…」
虐おじ「え?」
ひで「イッッったい!!」
虐おじ「痛いじゃねぇよお前!」
(全裸にされるひで)
虐おじ「 ア ア゛イ ッ ! ! 」
虐おじ「ほら…ほら…」
ひで「あ~もう…痛い…」
虐おじ「立てよ。ケツ向けろよオイオラァ、こっちケツ向けろよ。え?」
虐おじ「向けろっつってんだルルォおい!」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛もうイッタい!」
(ひで竹刀から逃げる)
虐おじ「ほらどうしたんだ?え?」
ひで「い・た・い・の・に…この人おかしい」
虐おじ「オォイ!」
ひで「あぁ…」
虐おじ「オォイ!」(音声編集)
ひで「あぁ…」(音声編集)
ひで「あ゛ぁーもう…」
虐おじ「え?オラァ」
ひで「DESIRE!!!(NKMRAKN)」
虐おじ「ケツ出さねぇから痛ェんだろうがオイ!!」
虐おじ「なぁ?ケツ出してみろほら」
ひで「ねーもうイ↑ッ↓タ→イ↑!」
虐おじ「あと四カット三回。二回しか終わってない(メタ発言)」
ひで「ね~痛いもう…」
虐おじ「二回しか終わってない」
ひで「コカインだよぉも~~~…」
虐おじ「腕、腕出すと痛いよ?骨当たると痛いよ?」
ひで「ねぇ痛、フザケン…」
虐おじ「イチ!ニ!」
ひで「ワァーイッタい!うわ!アッー!」
虐おじ「ほら骨出すと痛いよ?」
ひで「ネーモ…」
虐おじ「肘アタック(当たると)痛いよもっと!ホラ」
ひで「あ゛~~↓痛い」
虐おじ「悪い子はお仕置きだど~(SGC-)」
ひで「あーもうイタインダヨォー…」
虐おじ「えぇ!?」
ひで「イャ、イー!」
虐おじ「ホラァ」
(ダウン連おじさん)
ひで「痛いー!もう痛いよ!ねぇヤ↑ダ!イ゛タ゛ァ゛イ゛も゛ぉ゛!!!」
力負けおじさん)
虐おじ「取れよホラ、は?おい!ホラ、どしたんだよおいオラ、え?オラ」
(玉音放送を拝聴するひで)
~~水責め編~~
虐おじ「顔上げてみろよ。上げろっつってんだろ」
虐おじ「泣けば許されると思ってんのか?」
虐おじ「お前、おじさんに嘘ついたんだぞ?なぁ。なぁオイ」
虐おじ「ホラ、仰向けになってみろ、な?」
虐おじ「今度は優しくヤってやるから」
虐おじ「優しく、可愛がってやるよ…な?」
(泣き笑うひで)
(水分補給)
ひで「ゲフゲフッ!ッカッ!ゲホゲホ!やだ…」
ひで「ナ゛ッ゛!止めて!」
(滴定おじさん)
ひで「ゲホゲホ!」
虐おじ「おい、かかっただろ顔に!なぁ?」
虐おじ「まぁいいや…さっきのぉ(水分補給)とぉ…ン…(滴定)これ、どっちが美味い?」
ひで「…」
虐おじ「どっちが美味い」
ひで「ゲフッ…」
虐おじ「訊いてんだよ…」
虐おじ「訊いてんだよ小僧!」
(毒霧)
ひで「グワ゛ー゛!!」
虐おじ「訊いてんだよ!なぁ!オラ」
(毒霧)
虐おじ「どうなんだよ、なぁ?YO」
虐おじ「ローランだ?おい」
虐おじ「ローランだよ?どっちが美味いのか?」
虐おじ「WA、忘れたか?どっちが美味いって訊いてんだよオラァ、おい!」
ひで「やめ…」
虐おじ「コラァ!」
ひで「やーだー」
虐おじ「何が嫌なんだよ…、何が嫌なんだよ、え?おい」
(ビンタ失敗、転がるボトルキャップくん)
虐おじ「何が嫌なんだよほら?」
ひで「うー…やだ止めて」
虐おじ「何が嫌なの?何を止めればいい?何が嫌なの?」
ひで「やだもぉ痛いの…」
虐おじ「痛いの止める?そっか、分かったじゃあ痛いの止めてやるよ、チッ、な?」
虐おじ「ホラ口開けてみろよ、ン、痛いの止めるからよ」
虐おじ「hお前、美味しいの…飲ませてやるからな」
ひで「やだぁ」
(原爆投下)
虐おじ「どうだ?どうなんだよ(素足でひでの顔を踏む)」
虐おじ「オメェよぉ、靴下汚れっからな~、ほら(両足でひでの顔を踏む)」
ひで「わぁ~はぁ~ヤダ~~ヤダ止めてもぉ!!」
虐おじ「どうでちゅか~?(豹変)」
ひで「あ^~~もう止めて~」
虐おじ「ん?止めてじゃないよ、ホラ」
(毒霧)
ひで「ウガ!もういや…」
虐おじ「m…、m…、顔向けてみぃやオイオラァ、な?YO…コラ…起き上がってみろ、NA?」
虐おじ「いい面になったなぁ?ほら」
(不幸せなキス)
ひで「ン゛ン゛ン゛ン゛ン゛~~!(ドンドンドン)」
虐おじ「いい面しやがってオラァ…///」
(不幸せなキス)
ひで「ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…スゥ…ハァ…ハァ…」
~~鞭編~~
(ペットボトルを蹴倒す)
虐おじ「次これ。これ…これね?」
虐おじ「OK?」
ひで「ヤダ…」
虐おじ「OK牧場?(激寒)」
ひで「ヤダ」
虐おじ「おお~いッッ!!!!」
ひで「アッーー!!いってぇ…(素)」
(フェードアウト)
ひで「あー痛ったい痛い痛゛い゛!!!!!!」
ひで「ネイッタイ、チョットモウイッタイナモウ…」
虐おじ「ほら」
ひで「ね~もう痛ッいよも゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛!!!」
虐おじ「そっち行くんだったらやる、やろうやろうやろうなこれ!(高速ウェポンチェンジ)これな!やるねコレ!!」
ひで「イッ!!!(マジギレ)」
虐おじ「じゃあこっち来いよ(フェードアウト)」
ひで「ね~痛゛い゛痛゛い゛痛゛い゛!痛い…(カメラのある方向へ逃げるひで)」
虐おじ「ほら、そっち、そっち行ったらやる、やるぞお前?」
ひで「ネーモウ…」
虐おじ「やるぞそっち行ったら?」
虐おじ「じゃあこれ(竹刀を出す)」
ひで「モーヤダーモー…」
ひで「ウァッーいったい!!」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛ あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!」
虐おじ「真ん中来いよ!」
ひで「もうイッタイ!」
虐おじ「え!?真ん中来いよおi(フェードアウト)」
虐おじ「ウェーイ!!ウェーイ!!」
ひで「あー痛゛い゛!!あ゛あ゛ーちょっ…あ゛あ゛あ゛あ゛ あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!」(音声編集)
ひで「ああ痛゛ッ゛た゛い゛もう!!…ッハ…」
ひで「ねーもーイタインダヨォモォ…」
虐おじ「掴むな…汚れるんだよスーツが(倒置法)」
ひで「ねぇ…あーもう痛い…」
虐おじ「え?ホラ」
ひで「イタイ…イタイ…」
虐おじ「バカにしてんじゃないぞ?」
虐おじ「はい一!二!三!四!五!六!七!七離せよオーイ!!」
ひで「ライモーン…」
虐おじ「オーイオラァ!」
ひで「痛いんだよ!モ、ね~もうやだもー!」
虐おじ「そういうことやるから終わらない!(メタ発言)」
ひで「ねイタいーもう!!!イッタいよもう!」
ひで「ね理解った理解った理解ったよもう!!!」
虐おじ「こっち来いよ…こっち来いよ…」(音声編集)
ひで「ねーホモ…ねーホモ…」(音声編集)
ひで「痛いんだよおおおおおおおおおおおお!!!!も゛お゛お゛お゛お゛お゛!!!(マジギレ)」
虐おじ「鞭痛いのは分かってんだよおいオラァ!!!!」
虐おじ「YO!!!!」
(怯むひで)
ひで「痛い↑痛い→痛い↓」
虐おじ「1,2…」
虐おじ「掴んだら×2(かけるに)な!掴んだら×2!」
ひで「ヤハァ!やーだ!」
ひで「イタイイタイィー…愛でたい…(震え声)」
虐おじ「イチts~…、ニ~…」
ひで「あ^^~~!あーイタいイタい、イイタイ!」
虐おじ「サン!」
ひで「イィィィィ…」
虐おじ「ヨン!」
ひで「イッタい!!」
虐おじ「GO!」
ひで「あー!」
虐おじ「こっち来いよ!!」
ひで「痛ったいっスよもお~…イッタイ…(ドタバタドタバタ)」
虐おじ「真ん中来いy…(フェードアウト)」
ひで「いDIEDIEDIEDIEDIE!!!!!」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛痛゛い゛↑!あー!エハ!」
ひで「出会いたい!!(出会い厨)」
ひで「アァ…アーボ…」
ひで「あ゛あ゛あ゛!レモン止めてぇ(アンチYNZKNS)ねーもうホント痛い!」
~~蝋燭編~~
(布団に包まって咽び泣く(嘘泣き)ひで)
ひで「ね、やーだ…」
(布団を剝がす)
虐おじ「ほら。顔向けろ」
ひで「ヤダ…」
虐おじ「顔向けろよホラ」
ひで「ヤダ!」
虐おじ「嫌なのか?言うこと聞かないんだな?(鞭をちらつかせるおじさん)」
ひで「ねー分かったそれヤダ!分かった…」
虐おじ「言うこと聞かないんだな?」
ひで「ワカッタワカッタ…」
虐おじ「これ…」
ひで「ヤダ…」
虐おじ「じゃあ…ホラ、布団(を剝がす)」
虐おじ「座れ?」
虐おじ『──────枕に生を、背もたれに死を』(宝具詠唱)
虐おじ「座れ」
虐おじ「もっとほら、乳首見せろ、な?乳首見してみろほら」
虐おじ「ほら、これ」
ひで「ヤダ…」
虐おじ「さっきの(鞭)よりマシだろ?な?ホラ」
ひで「ン…ィタイィタイ…」
キュ…(乳首クリップ装着)
虐おじ「あ^~」
ひで「イテテ」
ひで「アー…リr…ぬh…」
虐おじ「もう一個…ね、もう一個。ここ着けるから」
虐おじ「これ、鰻重」
(二の腕で体を防御するひで)
虐おじ「ほら(腕をどけるしぐさ)」
ひで「ヤダ…」
(鞭を出され、ひで露骨に嫌がる)
ひで「ワカッt…」
虐おじ「どっちがいい?」
虐おじ「じゃあ辛抱しろよ~ちょっと…オラ」
ひで「うぅ…あ^~…」
虐おじ「似合ってるな、な?お似合いだな」
虐おじ「なんだよその反抗的な目は?なぁ…」
ひで「やだy…」
虐おじ「反抗的な目はなんだ?」
虐おじ「言うこと聞く気がないのか?」
ひで「キクユウコトキクカラヤダ…(矛盾)」
虐おじ「じゃあそこ来いよほら。ここに、こっち来てみろ、じゃあ。な?」
虐おじ「今聞くって言ったよな?今。聞く、って言ったよな?」
虐おじ「よし…そこ、ここ(床)に寝てみろ」
ひで「アアイ…」
虐おじ「仰向けになって…」
ひで「モウイタィ…」
虐おじ「ほら(鞭を見せる)早く寝ろよ!」
ひで「イヌァイ…」
(蠟燭を準備)
虐おじ「これ何か分かる?何だか分かる、これ?何だか分かるこれ?」
虐おじ「蝋燭」
(着火)
ひで「ねー嫌、ヤ、ヤダ!ん…」
(バタバタ)
虐おじ「ちょっ…(小声)」
ひで「アァっ…、アア!(バタバタ)」
ひで「ヌア!アツゥイ!!!」
ひで「アー…アツゥイ…、あー…あー…ねえアツいヤダ!」
虐おじ「ロウが少し垂れただけだロウ(激寒)」
ひで「エア!アツゥイ!!!ア゛ア゛ツイアツい!あ^~!」
ひで「アツイ!アッツイアッィアッィ!ア↑ーツイ!ア↑ーツイ!あ^~!アッツイアツイ…」
ひで「t…ィーアッツイ…ベン・ハーが熱いよぉ…」
ひで「アツイアツイ!ねーちょっアッツいねんそれ!(関西弁)アーツイ!」
ひで「あっついねぇー!あああついYOー!!アツツ…あ^~」
虐おじ「ほら、顔にかかるぞ?なあ」
ひで「あ^~~!アッツイ!アツイ!ちょ…アツゥイ!アツイ…」
(蝋燭増量)
ひで「ねーやだアツイィ~!」
ひで「アツイ!…あ~!あ~!ア゛!ツ゛!ヒ゛!あああ!!!」
ひで「っワ…ウーウー…」
ひで「熱いユ~!!!(適温)」
ひで「あ~!…ア゛!ツ゛!イ゛!アツイ!!あ↑あ→あ↓ハァハァ…アッツァツァ…アッツ…」
(鞭を出す)
ひで「ヤダヤダ…あ゛ーー!!(ドタバタ)」
虐おじ「動いたら叩くぞ」
ひで「ヤダ…ウーウー…あ゛あ゛あ゛あ゛つ゛い゛い゛い゛!」
虐おじ「動いたら叩くぞ!」
ひで「ひゃだぁぁ~~…う~、あああ~、アツゥイ…」
(うつぶせにされるひで)
ひで「アッハァあ゛つ゛↑い゛い゛い゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛(ビブラート)」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛つ゛い゛、あ゛あ゛あ゛あ゛も゛う゛や゛だ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛」
ひで「あ゛あ゛つ゛い゛い゛い゛い゛い゛(ドタドタドタドタ…)」
ひで「あ゛あ゛は゛は゛www」
(TNK蝋責め)
ひで「ヤダ!ねーヒャダヒャダ!!アアツイ!!あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛」
ひで「う゛!!うー!ハァッ!ヤダ!あ゛あ゛っ゛は゛!う゛!あ゛あ゛アツゥイ!」
虐おじ「真っ赤にしてやるよ今これから(共産主義革命)」
ひで「あ゛ー!う゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛アツゥイ!ああ!ネモーヤダ…」
虐おじ「真っ赤っ赤にしてやるよ」
ひで「あ…、あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!!!!う゛う゛!」
虐おじ「ほら動くと、動くと当たらないだろ?」
ひで「ヒエェーーーーーーーー!!!」
虐おじ「動くと当たらないだろぉ!?」
虐おじ「脚ホラ、掴んでホラ、ケツ見してみろ、ケツの…、もっと、クッっとホラ…」
虐おじ「あ、いいよ?聞かないんだったら…(鞭)」
ひで「ヤァキクキクキクキク…」(まんぐり返し)
虐おじ「自分でホラ、ちゃんと押さえて」
ひで「ねーヤダヤダ!!ヤダ!!!ねヤダそれイ→タ↑イ→イ↑タ↓イ→イ↑タ→イ↓」
ひで「やだああああああああああああああああああああああああああ!!!!」
ひで「うう!!うわあああ!!!あああああああ!!!イタイ…」
ひで「ゲホ…イヤヤダキク…Get it!」
虐おじ「ホラ…、5,4,3,…」(まんぐり返し)
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!!ぐわああああああああああああ!!」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛っつ゛う゛う゛う゛う゛う゛!!あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛は゛痛い!!」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!はあ゛あ゛あ゛!あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!ハ!あ゛!あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!はあ゛!」
ひで「ヤダッキッヤダッユウコトキクネッチョ、ユ゛ウ゛コ゛ト゛キ゛ク゛カ゛ラ゛ヤ゛メ゛テ゛!!!(高速詠唱)」
虐おじ「聞くっつって聞かないだルルォさっきからァ!?言うこと聞かないだろぉ!?」
ひで「ヤダ、ネー、ヤ・メ・テ・ヨ、ニャカッタ!!」
ひで「…わあああああはぁ…」
虐おじ「5,4,3,2,…」(まんぐり返し)
ひで「ううううう!…」
ひで「ア゛!!(スタッカート)」
ひで「ゲフゲフ…イ゛ヤ゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛!!!」
ひで「ア゛ア゛痛゛い゛!!あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛hあ゛あ゛あ゛あ゛」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛も゛う゛!!(ドンドンドン)あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!!」
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛も゛う゛や゛だ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!!!!!」
ひで「や゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛ん゛も゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛お゛!!!!!」
ひで「ヘアッハ…やっ…ハッーーハッハッハッハッハwww…」
虐おじ「起立」
ひで「あ^~もう…ハァ…ハァ…ハァ…」
(疲れたアピールをするひで)
虐おじ「気を付け。俺に見してみろ」
ブゥゥゥゥゥーーーン…
虐おじ「ほら、ちゃんと顔上げて」
ひで「ハァイ…ウッゥ…」
虐おじ「一回転してみろ」
ブゥゥゥゥゥーーーン…
虐おじ「ちゃんと回らないなら(鞭)」
ひで「ヤ!ヤダヤダ…」
ひで「ねやだやめて叩かないで!叩かないでよ!」
虐おじ「やれよじゃあ!!!」
キン!(謎の金属音、通称ヤメチクリウム合金)
ひで「ゲフッ…」
虐おじ「一周、しろよ」
ひで「アイ…アイ…」
虐おじ「もう一周しろよ」
ひで「アイ…」
虐おじ「ゆっくり回れよ?見えないだろ」
ひで「ハァ…ハァ…ハァ…」
虐おじ「あぁ^~良い色に染まったなぁ…」
~~ご奉仕編~~
虐おじ「おぅ、おじさんを気持ちよくさせることができたらなぁ、とっておきのご褒美…やるよ」
ひで「ほんとぉ?(狂気)」
虐おじ「おう、本当だよ。お前と違って嘘つかないからな、おじさんは(皮肉)」
虐おじ「(ペシ)よし…」
虐おじ「その代わり気持ちよくできなかったら…どうなるか分かるな?な?」
ひで「ハイ…」
虐おじ「じゃあお前脱がせろよ、ズボン」
虐おじ「ハァー(クソデカため息)、チッ」
虐おじ「汚れたこれ(ズボン)も、後でどうにかしてもらうからな」
(ひで、しゃぶり始める)
虐おじ「オラァ…足先からやれよ、こっから。舐め上げてこいよ」
平野「(ブツブツブツ)」
虐おじ「ちゃんとやれよ?」
(股間まで来たところで再びしゃぶり出す)
虐おじ「…バカヤロお前、右もやれよ右も」
(TNKを遠ざけられ、右足先からやり直し)
虐おじ「舐め上げてこいよ」
(舐め終え、フ○ラ再開)
虐おじ「ンー…アァ…(恍惚)」
虐おじ「じゃあ上も舐めてみろほら、乳首も舐めてみろほら?ん?」
虐おじ「…チョット待って、ボタン外してみろ」
(おじさんは上から、ひでは下からおじさんのワイシャツのボタンを外していく)
虐おじ「ほら、ちゃんと咥えろよほら」
虐おじ「チンタラチンタラ舐めて…激しくオラ、やれよオラ。おぅ」
ギュイ!…ギュイ!…ギュイ!…
ひで「ゲホッ…ゲホッ…」
虐おじ「ゴホゴホじゃねえよオラ、え?」
ギュイ!…ギュイ!…
ひで「ゴボッ」
虐おじ「ほらどうしたほら、オラァ…(イラマ)」
ひで「ゲホゲホ…ンン…アァ…」
虐おじ「気持ちよくねえんだよオラ…」
虐おじ「おじさんなんて言った?」
ひで「気持ちよくしろって…」
虐おじ「気持ちよくできましたか?」
ひで「ハァ…出来ませんでした…」
虐おじ「でしょ?…」
虐おじ「じゃあオラオラ来いよオラァ!!!!(豹変)」
(ドタバタドタバタ)
~~便所掃除編~~
虐おじ「オラァ…チッ!…」
ひで「やめ!やめて!ヤダヤダ!ウッ!ウッ!」
虐おじ「ほら顔つけろこの周り」
虐おじ「ホラァー!(水洗)」
ひで「あああ!!ウッ!ウッ!嫌!」
虐おじ「オラ、つけろオラ!」
虐おじ「えーオラ、どうなんだよオイオラ!え?」
ひで「止めて!」
虐おじ「オラつけろよホラ、オラ」
虐おじ「ほらお前騒がないでじっとしてろよ、なぁオイ」
ひで「あー、あー!あー止めて^~!!あー、あー、あー…」
虐おじ「顔上げろ、顔」
虐おじ「お前ちょっと周り舐めてみろオラ、掃除。オラ便所掃除しろお前。なぁ」
ひで「ハァ…ハァ…」
虐おじ「悪い子は便所掃除だよお前」
ひで「ヤダ!」
虐おじ「ほら、まわ、まわ…」
ひで「ヤダ」
虐おじ「汚えからよお前、一週間ぐらい今日洗ってねえから。洗えよおい、なぁ」
虐おじ「やれよ早くおいオラァ!周り、ホラ、周り舐めろおいホラ」
ひで「あ^~」
虐おじ「ホラ、どうなんだホラ、え?」
虐おじ「逆も然りほら、周り、しっかり、便所掃除しろしっかりホラ」
ひで「イヤ、ウーン」
虐おじ「お前便所掃除なんかやったことないだろお前!なぁ」
虐おじ「ちゃんとキレイにしろよオイ」
虐おじ「ほら、ここもほら!真ん中の方もやれよホラ」
ひで「ブホー」
虐おじ「ホラ中もやれ那珂も(水洗)」
ひで「ああああ!ウウ冷たい!」
虐おじ「ほら、え?」
ひで「あーははー…ヤダ…」
虐おじ「どうなんだよホラ」
ひで「アッー…アッー!アッー!アッー!ウッー!」
虐おじ「掃除しろちゃんとホラ!」
ひで「や^~!」
虐おじ「周りやれよ」(音声編集によりセリフが途切れている?)
虐おじ「えぇ?おいゴラァ、顔上げろ」
虐おじ「お前こん中にケツ突っ込め、な?おい」
虐おじ「やれよほら!早くやるんだよォ!」
ひで「アーイtt…」
虐おじ「ほら、ケツ…突っ込めよ」
ひで「アー、イタイ…」
虐おじ「ケツ突っ込めっつてんだよなぁ、分かる?『突っ込め!』」
ひで「ウー☆」
虐おじ「突っ込めって言ってんの!ね!?突っ込めって言ってんだよ!!!(特攻隊)」
ひで「も、入んない…」
虐おじ「入んねぇのか?(落胆)」
虐おじ「お前アレ…口答えするんだな?」
虐おじ「まっいいやお前…、今日から…、便器だな(就職内定)」
虐おじ「…ホラ、何だ今の反抗的な目はァ~~!」
(ションベンをかけられるひで)
ひで「ん…んあー…」
虐おじ「あ^~~~!オラ、オラw」
虐おじ「なんだこの手!なんだこの手ぇは!?(驚愕)」
虐おじ「ウォラ、送辞」
ひで「んあー!」
虐おじ「舐めろ」
ひで「オー、オー、オー、オー、ンー!ん…ンー…ンー…」
虐おじ「きったねぇおめぇ」
~~お風呂編~~
虐おじ「え、入れよオラ、ホラ」
虐おじ「水。張っといたからお前の為に」
ひで「ハイ」
虐おじ「ホラ、入れ。モタモタしてんじゃねーよ」
ひで「アーツメタイ、ヌァ、あぁ^~」
虐おじ「あーホラ、『あぁ^~』じゃなくてホラww」
(水風呂にひでを押し込む)
ひで「アーツメタイ…アーツメタイ!!アー!アー!アー!ア!アー!ウー!ウ!ファ…、止めて!ハァ…ハァハァハァ…あぁ^~ツッ!う~わーもう!ア↑ー!」
ひで「…ア!ウ!」
虐おじ「あた、頭もホラ」
ひで「アー!アッアッアッアッアッアッハッハッあーもう…」
虐おじ「よしー。こっち向いてみ?こっち向いて?ホラこっち向け?」
(オードリーWKBYS)
ひで「うわぁ!ハァ!ハァ!ハァ!ハァ!あーもう…」
ひで「おbgrrrr…あー、ペプシ…」
虐おじ「ペプシじゃねえ!ほら頭洗ってやるよ(親切)」
ひで「bgrrr…苦しっ…(ぜかまし)(だらしねぇ(レ))」
虐おじ「ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛!!」
ひで「brrrgg!!」
虐おじ「オラァ!!」
ひで「ああ逃れられない!(カルマ)ねーヤダ…ああ…」
虐おじ「ホラァ!」
ひで「ハァ!ウ!ウ!ウ!ウ!ウ!…プ、…ブワァァァァア!ヤダ…」
虐おじ「ほら頭洗ってやるよ」(音声編集によりセリフが途切れている?)
虐おじ「汚いだろォ!」
ひで「ヤー↑!ヤー↑!ウゥ~!ウァー!ハァハァ…ウ!ハァハァハァ…」
(ひでの頭を水風呂に沈めようとするおじさん)
ひで「わかったわかったダイエー!」
ひで「ダイナマイッ!!」
虐おじ「ウ゛ウ゛ウ゛ウ゛ゥ゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛!!」
ひで「あああヤバイ!」
虐おじ「ア゛ア゛ア゛ーーーー!!」
ひで「ヤダホントに…」
虐おじ「ウ゛ア゛ア゛ア゛ア゛ア゛!!」
ひで「hm…」
(抵抗するひでに普通に力負けして沈められず。一瞬の静寂)
ひで「ブワァァァアア!!アァ!」
虐おじ「じゃあ束子で洗ってやるからな、えぇ?ほら」
ひで「ハァハァハァハァハァ…」
虐おじ「気持ちよかっただろ?」
虐おじ「束子、ほら」
ひで「アー☆ウー☆ハァ☆ウー☆ウゥ↓☆…ハァ」
虐おじ「(蝋)落としてやるからな。ほら」
ひで「ハァ…ハァ…ハァ…ア゛ア゛、ハァ…ハァ…アァ…ハァ…ウ゛ウ゛!ウ゛ー!、イテ…ウ゛ー!」
虐おじ「ついてんじゃねーかここに(太もも)」
ひで「ウー!ウー!ハァ…ハァ…ハァ…」
虐おじ「いっぱいついてるよ、ホラ?後ろ向け後ろ」
ひで「ウ゛ー!ウ゛ー!ウ゛ー!ン゛ン゛!ウワァ!アッー!ウワァ!ウー↑!ウハァハァハァ」
虐おじ「動くんじゃないよ、前向け前!(ダブルバインド)」
ひで「ハァハァ、ウワアアア!!ウウ…うわああ!あああああいt…ゥウーわああhああああwww!」
ひで「うわああああ!ああああ!うわ!ヘアッハ!あああ↑あああああ(ラックに頭をぶつける)イデッ!ああっは…」
虐おじ「暴れると痛いぞ~(アドリブ)」
ひで「うううわああああ!うううう!えあああああ!うううううハァハァ…、ヘァヘァ!」
虐おじ「ついてンだろ腹に!」
ひで「ング!ン゛ン゛ン゛!あああ!」
虐おじ「腹についてるだろ!」
ひで「ングアア!ヘアッハ!ンアアア!…ア゛ア゛!ヘフうううう!ヘフへフヘフ…」
虐おじ「ほらほら、手どけろ手!」
ひで「ウ゛ワ゛!う↑ぅ↑!(円谷プロ作品特有のやられモーション)痛ッァい!」
ひで「いっt…」
虐おじ「ホラ!」
虐おじ「ポコチンの方も、ほら、ほら(露骨に手加減)」
ひで「う…う゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!デュフ、いt、いt、うわああは、ヘフへフへフへフ…」
虐おじ「オルルァどうした(KRDTKY)」
ひで「う゛う゛う゛う゛う゛!うーいt…ハァハァハァハァ…あ^~イタイイタイイタイ↑痛い痛゛い゛!痛い!あぁ!?」
虐おじ「あぁほら、良かったな、ほら」
虐おじ「自分から入っていくのか…(困惑)」
ひで「あ~、おっスイマセン(素)」
ひで「gbrrrrr… ブワァァァァアァァ!ハァハァハァ…」
虐おじ「良かったな、ホラ、お疲れー^^(浸かれー)」
ひで「ウゥ!ふぅわ!ふぅわああああーーー!ヘフふわあああああ!うわああああヘフふわあああああ!ハァ…ハァ…」
虐おじ「20秒ね?」
(シャワー開始)
ひで「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!う゛!あ゛!あ゛!ゲフゲフ…あ゛!ゲフあ゛!ゲフあ゛!あ゛!あ゛!ドゥフ…」
虐おじ「…3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13」
ひで「ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!ヘゥ゛!お!お!お!」
ひで「溺れる!溺れる!!」
虐おじ「14,15,16,17,18,19…」
ひで「ウワァ!ハ!ハ!ハ!ハ!ハ!アァ↑!アァ↑!アァ↑!…」
ひで「ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…」
ひで「アーボ…(二匹目)」
ひで「ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…ハァ…」
~~肛虐編~~
(まんぐり返しで柱に縛られているひで)
ひで「何すんの?」
虐おじ「挿れてやるからよ…」
(ひでのケツ穴にローションを垂らす)
ひで「あっ…///…ん…ん、あー」
虐おじ「どうだ?」
ひで「イタイー」
虐おじ「痛い?」
ひで「ウー、あー…あー…あ…」
虐おじ「これな?(ア○ルビーズを見せる)」
ひで「そんなの…入んないよぅ…」
虐おじ「ん?(聞き取り困難)入るだろ?」
ひで「ハインナイ…」
田舎少年「うわああああああああああああああああああああ!」
虐おじ「“上”が騒がしくなってきたな…」
田舎少年「うわああああああああああああああああああああ!」
ひで「う、あーーあーあーー…」
虐おじ「あ↑ぁ↓゜…」
ひで「アーーーーうわぁーーー!」
ひで「ナァ^~~!」
虐おじ「ほっ」
田舎少年「うわああああああああああああああああああああ!」
ひで「ねぇちょっと痛い!ねぇニコは要んない!(エグゼイドアンチ)」
虐おじ「えぇ…?(困惑)入んねぇのか?」
ひで「ぬん…」
田舎少年「うわああああああああああああああああああああ!」
虐おじ「頑張ってみようか?」
ひで「やー無理…ねぇニコ…nコ入んない…エンリコ・ハインナイ!」
ひで「あー!うー!あー!ああああああ…あああああーーーーァァァァ…うううーーー…(ここでア○ルビーズが引き抜かれる)うああ!ハァ、ハァ、ハァ…ハァ」
ひで「ねぇもう…(デ○ル○登場)…あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛!!」
ひで「あーツモッ、うームリィ、うー☆、うー☆、あ゛あ゛!であああ」
ひで「ああ!うう ケホ…ヌフ…ああ!…ああ!…あー↓…うー↓…ドゥー↓」
虐おじ「ほらどうした、ほら力抜け?力抜けほら、ホラホラホラ」
(マスターソード)
ひで「うー↓、あぁ^~~グルジア~~!」
虐おじ「挿入ったぞ?」
ひで「あ~!うー↓、あー!ああ↑あ!オォ…オォォォ!」
ひで「あー!ライララライ!痛い…ッグ、あーちょっと…」
虐おじ「自分でやってみろ」
ひで「痛いにょ(DGK)」
虐おじ「自分で挿し入れ…」
ひで「アー痛゛ぃ゛の゛!!(半ギレ)ネーヌイテェもう!ねぇ痛い、本当痛いんだってぇ…ねーもう!」
虐おじ「自分らしい自分を…(自分で出し入れしてみろ)」
ひで「うっ!…ヌッ!うああ!うう、ううhあああ…」
(ひでの凄まじい形相のクローズアップ。通称ヤメチク・リー)
ひで「あー…ハァ…ハァ…あ^~~~~~~!あ^~~~~~!」
虐おじ「え?痛いんだろ!?」
ひで「グリザイア~~~!!」
ひで「あーーー、ぐあ゛あ゛あ゛あ゛あ゛、ぬっふーん、へあっはあ゛あ゛あ゛ん゛も゛お゛お゛お゛お゛!」
田舎少年「うわああああああああああああああああああああ!」」
ひで「んあ、ねううううううん!あー…うあー…」
(デ○ル○をひり出すひで)
ひで「クソォ!(悪態)」
ひで「あー!あー!うあー!ハァ…ハァ…ハァ…」
ひで「ああ^~もうお○っ○出ちゃいそぉ!(池沼)」
虐おじ「出していいぞ」
ひで「そんなことしたらパパに怒られちゃうだろ!(父子家庭)」
虐おじ「怒られねーよ。なんてったってお前は便器だからな(ぼくビデ)」
虐おじ「ほら、出してみろよ」
虐おじ「ほら、出していいぞほら。ほら」
ひで「ヌ…ヌ…ヌア…うーあ」
虐おじ「キッタネェー、流石便器だなお前」
ひで「う…うーあ…ヌア…ヌア…うっ…ヌア…ヌッ!…ハァハァ…」
虐おじ「これ(酒瓶)何すると思う?これから」
ひで「やだ…」
虐おじ「何すると思う?これから」
虐おじ「ブチ込むんだよ」
ひで「ヤダ(食い気味)」
虐おじ「ん?何が嫌なんだ?」
ひで「ヤダ!」
虐おじ「何が嫌なのか言ってみろよ…こんなんじゃ足りないってか?」
ひで「yだ、ヤダヤダ!」
(酒瓶挿入)
虐おじ「えぇ…ほら」
ひで「う…ヌッ!」
虐おじ「ほら…ええおいほら?」
ひで「あっ…///…うー↑…あっ…///…うー↑…あっ…///…あああ//…あk//…あ、あー!、あー!、あー!あー!あー!ううやだああ~!」
虐おじ「オルァ…(グリグリ)」
ひで「あー!あ!あー!あー…あー…あー!」
虐おじ「ちょっとずつ入ってきてるよ…ほら」
ひで「あー…あー…あー!あー↓あー…」
虐おじ「えぇ…(ペシペシペシペシ)」
~~ス○ト○編~~
虐おじ「お前、う○こ出たな?う○こ塗ってやるよじゃあ(狂気)」
ひで「やだ!やだ!ねぇ小生やだ!やだ↑やだ↑↑や~~↑↑↑ハフハフ…」
ひで「ねーホントムリムリムリムリ、ねぇ、やー、ふー、うっ一、ああーッ!!」
(ひでのう○こを塗ろうとするおじさん)
ひで「ぎゅっ!うゎー!すた丼…」
ひで「ゲホッ…ゲホッ…う~わ゛~~!ゲホッ、オエ…オエ、ゲッホゲッホ!!!」
ひで「ア゛、ヴォエ!!うわあ~、や゛~!!ねーやだぁーやだ!」
ひで「ネプッ!嫌~~~!う~~h~~…うー!うー!うー、ゲホ…ゲホォェ…」
ひで「ヴヴヴヴォォォォエ!!!!」
虐おじ「えぇ…(困惑)」
ひで「ネームリムリ!うー☆うー☆…やだ~~~ううううう~~~~!嫌~!」
虐おじ「くっせぇなオメェ…」
ひで「あ~~~~~!」
虐おじ「ナンダオマエ!クッソォ…(ひでを消臭)」
ひで「う…う…ヴォエ!ヴォエ!ゲホゲホゲホ!…ヴォエ!ヴォェ…ヴォ…ヴォ…ヴォエエエ!!!」
~~ガン掘り編(ホモの抜きどころ)~~
虐おじ「し~~~、おぅ…おぉ…」
ひで「イテテッテ」
虐おじ「おう今まで頑張ったからご褒美あげるよ」
虐おじ「な?ほら、手ついてみろもっと下に、言うこと聞けよ?ほら」
ひで「ハイ」
虐おじ「もっと下についてみろ、手」
(後背位で掘られるひで)
ひで「これが、ご褒美なの?なんか犯されてるよぉ…?あぁ///…」
(ベッドで深山のような体位になる)
虐おじ「脚脚ほら、持てよ脚…」
虐おじ「ちゃんと締めろよほら、もっとほら」
(頭を何度も上げ下げするひで)
虐おじ「ほら、えぇ?自分でシゴいてみろよ…」
虐おじ「ほら…どうなんだよホラ、え?」
ひで「あー苦し」
虐おじ「しねよ(直球)」
ひで「クルシッ」
ひで「あーイく(棒読み)」
ひで「あーイク(2カメ)」
虐おじ「ホラ出てるよなんか、お前先イったんだろォ…(ねっとり)」
虐おじ「オォ…×N」
(ひでに顔○する虐待おじさん)
虐おじ「スーハースー…ハー……」
(精○をひでの顔中に擦り付ける)
ひで「ンンンンンンンンンンン…」
~~締め出し編~~
虐おじ「こっち来い…」
ひで「うん、ナ…」
(窓際に連行されるひで)
窓「ガラガラガラガラガラガラガラガラ…」
窓「ピシッ!!!」
(自分から出ていくひで)
ひで「ねぇ助けて、ね、TAS…助けて入れて!(ガンガンガンガンガン…)」
窓「ピシッ!!!」
ひで「ねぇ寒い入れてよぉ…入れてってばぁ…(ガンガンガンガンガン…)」
(即死カーテン君)
虐おじ「はぁぁ…」
窓「ガンガン…」
(突然ひでが窓を叩くのをやめて終了)
編集
※シャワー室に入ってくるKBTIT
KBTIT「なんだよ…」
KBTIT「おお…今日も美味そうな獲物がいるじゃんよ」
KBTIT「おっペンギンちゃーん?(イケメンじゃーん)オイ」
ポイテーロ「触んなよ…」
KBTIT「何だよ、ここに来たからには・・・何されるかわかってんだろうなぁ、オイ」
ポイテーロ「離せよこの…」
KBTIT「お前の悶絶する顔が見たいんだよ!お友達になるんぜよ!(俺の犬になるんだよ)」
KBTIT「もう出られないぞホラ」
KBTIT「ホラ来い」
ポイテーロ「やめろ離せ…」
KBTIT「クォーイ!」
ポイテーロ「離せっ…」
KBTIT「オイ!」
※股間に優しい膝蹴り
ポイテーロ「アウーン!アウン!アウン!」
ポイテーロ「アッ!ハナセ!(棒読み)」
KBTIT「来い!」
ポイテーロ「ハナセ!」
~鞭打ち編~
ポイテーロ「ア!(スタッカート)」
KBTIT「ほら叫べ!」
KBTIT「逃げんじゃねーよ!」(拘束されているポイテーロに向かって)
KBTIT「段々気持ち良くなってくるぜこれが」
KBTIT「もぉ~逃げんじゃねぇよ~」
KBTIT「おぉ良い色に染まってきたにゃ~ん?ホラ?全身が~(倒置法)」
KBTIT「最後の一発くれてやるよオラ!」(と言いつつ2発)
KBTIT「おぉ。じゃあ次行くぞ」
~洗濯バサミ責め編~
KBTIT「なんだその反抗的な目は~?まだ足りねんか?」
KBTIT「これ分かるかこれ?」(洗濯バサミを取り出す)
ポイテーロ「何すんだよ・・・」
KBTIT「お前を芸術品に仕立てや…仕立てあげてやんだよ~」
ポイテーロ「ふざけんな!」
KBTIT「お前を芸術し、ひぃんにしてゃんだよ!」
ポイテーロ「ふざけんな…」
KBTIT「お前を芸術品にしてやるよ(妥協)」
ポイテーロ「ふ・ざ・け・ん・な!ヤ・メ・ロ・バ・カ!」
ポイテーロ「アッー!」(洗濯ばさみ装着。寒さで震えているので洗濯バサミもブルブルしている)
ポイテーロ「…くそぉ!Damn it(てめぇ)…ポイテーロ(覚えてろ)」
KBTIT「何震えてんだお前?そんなにキモティンカ?ん~?」
ポイテーロ「ふざけんなてめぇ!」
KBTIT「おー良いカッコだぜぇ?」
ポイテーロ「ふざけんなてめぇ!(リピート)」
KBTIT「おー良いカッコだぜぇ?(リピート」
KBTIT「おぉ、イキがあって良いぜこの奴隷よ」
ポイテーロ「てめぇの奴隷なんか誰がなるか」
KBTIT「なるんだよ今日から~」
ポイテーロ「ぜってぇなんねぇ」
KBTIT「そういう風に仕込むんだよ。その為にこれやってんだろ?お前」
ポイテーロ「ぜってぇなんねぇ…」
KBTIT「痛みで分からせなきゃだめなんだよ最初は」
KBTIT「キモティ=ダロ?ほら」
ポイテーロ「ヤ・メ・ロ・バ・カ…」
KBTIT「感じんだろ?」
ポイテーロ「触れんな!」
KBTIT「えぇ?」
ポイテーロ「てんめぇ覚えてろ…」
KBTIT「全身芸術品にしてやるよ」
KBTIT「写真撮ってばらまいてやるからな?あぁ?」
ポイテーロ「ふざけんなてめぇ…」
KBTIT「はぁはぁはぁはぁ…」
KBTIT「客も取ってやるよ客も」
ポイテーロ「てめぇの奴隷なんかなるか!」
KBTIT「デブハゲの親父に抱かれるんだよ。あぁ?」
ポイテーロ「ぜってーおめぇの奴隷なんかならねぇ」
KBTIT「誰も助けに来ねーぞ」
KBTIT「可愛いぜ?」
KBTIT「そのうちこれが勃つ様になるからな?ん?気持ち良い薬も仕込んであるぜ?お?」
ポイテーロ「ぜってーおめぇの奴隷なんかなってやんねぇ」
KBTIT「俺の奴隷じゃねぇよ。客の奴隷になるんだよ、客の」
ポイテーロ「ぜってーならねぇ」
KBTIT「いい金になるからな」
KBTIT「抱かれたくて来たんだろ?違うか?男探しに来たんか?」
ポイテーロ「ふざけんな」
KBTIT「行くぜぇ~、お前の急所…」
※乳首に洗濯バサミ装着
ポイテーロ「てんめぇ、ざけんな…」
ポイテーロ「ざけんなてめぇ!」
※チ○コに洗濯バサミ装着
KBTIT「お前のもん使いもんにならなくしてやるよ」
ポイテーロ「てめぇ…」
KBTIT「どうだ?」
ポイテーロ「てめぇ…」
ポイテーロ「ぜってーてめぇ許さねえ…」
KBTIT「いいカッコだぜぇ?」
KBTIT「いいカッコだぜぇ?(リピート)」
KBTIT「何?許さねぇだと?(時間差)」(ポイテーロのセリフから7秒後)
KBTIT「んな生意気なこと言ってて…これからどうなるかわかってんだろうなぁ?お?」
KBTIT「この綺麗な顔もめちゃくちゃにしてやるぜ?」
※顔に洗濯バサミ装着
ポイテーロ「へめぇおほえてろ…」
KBTIT「この口にチ○ポ突っ込んでやるからなぁ?」
KBTIT「これで百個だぜ!おめでとう!」
KBTIT「おぉーいいなぁ!こっち見ろこっち!イケメンが良い顔してるぜぇ~?」
KBTIT「おぉーすっげえなあ」
KBTIT「じゃあこれから・・・取ってやるぜ?」
KBTIT「なかなか食いついて離れねぇなー、お前のこと好きみたいだぞ!ホラ~、お前に群がる男みてえだなー(自己嫌悪)」
KBTIT「取ってやってんだぞぉ!」
(ポイテーロに首輪をつけて散歩へ)
KBTIT「早く歩け!汚ねーなぁ」
KBTIT「わんはどうしたわんは!しょうがねーなホントに!」
KBTIT「何やってんだよオラー、ちゃんとウチへ連れてけ!」
KBTIT「筋肉質にしてやんねぇとな」
(体育館へ)
KBTIT「どうだ?また叩かれるか?」
KBTIT「聞くか!?」
KBTIT「お~・・・言ったな?」
KBTIT「もう鞭は嫌か?」
KBTIT「また…言う事聞かなかったら、ちだ、血だらけにするぞ」
KBTIT「お前はもう俺の犬なんだ。犬なんだ。分かったか?ん?」
KBTIT「ワンって言ってみ?」(ワン)「でっかい声で!」(ワン)「よし…可愛がってやるからな」
KBTIT「もし反抗したらこれで殴るからな」
KBTIT「俺んちの体育館だからすっげーだろ?おう?」
KBTIT「今日からたっぷりここで可愛がってやるからなっ↑」
KBTIT「ん?気持ちいいか?おー可愛いじゃ~ん。エロいぜぇ?」
>>2045
ならば戦争決定だなけれどどうせお前は私がどこにいるのかも知らないだろまぁせめてどの県にいるかだけ言ってやる今は沖縄県だ新しい支部第2沖縄支部のリーダーになったため私守矢1等中佐お前らまだ慣れてないと思から守矢1等少佐が沖縄に行くという訳だそれを頼りに探しな
>>2048
けれどそこは本部じゃないぜ☆なんにせよ本部は北海道だからなそもそもお前はどこの県にいるのか教えてもらいたいね
>>2048
そもそもお前キモイねんなんだよあのストーリーキモ過ぎるだろうがお前これ大人向けでも子供向けでもないエ○チな大人向けの本やないかもっとましなのか来なさい
>>2048
お前のストーリーよりこっちの方がまだ良い方だお前のストーリーは第2期作るな↓の方のアニメは3期作れ

>>2048
はいはい良い子はミルクでも飲んで寝てなさい10コメさんwwwwwwwwww
>>2048
私のストーリーと貴方のストーリーどっちがマシかと言われたらこっちがマシに決まってるだろうが「マウント」
第30話満月の決戦
ナレーション「その後沖田の治療に成功し沖田は難を逃れたこれを沖田1等大佐殺人失敗事件となずけた」
板墨「いいか沖田今回は大阪府豊中市新千里の所にある千里中央の全体を見張れ今回は敵であるネット帝国の居残りを探しにここに来た」
沖田「はい板墨様では私は南広場を」
板墨「私は北広場を」
板墨&沖田「ではまた朝5時に会おう」
板墨「それにしても夜は暗いな」
沖田「とりあえず南広場全土を探さないと」
板墨「とりあえずそこの山から探すか」
板墨「それにしても小さい山だな子供向けか」
敵の幹部「板墨覚悟―」
板墨「フン」
カキーン
板墨「はいはい敵ですかこの名刀月の丸がお前の腹を少しだけ切る」
敵の幹部「そんな日本刀でやるのかよこの中国の剣青龍刀で切ってお前の刀をたたき割ってやるよ」
板墨「へーお前中国人なんだな声を日本語にしようとしても下手すぎるなお前」
敵の幹部「うるさいお前の刀を砕いて次にお前の頭をこの剣で真っ二つにしてやる」
板墨「やれるものならやってみろ勝負だ」
一方そのころ
沖田「とりあえず3階に着いたけどなかなかいないな」
敵の幹部2「板墨の幹部覚悟―」
沖田「おっと危ない危ない子の名刀日の丸がお前の背中に少し傷をつける」
敵の幹部2「やれるもんならやってみろ俺のさっきリーダーからもらった子の青龍刀でお前の腹の骨を打ち砕いてやる」
沖田「いざ勝負」
一方そのころ
板墨「フン」
ガキ―ン
敵の幹部「弱いなそんな攻撃でやられるとでも思ったか」
青龍刀にひびが入る音「ピキ」
板墨「フン」
青龍刀にひびが入る音「ピキピキ」
敵の幹部「そんな馬鹿な青龍刀にひびが」
敵の幹部「クソジパングめよくも」
板墨「フン」
青龍刀が割れる音「パキーン」
敵の幹部「嘘だ」
板墨「呆然としてないでさっさとこっちにこい」
敵の幹部「はっはいー」
一方そのころ
沖田「よいしょ」
青龍刀が割れる音「パリリーン」
敵の幹部2「嫌だ認めたくない認めたくないんだー」
沖田「暴れても無駄だよさっさと来な」
敵の幹部2「嫌だあっあっあああああああああああああああ」
その後
板墨「なんとか片付いたな」
沖田「ええそうですね」
第31話をお楽しみに
>>2055
そもそもお前は何であんな変態向けのストーリーを書いてるんですか?理由を言ってくださいいいこと言ってやるからとっとと言いな
>>2055
そもそもwwwお前のストーリーよりwww私のストーリーの方がwww変態向けには入りませんよwwwwつまりこれ出版したらどっちの評価が高くなると思うwww私だよwwwお前見たいな変態ストーリーは人気無くなるよwww
(公園を歩くだいちを盗撮する平野)
平野「がわ゙い゙い゙な゙ぁ゙だい゙ぢぐん゙」
(平野、座っているだいちに後ろから近寄り声をかける)
平野「だいち君こんにちは~」
だいち「お兄さんだぁれ?」
平野「僕は、だいち君のお母さんのお友達だよ」
「何してるの?こんなところで」
「早く帰らないとお母さん心配しちゃうよっ」
だいち「え、お母さん今日仕事でいないんだよね、お家に帰っても僕一人だけなんだぁ」
平野「そうなんだ、じゃあ、お母さんが帰ってくるまでお兄ちゃんのお家であそぼっか」
だいち「え?お兄さんのお家?」
平野「お菓子もジュースも、おもちゃもたくさんあるよ」
Now Loading...
だいち「えーでもステラな(知らない)人だし、なんかお母さん知らない人のお家に行っちゃダメって言ってるよ」
平野「そっか、だいち君are(複数形)お利口だね」
「じゃあ、ちゃんと、ご挨拶しなきゃね」
ヒヨドリくん迫真の警告
平野「じゃあ僕は、だいち君の、お母さんのお友達の、平野。君は、だいち君。よろしくね!」
だいち「うん」
平野「ほら、これで知らない人じゃなくなったよ(ペニーワイズ)」
だいち「うん!」
平野「じゃあ、お兄さんのお家、行こうか!」
だいち「うん!」
平野「じゃあ行こうか」
~平野の家~
平野「どうぞどうぞ」
だいち「あっ、お邪魔しまーす」
平野「どうぞ入ってくださ~い」
だいち「お兄ちゃん家って結構近いんだね」
平野「そうだね…じゃあとりあえずここに座ろっか」
「今からお茶とジュース持ってくるからね」
だいち「ありがとうございまーす」
(だいち、リビングのソファーに座る)
(平野は台所でオレンジジュースに睡眠薬を投入)
サッー!(迫真)
(平野、お菓子とともにジュースをもってリビングへ)
平野「淡い(は~い)だいち君おまたせ~」
だいち「ありがとう」
平野「犯すだよ~(事後予知)(お菓子だよ~)」
だいち「あっこんなにいっぱいいいの?」
平野「うんいいんだよ。たくさん食べて、おかわりもあるから」
だいち「いただきまーす」
(平野はソファーに座りだいちが食べる様子を見つめる)
平野「どうぞ」
(だいち、いい食べっぷり)
「お菓子おいしいかい?」
だいち「うん美味しいよお兄ちゃん」
平野「たくさん食べてね」
「ジュースも飲んでね(催促)」
だいち「うん」
(だいちここでやっとジュースを手に取る)
だいち「いただきます」
平野「飲んで飲んで(せっかち)」
「おいしい?」
だいち「うん、おいしい」
平野「かわいいなだいち君…」
だいち「ん?何か言った?」
平野「ううん、何も言ってないよお食べお食べうんうん」
「うん…うん……ジュースも飲んでね(二度目)」
だいち「お兄ちゃんジュースおかわり」
平野「はい、ちょっと待ってね」
(だいち、あくびをし目をこする)
だいち「ん~眠いかな」
(だいち遂にダウン、そこに平野が戻ってくる)
平野「だいち君お待たせ~…あっ」
「やっと…眠ったか(ご満悦)」
(だいちの帽子を取り、寝顔をねっとり眺める)
平野「だいち君の寝顔もかわいいなぁ」
(だいちを椅子に座らせ、上半身を裸にし、ビデオカメラで撮影する平野)
平野「はぁ~いいなぁ~んん~」
「すべすべだぁ…はぁ~だいちくん可愛いなぁ~」
「はぁどうしてそんなに可愛いんだ?ん~?」
(平野、だいちの股間を小刻みに触る)
だいち「んん…」
平野「あっ!」
「大丈夫大丈夫…よし」
(平野、だいちの手を後ろに回し椅子に縛り付ける)
平野「だいちくんのおへそも可愛いなぁ」
「はぁ乳首が特にかわいい…」
(ひとしきり乳首とへそを舐めた後に再び股間に手をやる平野)
平野「あぁ凄いっ!あぁたまんないよぉ…」
(ここでズボンを脱がせる)
平野「はぁだいちくん可愛いなぁ…」
「はぁ可愛い…」
(パンツに顔をうずめ臭いをかぐ平野)
平野「これがだいちくんの…臭いかぁ」
「パンツの中はどうなってるのかぁ?」
「(勃○チ○ポを見て)あぁ~たまんない」
(平野、ついにパンツを脱がせだいちを全裸にする)
平野「これがだいちくんの…おち○ち○かぁ(恍惚)」
(平野、乳首舐めを再開、乳首を舐めるのに連動してだいちのチ○コも動いている)
平野「だいちくんのおち○ち○…いい臭い」
(脱いだパンツの臭いをかいだ後、フ○ラを始める平野)
平野「美味しい…だいちくんのおち○ち○美味しいなぁ…」
「だいちくん可愛いなぁ!肌も…美しい」
だいち「…ここどこ?(起床)」
「えっお兄さん何やってるの!?」
平野「もう目覚めちゃったかぁ ハァハァ」
だいち「何やってるの?」
平野「楽しいことしてるんだよ」
だいち「やめて!」
「やめてお兄ちゃん!」
(平野、だいちの口を手で塞ぐ それでも叫び続けるだいち)
平野「ねっ、大きい声出すな。ダメだよ」
「じゃあお兄ちゃんともっと楽しいことしようか」
「じゃあ大きい声出しちゃダメだからね」(ここで手をいったん離す)
だいち「助けて!」
平野「ほらダメだって…何するんだ!!」(再び口をを塞ぐが、だいちが手を噛んだ)
だいち「お兄ちゃん何やってるの変態!」
平野「ただ楽しんでるだけや!(豹変)」
だいち「警察呼ぶよ!」
平野「何を言ってるんだ!呼べるものなら呼んでみなよほら」
だいち「助けて!」
平野「お母さんに言うぞ!」
(再び口を塞ぎ、また噛まれる)
平野「また噛んだな!よし君みたいな子はお仕置きだ!」
だいち「やめて…」
平野「お仕置きしないと…ダメだお前みたいな子は」
~ベッドに移動~
だいち「やめて!」
平野「楽しいこと…しようね」
だいち「やだ!やめて!」
(平野、だいちにしゃぶりつく)
だいち「や、やめて!」
平野「ほらだいちくん、お○っ○するところ舐めるよ」
だいち「やめて!」
平野「あぁだいちくんのおち○ち○美味しいよ」
だいち「やめ…」
平野「だいちくんおち○ち○舐められて気持ちいい?」
だいち「気持ち悪い…」
平野「なんか…変な感覚じゃない?」
だいち「気持ちよくなんてない!」
平野「これはね、おち○ち○が気持ちよくなってる証拠なんだよ(勃○)」
「気持ちいいって言ってるんだよこれは」
だいち「気持ちよくない!」
平野「これは気持ちいいって言ってるんだよほら」
「ほら凄く硬くなってる」
だいち「やめて!」
(だいちをちんぐり返しにして肛門を見つめる平野)
だいち「やめて!」
平野「ここも可愛いねぇ」
「だいちくんのここも可愛い」
「お兄さんが舐めちゃおうか」
だいち「やめて!やめて汚い」
平野「だいちくんのここは綺麗だよ」
だいち「そこう○ち出てるとこ…」
(体勢を戻し上にまたがる平野)
だいち「なんで服脱いでるの?」
平野「これからもっとね、楽しいことするんだよ?」
だいち「何が楽しいことなの?やめて…」
(平野、下半身を脱ぎ、だいちの体を押さえつける)
だいち「痛い…」
平野「さっきね、僕がね、だいちくんのおち○ち○をね、舐めたみたいにね、舐めてごらん」
だいち「あぁっ、ヤダ!」
平野「口開けてほら、口開けて」
「口開けてほら、ちゃんとね口開けてほら」
「口ちゃんとね、開けないとね、気持ちよくないからね、楽しくないからね」
(平野、だいちの口にチ○コを投入)
平野「さっきね、僕がね、舐めたみたいにね、舌でほら、飴玉を転がすみたいにね、やるんだよほら」
「ほらね、もっと飴玉をね、ほら転がすみたいにね、するんだよほら、ちゃんと口開けてね」
だいち「苦しい!」
平野「だいちくんのお口すごい気持ちいいよ」
だいち「気持ち悪い…」
平野「気持ち悪くないよ、楽しいことだよほら」
「じゃあ今度は舌出してみようか、ほら舌出してほら」
「舌出して、ほら舌出してもっと舌を出して、そうそうそう そのままねそのまま」
「はいそのまま舌出してね、ほら舌出してね、もっと舌出して」
(ねっとりキスを連続でやる平野)
平野「じゃあねお兄さんとねもっとね楽しいことしようね」
だいち「嫌ぁ…」
平野「ね、もっとねしようね!もっとしようね!」
(平野、指を舐めだいちの肛門に指を入れる)
平野「だいちくんのここは狭いなぁ、きついなぁ」
「落ち着いてね」
(再びちんぐり返しにしてだいちのケツにローションを塗る)
平野「ちょっと冷たいかもしれないけど…」
「大丈夫だから」
「お兄ちゃんのね、指挿れるよ」
だいち「あ″ぁイタ!痛い!」
平野「どんどん入っていくよ」
「あぁ根元まで入ったよほら」
「見えるか?ね、指がね入ってるよ」
「次はね、もっといいものをね、入れるからね」
だいち「やめてよぉ!」
平野「いいものをね、入れてあげるからね」
(平野、遂にだいちに挿入)
だいち「痛い…やめ…やめて」
平野「締まりが凄いなぁ」
「だいちくん締まりが凄い」
(ガン堀り開始、平野は再びビデオカメラで撮影)
平野「あぁ気持ちいい」
「凄い気持ちいい」
「ねぇだいちくん、可愛い君を記念に撮ろうね」
「気持ちよくなってきたの?」
だいち「気持ちよくない!」
平野「ほら、どんどん気持ちよくなっていくからね」
「あぁだいちくんの中に入っていくよ」
「だいちくんの小さいおしりの穴にお兄さんのおち○ち○が出入りしてるよ」
「だいちくん…たまんないよ」
(体勢を正○位からバックに変更)
平野「だいちくん気持ちいいよ」
だいち「痛いぃ…」
平野「だいちくんおしりいいよ」
だいち「やだよぉ…」(泣き出す)
平野「気持ちいいよ~まだやめないよ~」
「あぁだいちくん…こっち向いて」
「ほらこっち向いてほら」
「楽しもうってね、だいちくんに言ったよね?だいちくんは楽しくないのかい?」
だいち「楽しくない…」
平野「お兄さんは楽しいよ」
(また体勢を戻し、だいちのチ○コをしごきながら掘り始める)
平野「あぁ気持ちいい…」
「あぁやらしい音がしてる、あぁやらしい」
だいち「うぅ…なんか出ちゃう」
平野「出していいよ」
「出して…」(しごく手をさらに早める)
(だいち射○)
だいち「なんかお○っ○じゃないのが出た…」
平野「これはね、だいちくんが気持ちいいから出た証拠なんだよ」
「お兄ちゃんも気持ちいい証拠だぞ」
「あぁっ!!」
(平野、だいちに顔○)
だいち「あぁ…うぅ…臭い」
平野「だいちくんのお尻気持ちよくていっぱい出ちゃったよ」
「口開けてごらん。ほら口を開けてほら」
(精○を口に入れる平野、だいちはすぐに吐き出す)
平野「だいちくんは本当に可愛いね、これからももっと楽しいことしようね」
(平野ベッドから降り退出、だいちはベッドで気絶したまま終了)
>>2065
キモてかそもそも私のストーリーよりも変態ストーリーじゃんwwwww「マウント」
>>2067
と言うかそもそも何でそんなんだしているのか知らない現代の人と言うのは変態ストーリーな好きな人が多いのか私は嫌いだぞ
>>2067
言いたいことは分かるよなち○ぽとかお尻の穴とか精○ねっとりキスとか辞めてくれないキモ過ぎるんで普通に無理
>>2071
つまり言いたい事分かる?お前のストーリーよりこっちのストーリーがいいだろ例えばムカデ企業とゴ○ブ○企業がライバルでムカデ企業が変態ストーリーを作り本屋に出してゴ○ブ○企業もストーリーを作るがムカデ企業見たいな変態ストーリーではなく主人公の喜怒哀楽の性格を楽しめるストーリーを本屋に出したらどちらが人気になると思うゴ○ブ○企業のストーリーだろ?つまり3コメと私がストーリーを出し3コメがその変態ストーリーを出してもあまり人気が出ないという事だ「マウント」
板墨様が引っ越してからこれで6ヶ月大阪府豊中市に移動したんだったなこれがジオ基地と言う名前になるとは
>>2079
貴様どこに逃げてたんだクソ22最近いないからお前の警戒レベルが5になったじゃないか
第31話ドローンによる偵察を防げ若き者たちよ前前半
板墨「今回は全員千里中央の所で今日の朝~翌日の朝の5時まで起きていること今回は休憩したいときはいつでもどうぞあと食べたいときはコンビニやヤマダ電機4階にある所で食べてきなさい分かったな」
みんな「分かりました」
板墨「ではこれより全50人による見張りを開始する見張り開始イサミシューン」
その後
沖田「とりあえず私は板墨様と同じ北広場方面今回新たにあのビルと向こうのビルの部屋を買って基地を2つも作る予定でそしてその境界線がちょうどこの千里中央の緑の掴む所と赤の掴む所で分かれているんだよなけれどまずは仕事が優先だ何とかして探さないと」
金森「とりあえず向こう側に行こう」
板墨「沖田こっちだ」
沖田「はい板墨様」
第32話お楽しみに
編集
※奥から2人が来る
野獣「ん~、いい時には結構いくね」
野獣「一ヶ月くらい...(?)」
遠野「ソウデスヨ・・・(?)」
遠野「ヘェ・・・(?)」
野獣「結構楽だったよね」
野獣(野獣邸を指差し)「こ↑こ↓」
遠野「はえ~、すっごい大きい…」
※2人して野獣邸へ入る
ドアくん「ガチャン!ゴン!(迫真)」
野獣「入って、どうぞ!」 (「帰って、どうぞ(門番払い)」の空耳あり)
遠野「あっ、おじゃましまーす」
遠野「家の中だぁ…」
ドアくん「ギィー、ガッタン!」
野獣「†悔い改めて†」(いいよ上がって)
遠野「あっ…すいません」
遠野「本当に大きいっすね~…」
※野獣邸内のソファに座る2人
遠野「今日は本当疲れましたよー…」
野獣「ねー今日練習きつかったねー」
遠野「ふぁい…」
野獣「まぁ大会近いからね、しょうがないね」
遠野「そうなんすよねぇ」
野獣「今日タァイムはどう?」
遠野「いやぁ全然…」
野獣「伸びた?伸びない?」
遠野「あーい…」
野獣「緊張すると力出ないからね」
遠野「そうなんすよね…」
野獣「ちゃんと、ベスト出せるようにね」
遠野「はい…」
野獣「やった方がいいよね」
遠野「はい」
野獣「ウン・・・」
野獣「まずうちさぁ…」
遠野「うん」
野獣「屋上…あんだけど…」
遠野「はえ~」
野獣「焼いてかない?」
遠野「あ~、いいっすね~」
野獣「ウン」
※場面変換して屋上に。2人で競泳パンツ(野獣はSPEEDO社製)に着替える
一般通過バイク「ブロロロロオオオオン…ブロロロロオオオオオン…」
セミ兄貴「ミーン ミーン ミーン ミーン ミーン ミーン ミーン(迫真)」
遠野「見られないすかね…?」
野獣「大丈夫でしょ。ま、多少はね?」
※屋上に寝そべる二人
遠野「暑いっすねー」
野獣「暑いねー。」
野獣「オイル塗ろっか」(滑舌が悪く「オイル・ヌ・ロッカー」と聞こえる)
遠野「ああ…」
野獣「ちょっと、塗ってやるわ」
遠野「あー、ありがとうございます」
※遠野にオイルを塗りながらわざとらしく股間を触る
野獣「硬くなってんぜ?」
遠野「いやそんなことないっすよ…」
野獣「溜まってんなぁオイ」
遠野「先輩だめっすよ…」
※遠野のチ○コがパンツからはみ出る
野獣「どんぐらいやってないの?」(「どう森やりたいの?」の空耳あり)
遠野「もう2ヶ月くらい…」
野獣「2ヶ月…だいぶ溜まってんじゃんアゼルバイジャン」(「危ないじゃん」もしくは「ヤバイじゃん」)
※遠野のチンピク
※否定しつつも反応を見せる遠野の股間を見て野獣の汚いドアップに。野獣の眼光がギラリと光る
※交代し、遠野がオイルを塗る
野獣「あんまり上手いから気持ちよくなってきたよ…」
遠野「フッ(笑顔)」(困惑か苦笑いか、遠野が一瞬微笑む)
野獣(自分の股間を触り)「勃ってきちゃったよ…」
※遠野の手を握って止めさせる
※次のカットで野獣もチ○コをわざとらしくパンツからはみ出す
野獣「スゥー・・・more precious(もうこれ以上やると)気持ち良くなっちゃう、もういいよ。ヤバイヤバイ。」
※しばらく休憩
野獣「喉渇いた…喉渇かない?」
遠野「あー、喉渇きましたね」
野獣「何か飲み物持ってくるよ。」
遠野「はい」
野獣「ちょっと待ってて」
遠野「はい」
※野獣、台所でコップにアイスティーを注ぐ
アイスティー&氷「ジョロロロロロロ…コロッ…」
容器「ドンッ、ゴッ!」
コップ「カッ…」
※さらにアイスティーに睡眠薬らしき白い粉を混入
粉「サッー!(迫真)」
※野獣、アイスティーを持って屋上へ
野獣「おまたせ!」
遠野「あっ」
野獣「アイスティーしかなかったけどいいかな?」
遠野「ハイハイ!」
遠野「いただきまーす」
野獣「ドゾー」
野獣「っしょ…」
※一気にアイスティー(睡眠薬入り)を飲み干す遠野を尻目に再び不気味な笑みを浮かべる野獣(通称「したり顔先輩」)、画面外でも演技を続ける役者の鑑。
遠野「んっ。」
野獣「焼けたかな?ちょっと…」
野獣(自分を見て)「これもうわかんねぇな…お前どう?」
野獣(遠野の焼け具合を見て)「He didn't…he begin…」(いいじゃん。きれいきれいきれい)
野獣「ちょ、これ(まくって)…」
野獣「すっげえ白くなってる。はっきりわかんだね」
野獣(遠野のパンツ跡を指でなぞりながら)「なんかこの辺がちょっとセクシー…エロいッ!」
※空が若干曇ってくる
野獣 「曇ってきたな。そろそろ…中入るか」
※2人とも立ち上がるが、遠野、薬が回ってふらついてしまう
遠野「シシシット…」
野獣(遠野を支えながら)「おっ大丈夫か大丈夫か?」
遠野「大丈夫です…」
野獣「ウシシ…」
※そのまま遠野を支えて室内へ…そして先輩はついに野獣と化す…
※両腕を拘束した遠野をどこかで見た地下室のソファに寝かせ、荒い息をしながら全身を触る
※体を舐め回し始める
野獣「ハァ…ハァ…キシュ!キシュン!キュイッ!(乳首を吸う音)チュパ…チュパ…」
※遠野のパンツに顔を埋め、パンツ越しにチ○コを舐める
※途中で遠野が目を覚ます
遠野「先輩!?何してんすか?!やめてくださいよ本当に!」
野獣「暴れんなよ…暴れんなよ…」
※腹に顔をグリグリ押しつける
遠野「ターミナルさん⁉(田所さん⁉)ちょっと、まずいですよ!」
野獣「いいだろよぉ!、な、ニョロトノ(いいだろ遠野)!」(二人の声が重なって聞き取りづらい)
遠野「やめてください…!」
野獣「な、な、暴れんなって!」
遠野「ちょっ!ちょっ!?」
遠野「うっ、何すか!何するんですか!?」
※暴れる遠野を黙らせるため、薬をハンカチにトントンとマジキチ顔で浸す。スマホをタップするような手つきから「やわらかスマホ」と呼ばれる
遠野「何するん…ちょっとホ↑ントに…ドイツ…!?」
(遠野の腕が何かに当たり『KONG!』と音を立てる)
※遠野の口と鼻にハンカチを押し付ける。
遠野「う、羽毛…」
※まさに野獣のような動きで動きの止まった遠野を舐め回す
野獣「遠野、気持ちいいか?」
遠野「う、うん…」
野獣「気持ちいいだろ?」
遠野「うん…」
野獣「お前のことが好きだったんだよ!(迫真)」
遠野「うっ、んっ!」
※遠野のパンツにハアハア息を掛ける野獣。
※野獣、遠野のパンツを脱がせる。そしてチ○コを熟練の舌使いで責める。
※責められて悶え喘ぐ遠野
野獣(ケツ舐めによがる遠野を見つつ)「いいのかぁ~?」(声が別人のよう)
※直立してパンツを脱ぎ(脱ぎ方が独特である為「ホモステップ」と呼ばれる)、遠野に馬乗りになる
野獣(薬の入った瓶を遠野に近づけて)「これ吸ってみな」(またも声が別人のよう)
※野獣、遠野の口枷を取る。
野獣「オォ~、気持ちいいぜぇ…?」
※ケツ筋を脈動させて腰を繰り出す。
野獣「もっと舌使ってくれよ…」
※いわゆるケツ筋ビートのシーン
野獣「気持ちいいよぉ…」
※カメラが切り替わり、野獣のイ○モ○をしゃぶる遠野のアップに
野獣「自分でも動かしてぇ…」
野獣「アーそれいいよぉ…」
※まんぐり返しの遠野に挿入。挿入時に超小声で野獣が「チョットマッテヨー」と呟きそれに遠野が「ウン」と答えている。はっきり和姦だね
※そして野獣と遠野の喘ぎのハーモニーが響き渡る
野獣「気持ちいいかぁ?」
遠野「キモチイイ…」
※キスする
※掘り続ける
野獣「気持ちいいかァ?」
遠野「ン、キモチイイ、キモチイイ…」
※遠野を横向けにして挿入
野獣「気持ちぃぃ…気持ちいいよぉ…」
※遠野 ON 乗馬マシンのシーン
遠野「アァーハン…アッ…アアッ、アッ…ウッ…(日本レベル)」
野獣「あぁ気持ちいい…気持ちいいよぉ…」
※掘り続ける
※再び正○位で挿入
遠野「アン、アン、アーンン(低音)」
野獣「気持ちいいよォ、気持ちよくなってきた…」
※バックに変わる
野獣「イクワヨ!」
※必死な表情で遠野をバックで掘る(苦行先輩)
遠野「アン!アン!アン!アン!アン!アン!アン!アン!ア、アアーン!(世界レベル)アッ…アッ…」
※そのままピチュン!とゴムを外し、遠野の背中に射○
※騎○位で遠野に跨り、騎○位開始
※途中で突然正○位に移行。遠野の挿入をカエルのように開脚し、涅槃に達したかの如き表情で待ち受ける野獣(通称涅槃先輩)。そして男性○確認できず。
野獣「ああ、気持ちいい…。いいよぉ…ハァ、ハァ、ハァ、ハァ…」
※野獣、そのまま遠野にキスされる
野獣「アアッー、ウァーッ、ア、フュアッ!アァ…ォゥ、ンッ…オォン!アォン! 」
「ハァ、アッ、アッ、アッ、アッ、アッ、アッ、アッ、アッ、アッ、アッ…」
野獣「アァッ!ハァッ!アッ!イキスギィ!イク!イクイクイクイク…アッ……ァ、ンアッー!(野獣の咆哮)アァッ、アッ…アッ…フアッ…ウッ…アアッ…アーッ…アーッ…」(2発目の射○)
※自分のモノを勢いよくシゴいていた野獣に遠野も手伝おうと手を添えるが、野獣は左手で振り払う
遠野「ウン、ウン、ウン、ウン、ウン、ウン、ウン…」
野獣「フッ!フッ!フッ!フッ!フッ、フッ、フッ、フッ…(機関車)」
遠野「ウンッ!ウンッ!ウンッ!…ンッ!、パッソ(イキソ)!…センパ(イ)」
※「パッソ」は野獣の喘ぎ声と被っている為、聞き取りにくい
野獣 「いいよ、来いよ!胸にかけて!胸に!アアッ!」
遠野「ウン!ウン!ウン!」
※遠野、立ち上がってコ○ド○ムを外し投げ捨てる
野獣(遠野、発射開始)「アッー、胸にかけて、アッー!…ファッ⁉」
遠野「ウーン...」
※胸を越えて枕や顔にかかってしまい、若干顔を曇らせる野獣※再び正○位で挿入
遠野「アン、アン、アーンン(低音)」
野獣「気持ちいいよォ、気持ちよくなってきた…」
※バックに変わる
野獣「イクワヨ!」
※必死な表情で遠野をバックで掘る(苦行先輩)
遠野「アン!アン!アン!アン!アン!アン!アン!アン!ア、アアーン!(世界レベル)アッ…アッ…」
※そのままピチュン!とゴムを外し、遠野の背中に射○
※騎○位で遠野に跨り、騎○位開始
>>2088
ほらぁやっぱキモイやん変態ストーリーを辞めろ辞めなければ板墨様に頼んで攻撃してもらおうかな?お前のアカウント
>>2088
このストーリー友達に見せたらこんなコメントがあったで
友達1キモ過ぎてワロタwwwww
友達2頭おかしいのかこいつもうこれせから始まってすで終わるやつだろキモ過ぎワロタ頭大丈夫か?これ女子が見たら何この人的になりそうwwwww
友達3ウワキモ私女子だけどこんな人見たことないわぁ
友達4これどう見ても3コメがどう見ても変態性がありそうだな
私キモ過ぎてマジで無理
友達5無理こういう人マジで無理
友達6せらりあっえるしりあくろりあすこの中から答えてみろ3コメざまあみろバーカ
と言っていますね「私のコメントもありますね」
>>2090
因みにこのストーリーを友達に見せたらこんなコメントがありました
友達1「イキスギィ!」
友達2「イキスギィ!」
友達3「イキスギィ!」
友達4「イキスギィ!」
友達5「イキスギィ!」
友達6「イキスギィ!」
>>2091
じゃあ私のストーリーの評判を言ってやろうか?これ本にしたので130人に見せた結果評判は
⭐⭐⭐⭐⭐最高評判の5に入りましたよあと友達にも見せたらこんなコメントも
友達1面白い面白いやはりこのストーリー面白い続き書いてくれ何度でも読むさ
友達2まるでアルスラ―ン戦記を読んでるみたいで面白かった
友達3このストーリー3コメのクソ変態ストーリーよりも面白い
友達4個のストーリーいいんだよね大超ルーナ東亜東方帝国改に入部したい大超ルーナ東亜東方帝国改万歳
と言ってますね
>>2094
因みに私の友達に貴方のストーリーを見せたらこんな反応が来ました
友達1「ジュッセンパイヤー島の戦いの伝記の方がいい」
あとは同じ
>>2094
じゃあストーリーを作る上でのアドバイスを言ってやる
句読点はしっかり入れろ。文がどこで区切られているかわからない。
あと、テンプレみたいな展開やめろ
>>2096
こっちだってアドバイスを言ってやる
変態系の言葉は辞めろ
ち○ぽとか的〇とか精○とかその他もろもろの言い方は全てダメだ
あと変態ストーリーを作るのを辞めろお前よりは私のがマシだ
新ストーリー
今回新たに新ストーリーを作ることになりましたタイトルは
沈没戦艦魔理沙です
このストーリーの主な人板墨様 沖田万騎長などです
>>2101
作ってんじゃねぇかお前がこのトピに作った迷惑文章とみられる平野とだいちと書いたよな?お前それ以外のトピでやっても同じこと言われるだけだぞバカお前な変態だよこんなの書くなんて
>>2103
平野とだいちを作った人↓
>>2109
MUR「おっ、そうだな。あっ、そうだ。おいKMRァ、お前さっき俺らが着替えてる時チラチラ見てただろ」
KMR「いや、僕見てないですよ」
MUR「嘘つけ絶対見てたゾ」
KMR「何で見る必要なんかあるんですか(正論)」
MUR「そうだよ(便乗)」
2人はラーメンを食べて終了
>>2114
ロケット発射「お手本」
アナウンス「ロケット発射まで残り109876543210」
ニュースの人「h4ロケット6号が今宇宙に向けて発射しました」
みんな「ワーーーー」
みたいなのがお手本
>>2117
まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️
>>2117
まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️に
>>2117
まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️ まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️ まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️ まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️まんぜう軍‼️全軍突撃🫵︎🐮‼️
>>2122
~階段~
ダンダンダンダン!!(開幕クッソうるさい)と階段を駆け上がってくるネゴシックス風の寿司職人
寿「ふぅー腹へったなー」
寿「ひとつくらい…食べてもバレへんか(バカッター)」
めりめりとラップを外し、いなり寿司を取り出し食べる
ピーポーピーポーピーポーピーポーピーポー…(救急車くん迫真の警告)
客先の扉の前に行き、ピンポーンとチャイムを押す。(左隅には観葉植物くん。なぜか枯れている)
~玄関~
関「はーい」
寿「毎度ー土屋(寿司屋)でーす」
関「ごくろうさんはいどうぞどうぞ入って。わぁーありがとありがと。あれ?新人さん?」
寿「はい、まだ淫ら(見習い)なんです」音割れが激しく聞き取りづらい
関「かわいいねーいくつ?」
寿「ジラーチ(18)っす(笑)」
関「18?頑張ってね」
お札を貰う
寿「ちょうどいただきます、ありがとうございまーす」
関「あれ?」
寿「お?どうしました?(煽り)」
関「いなりが入ってないやん!どうしてくれんのこれ(憤怒)」
寿「や、すいません」
関「え…注文通ってないの?あんたんところの店」
寿「いや…そげなことはないですけど」
関「だけどないじゃんいなりが。いなりを食べたかったから注文したの!何でないの?」
寿「僕がさっき食べちゃいました(自白)」
関「食べたぁ?」
寿「すいません」
関「余の(よもや)いなりを食べたの?コロナ禍(この中)の中で?」
寿「はい…」憤りながら携帯を取り出すカーリー
関「親方に電話させてもらうね」
寿「や、それだけは…本当にやめてください」
電話を掛けるのを必死で止めようとする寿司屋
関「お↓い↑なりを食べたんだから電話させてもらうから」
寿「いや…親方だけには…クビになっちゃうんで」
関「関係ないよそんなん、クビになったらええやんいなり食べたんやったら(正論)」
寿「いや、それだけは…本当に勘弁してください」
関「いやもうごめん…もうこれはちょっと…許せんし…」
寿「いや、無理(タメ口)」
関「もういいから」
寿「いや、いや…すいません」
土下座する寿司職人
関「こんなん土下座されたってさー」
関「顔だけ上げて」
関「いなり作ったことあんの?」
寿「や、僕はまだないです」
関「ないのにつまみ食いしたの?」
寿「はい…」
関「ハァ〜…もうこんな…若い子に土下座されたら…」
>>2126
こっちだって忙しん板墨様の命令により北海道で本部にヒグマが本部に来ないように獣医として派遣されたんだよ
第6話第1関門雨
タカシ「行け―sukaiona」
ケンタ「そうはさせないぞ」
雨の音「ザーーーーーーー」
雷の音「ピカゴロゴロゴロ」
オオウチ「しまった雨に濡れてウワーやられた」
ケンタ「ヤバい積乱雲に突入するぞ」
雪「そんな」
海「うそ私のルバⅠがやられちゃうかも」
積乱雲の中「ピカゴロゴロザーーーーーー」
海「ヤバいルバⅠが雷に打たれた落ちていくーお願い翼もうちょい耐えて―」
ルバⅠ「ヒュー――――――――――――ドッポ―ン」
海「そんなぁ」
秋「このままじゃやられちゃう」
第2関門波
雪「ヤバいよ近くの海が荒れてるよ」
タカシ「クソこのままでは一部が波に飲み込まれちゃう」
ケンタ「オイオイオイ波が来たぞー」
タカシ「ヤバいよ一部が波に飲み込まれちゃった」
秋「けどあともうちょっとでゴールだよ」
タカシ「行かないと」
ケンタ「そうはさせないぞこのまま雷に当たるか雨に濡れるか波に飲み込まれろ」
秋「ケンタ貴方の飛行機が」
ケンタ「ゑ雷が翼に当たってそして雨に濡れて波に飲み込まれただと」
ケンタ「絶望だー」
そしてついに
タカシ「ゴール」
雪「ゴール」
ケンタ「勝者タカシと雪ですおめでとうもろこし」
タカシ「変なこと言うな」
第7話お楽しみに
第7話親たちの襲撃
タカシ「でこれからどうしようとりあえずこのジオ千里桃山台を改造して自分たちの家にする?」
子供たち「賛成」
その時
親たちと警察「そこで何をしてるの?」
警察「親たちからは話は全て聞いたお前たちは親たちの腹を刺し病院送りにした後その後親たちが探して見つけたけど親たちに暴行をして暴言を吐いたらしいなお前たちを逮捕する」
タカシ「嘘だ何かの間違いだ」
子供たち「そうだそうだ」
警察「もし降りてこなければ自衛隊を呼ぶぞ」
ケンタ「クソ絶体絶命か」
その時
???「おーい」
ヤンキー少年団達「その声はパラグライダー少年団と改造少年団」
パラグライダー少年団のリーダーマサヒロ「初めまして僕はマサヒロ」
改造少年団のリーダーカイセン「初めまして俺はカイセン」
タカシ「よろしく」
改造少年団「じゃあ早速パラグライダー改造版の素材を持って来たから君たちも手伝って」
警察「降りてこない気か分かった自衛隊呼んでやる」
改造少年団「素材はこれだよ」
素材「プロペラジェットエンジンミニ飛行機エンジンガソリンレバー窓天井ベットチェスト自動操縦レバー椅子ドライブレコーダーフライトレコーダー」
タカシ「僕はこれにしようかな」
タカシが選んだもの「プロペラとジェットエンジンチェストとベットと椅子とレバーと自動操縦レバーとガソリン」
その後「1時間後」
みんな「出来た」
警察「さぁどうする自衛隊が来るまで残り50分だぞ」
タカシ「みんな行くよ大空え」
みんな「おお」
タカシ「みんな行け―」
親たち「警察さんあれを見て」
警察「クソ逃げる気か」
警察「こちら○○警察署の○○そちらから自衛隊機F35を送ってくれ」
電話の相手「いいですよ何機必要ですか?」
警察「4機だ」
電話の相手「かしこまりましたすぐに向かわせます」
第8話お楽しみに
第8話F35戦闘機から逃げろ
タカシ「みんな大丈夫かこのまま行こう」
みんな「おお」
ケンタ「みんなあれを見ろ何かが近づいてくるぞ」
雪「あれはF35戦闘機」
タカシ「そういえばさっき警察が自衛隊呼んだって言ってたよなもしかしてこいつが呼ばれた戦闘機なのか」
秋「みんな逃げて―」
タカシ「こっちに来たエンジン全開」
オミエ「ヤバい撃たれて落ちる―」
ドカーン
海「オミエー」
アイハラ「こっちもやられるウワー」
ヒュー―――ドカ―――――ン」
アゲハ「私もやられちゃうもう終わりかも」
ヒュルルルルルルルルルルドカーン「空中爆破」
タカシ「クソぉ」
雪「みんなあれを見て」
タカシ「あれは幻の空中都市バーレー亭」
ケンタ「嘘だろ」
タカシ「みんなあの中に行こう」
秋「何とか入れましたね」
一方そのころ
自衛隊「F35から逃れたもよう子供たちは空中都市バーレー亭に逃げたことが分かりました今現在ここ日本ではその子供たちを何かを使ってでも軍を動かしてでも捕まえなきゃならない」
第9話をお楽しみに