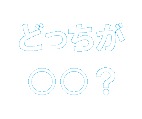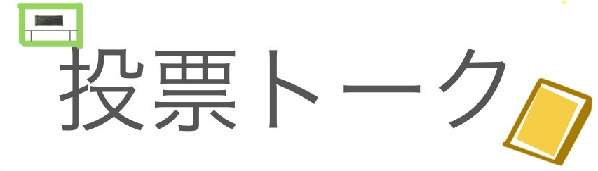世界の多砲塔戦車

今日は世界各国の多砲塔戦車を紹介する。
そもそも多砲塔戦車とはなにか。
多砲塔戦車とは、通常の戦車と違い、砲塔を2個以上取り付けた車両のこと。
利点は攻撃手段が多く、複数の方向に攻撃できるなど。
欠点は砲塔を多くした結果、車長の指揮が増えたり、装甲が足りない、駆動系の問題などいろいろある。
そのため、世界各国で試作まではいったもののほとんどは、採用、量産は全くされていない。
ってなわけで世界の多砲塔戦車を紹介するのだ
日本の多砲塔戦車

[九五式重戦車]
第一次世界大戦で戦車が登場して以降、フランスのルノーで開発されたルノーFT-17軽戦車に代表される車体上に1基の全周旋回砲塔を載せ、武装する革新的な設計が世界中に徐々に浸透していった。
九二式重装甲車もルノーFT-17を参考に造られた。
九五式重戦車は、そんな時代の流れとは異なる形で開発された。
日本独自に初めて開発された試製1号戦車、その改良型である試製九一式重戦車もまた多砲塔戦車であった。
これらは量産されることがなかったが、試製九一式重戦車をベースに、1932年より開発開始、1934年に試作車が完成。
名前の通り、皇紀2595年、西暦1935年に正式化。
見た目は試製1号戦車、試製九一式重戦車とよく似ていたが、装甲面、火力面がパワーアップしていた。
試製1号戦車、試製九一式重戦車は重量や機動性などの面から量産が見送られたのに対し、九五式重戦車は実用に値するとの評価を受け正式化したはずであるが、生産されたのはたった4輌であった。
これは九二式重装甲車の活躍などで陸軍内が機動力に重要性を感じていたタイミングであったことが要因。
その後に機動力のある戦車を多数生産していく方針が定められたこともあり、26tと大きく時速22㎞と機動性のない九五式重戦車の必要性はなくなり、実戦に投入されることはなかった。
車体が大きいがゆえの被弾率の高さ、多武装により機動性や装甲の厚さが損なわれること、大きな車体と武装によりコストがかかることにより多くの国が多砲塔重戦車の運用を見送ってきたが、日本も結局はそれにならう形になった。
採用:1935年
重量:26t
全長:6.47m
全幅:2.7m
全高:2.9m
エンジン:BMW水冷6気筒ガソリン290hp
武装:70㎜砲、37㎜砲、6.5㎜機銃×2
最大速度:22km/h
乗員:5名
ソ連製の多砲塔戦車
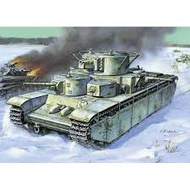
[T-35]
1930年代初頭、世界大恐慌によって各国が軍事費を削減するなか、「第一次五カ年計画」によって恐慌と無縁だったソ連は、多砲塔戦車の開発に着手した。
大型と中型の開発が並行して進められ、中型戦車はT-28となったが、大型戦車は1932年に試作初号機が完成、T-32として少数が生産された。
イギリスのインディペンデント戦車の影響を強く受けており、サスペンションは装甲スカートで覆われ、主砲塔を中心に砲塔は5基が搭載されていた。
76.2㎜砲を搭載した主砲塔を車体の中心に設け、主砲塔の周辺に小型砲塔が4基設置、右前部と左後部の砲塔には37㎜砲が、左前部と右後部の砲塔には7.62㎜機関銃が、それぞれ装備されていた。
T-32の後継車がT-35重戦車で、基本的には同じ仕様だが、エンジン出力を高くし、装甲厚は増大された。
また、装甲スカートの軽量化、弾薬庫の拡大、無線装置の搭載も行われている。
当時のソ連は軽戦車や中戦車が主力だったため、約30輌と生産数は少なかったが、5砲塔型の多砲塔戦車では、史上唯一量産された型である。
その後、副砲塔の37㎜砲が45㎜砲となった他、火炎放射器を搭載した車輌もごく少数あった。
また、後の後期生産型(1938年型)の主砲塔は円錐台形のものが搭載されている。
1941年の6月のドイツ軍侵攻開始時に実戦投入されたが、機動力に劣り、装甲が貧弱で、敵の攻撃を容易に受けやすいなど欠点も多く、多くの車輌が破壊されたり、破損したりした。
このT-35以降、多砲塔の重戦車は時代遅れだという認識が広がり、単砲塔が主力となっていく。
採用:1933年
重量:50t
全長:9.72m
全幅:3.20m
全高:3.43m
エンジン:12気筒ガソリン500hp
武装:76.2㎜砲、45㎜砲、7.62㎜機銃×6
最大速度:28.9㎞/h
乗員:10名
(データは1933年型)
ドイツの多砲塔戦車

[ノイバウフォールツォイク]
第二次世界大戦前、ソ連やフランスは多砲塔戦車を開発した。
ドイツは同じく研究を進め、1934年に試作車を完成させた。
名前の意味は新式車輌。
車体製造はラインメタル社、砲はクルップ社が請け負った。
75㎜戦車砲と37㎜砲各1門を左右に並べる格好で備えていた。
この後、ドイツ戦車は機動力を重視したため、本車は時代遅れになったが、少数生産され、対戦初期のノルウェーやソ連での戦闘に参加した。
だが装甲が薄く、また低速で故障しやすかったため、たちまち撃破された。
残った車輌は、後方でのプロパガンダに使用され、演説台の代わりとしても使われた。
完成:1934年
重量:23.4t
全長:6.6m
全幅:2.19m
全高:2.98m
エンジン:BMW水冷12気筒ガソリン250hp
武装:75㎜砲、37㎜砲、7.92㎜機銃×3
最大速度:30㎞/h
乗員:6名
フランスの多砲塔戦車

[FCM2C重戦車(シャール2C)」
FCM社が誇る、高さ10mにして重さ70tの重突破戦車。
もともとは第一次世界大戦末期の大がかりな作戦に用いられる予定であった。全周旋回砲塔には76㎜カノン砲を装備。
塹壕で困難な走行を容易にした車体側面の履帯で足回りを強化した。
その攻撃力と機動性の両面からの充実は頼もしい。
巨大な戦車の走行を可能にするため、ガソリンによる発電式のエンジンを用い、そこで生み出された電気で駆動するモーターの仕組みが用いられた。
復列式転輪6個を1つの水平バネで支える形式で、片輪24個作動した。
エンジンはそれでも不安があり、ドイツ性の160hp航空機エンジン、250hpエンジン、フランス産の250hpエンジンと紆余曲折を経ている。
武装は車体前部・左右にそれぞれ8㎜重機関銃を1挺、後部には旋回式銃塔に1挺。
155㎜砲に換装され、2C、bisといった後継を生んだ。
ストロボ・スコープ装備にして、多砲塔戦車としてはフランスのみならず世界初であった。
300輌の生産数で華々しく実戦デビューする予定だったが1918年に大戦は終了。
10輌のみの完成にとどまったが、戦時賠償によるメルセデス製6気筒180hpエンジンをドイツから手に入れての完成となった。
第一次世界大戦では活躍は望めなかったが、10輌あったうち8輌が、第二次世界大戦時にはドイツによるフランス侵攻に際し配備されることになった。
しかし鉄道での輸送時にドイツ軍からの攻撃に遭遇、乗員が先手を打って処分、破壊された状態でドイツ軍に捕獲された。
またしても活躍の機会を失ったのだ。
採用:1918年
重量:70t
全長:10.27 m
全幅:2.95m
全高:4.01m
エンジン:メルセデス水冷6気筒ガソリン×2
武装:75㎜砲、8㎜機銃×4
最大速度:12㎞/h
乗員:12名
おわり
このトピックは、名前 @IDを設定してる人のみコメントできます → 設定する(かんたんです)