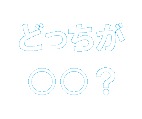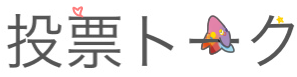日本語と英語はどっちがすぐれている?
>>121
表現の多彩さが英語にはあって、日本語には無いって言ってなかった?矛盾が凄い。
ついでに言うと、"put on" を「身につける」と意訳すれば、言い回しとしては一緒。
>>640
日常生活で「帽子身につけた?」「寒いから靴下身につけなさいよ」とか言わないな。
>>99
そもそも物数えるときに数詞を直接名詞につけられないのがすさまじく意味不明。「ウサギは1羽2羽」「イカは1ぱい2はい」とかバカかよ。
>>106
sをつける意味がわからん。doはsつけられるのにcanはsつけられないとかマジで何したいの?最初っからsつけんな。複数形の方のsも数をもう言ってるんだからわざわざつける必要ない。紙は数えられないけどレポートは数えられるとかそんな無駄なことをして他の人が覚えにくいくそ言語を崇めるとかwwさらには不規則動詞というくそシステム、こればかりはほんとに意味不明。
>>111
「複数形の方のsも数をもう言ってるんだからわざわざつける必要ない。」それが気になるならトルコ語やれよ。
>>106
君が知らないだけでちゃんと由来と意味はあるし、言語機能としての役割もあるからね。
>>511
だれも具体的なら正論だなどと言っていない。
主張には具体例が不可欠なだけ。
具体例がない主張は形而上学かなw
>>694
具体例具体例と言いながら、中身の無いスカスカのハリボテ理論を振り翳して、自分が賢いと勘違いして思い上がるよりマシ。
何年何月何日何時何分何秒地球が何回まわった時ー?!!
こ ど も か !!
>>750
何年何月何日何時何分何秒地球が何回まわった時ー?!!
突然なにを言っているのだろうこの人は。
>>767
具体例に拘り過ぎて、言動が小学生の中身の無い屁理屈と変わらない、という指摘。
やっぱり読解力というか汲み取り能力と言うか、コミュニケーション能力に乏しいのを、言語の所為にしてる人間が多いな。
僕が悪いんじゃないモン!!この言語がおかしいんだモン!!ってか?アホか。
>>694
じゃあ、具体例を出しているにもかかわらず、内容がスカスカで形而上学化してる英語派の主張は、そもそも論外って事か。
>>99
世界的に見て動詞が主語の人称と数で変化するほうがむしろ普通の言語だよ。インドヨーロッパ語族はほぼすべて。セム語,フィンランド語,バスク語,トルコご,スワヒリ語,アイヌ語も動詞が変化する。おまえはそれらすべてに「すさまじく意味不明」ってケンカ売るのか?
>>736
その返しが既に、正しく屁理屈を指摘された、子供そのまま。
反論出来ないから~、と本気で思っているのは、勘違いして思い上がっている子どもか、大人に成りきれない未熟者、考え足らずのおバカさんだけ。
まぁ、確かに大人気ない人間が、誤用しないとも限らないが、少数派。
ついでに言うと、言い回しや表現は違っても、世界中 割とどこでも通用する価値観なので、日本語だけの決まり文句でもない。
モノを知らずに知ったかぶると、却って恥をかく。
>>751
じゃあ「屁理屈言うな」を他のいくつかの言語で例示してみて。日本語の直訳じゃだめだ。その言語で高頻度で使われるやつな。
できなければ君が言ってる「価値観」はただの妄想。
>>752
筋も通りも無い無茶苦茶な決め付け理論、正に屁理屈だな。
君の屁理屈こそが妄想だろ。周りの無関係な第三者に聞いてごらん。
>>103
じゃあこれ見てみろ。
「アインシュタインの物理学を革新しようとする試み」
普通の日本語だよね。だれでも書きそうな。でもこれ
①[アインシュタインの[物理学を革新しようとする]試み] ②[[アインシュタインの物理学」を革新しようとする試み]なのか構造的にあいまい。名詞の前にすべての修飾語を並べないといけない日本語は,それが原因でこういうことが起きやすい。
英語はというと
①Einstein's attempt to revolutionize physics
②An attempt to revolutionize Einstein's physics
名詞の前後に修飾語が配置されるおかげで非常に明晰だ。
>>437
その通り。日本語では上の様な場合、文脈から読み解くしかないので、気になるならキッチリ相手の話を最初から最後まで聞くか、文章を読み込んでよく理解する必要がある。
で、日本人が文化的・社会的にワザとその様に言語を発達させて来た、と考えた事は?
情報伝達上 不便であること以上の利点や長所があるとは、まあ普通は考えないし気付かないかな。
曖昧さには社会の中に自然に溶け込んでいる、無意識の言語的習慣の側面があると思っている。
>>641
それって偉いことなの?
ひとことで言うとガラパゴス言語じゃん。
言語学的にいうとhigh-context「文脈依存性」言語。
これは婉曲表現だね。
露骨にいえば言語だけでコミュニケーションがちゃんと成立しないだめ言語。
ちなみに猿の鳴き声は文脈依存性めちゃ高いよね。
>>690
偉いも何も……。真っ先に突っ込むところがソレという事は、191にとって一番重要なのは、結局ソコなわけか。逆説的に191の短慮が丸見えだが、それはいいのか?
ガラパゴス言語とか、僻みの負け惜しみにしか見えないんだが。
依存性も何も、文脈が汲み取れない自慢をされましても…。
日本語、英語に限らず、相手の言葉使いや会話の文脈汲み取り能力で、為人や知識・教養・実力を図るのは、全世界共通だし、どんな言語圏でも上に上がれば上がるほど、その辺の基準は厳しくなる一方なんだが。
英語だとワザワザ文脈を汲まなくてもいいとか、簡易化するとか、無いぞ?
何を勘違いした事を言っているんだ?
知識・教養の足り無い、読み書きも十分に出来ないのが大半以上を占める下層階流の認識を、他言語圏全体の常識だと思ってる?
言葉知らずの物知らず、知識も教養も無く文脈も読めない様なヤツ、情報を鵜呑みにしたり、辞書丸覚えみたいな事しか出来ないヤツは、考え足らずのモノ知らず出来ない扱いを受けて弾かれるし、その辺は日本より他言語圏のがよっぽど厳しいんだが?
何より、言葉を話す人間自身の基礎教養や知識・知性を土台にしたコミュニケーション能力の高低は、言語を変えたトコロで誤魔化せないし、隠せないぞ。
>>695
何だろう、この敗北宣言決め付けが好きな人々。
日本語がそこそこ出来ても、本気で日本語能力と言うか、読解力が物凄く低いんだな。勘違いが酷過ぎ。
ここまで他者の意見を汲み取る事が出来ないって、コミュニケーション能力に問題あり過ぎじゃない?
>>696
いや、日本語が日本でしか価値を持たないのは当然では?まさか英語が英語圏以外でも価値を持つと思ってる?
>>733
英語はほぼ世界中で価値を持っているだろう?
航空機の通信が世界中どこでもほぼすべて英語なのは知らないのかな?
>>696
日本以外の世界で価値を持つ必要性が解らない。
何時の間に世界云々に話がズレてるの?
ああ、世界に認められる方が言語的に優秀って?
単純に多数決で決めるなら、最初から言語的優劣論自体に意味が無いよね。バカなの?
>>850
そのとおりだね。日本語は日本でしか価値を持たない。
つまり世界において価値が低い。
>>641
おまえ全然言語を論じないで文化とか社会とかばっかり。言語自体を論じる能力ゼロなのがよくわかる。
それ別にトピック作ってやれよ。
>>698
いや、自分の読解能力と理解力の無さを棚上げして、何言ってるの?
自分こそ知ったかぶって、全然見当違いの事 言ってる自覚ある?
僻み妬み嫉み?
>>698
其方こそ全く言語の意義や成り立ち・構造etc.を、理解していない短絡思考が丸解り。基本や背景を無視して言語自体を論じられると思っている辺り、考え足らずの素人同然なのが良く解る。
頭でっかちの詰め込み情報を知識と同一視するなよ。
>>641
「情報伝達上 不便であること以上の利点や長所がある」
ではその利点を具体的に教えてください。
>>103
日本語は名詞のあとに修飾語を置けないから
「頭が赤い魚を食べる猫」なんていうひどいあいまい性が生まれるんだろう?
>>110
じゃおまえどんな英語でも日本語に訳せるのかな。
Be the good girl you always have to be.訳してみ。
>>110
日本語が繊細だと感じるのは、あなたが日本語を母語としており、表現の細かいニュアンスまで感じ取れるからでは?
英語を母語とする人は、あなたが日本語に対して感じているように、英語が繊細だと感じているのでは?
am,are,isの必要性とか不規則動詞やsの必要性みたいな核心には反論してこない英語信者
>>113
そんな自明のことに答えるひま人がいないからだよ。
しかたないから答えてあげよう。
be動詞の人称変化があるから主語と動詞がたとえ離れていても主語が何か分かるんだよ。それからいくつもの名詞を含む複雑な名詞句に関係節がついたとき,isとareの区別のおかげで先行詞がどの名詞かわかることがしょっちゅうあるだろ?それから三単現のsがなかったらHe put off the meeting.が過去でhe puts off the meeting.が現在だってわかんないだろ?
まあ英語に縁のないおまえにはなに言ってるか分かんないだろうな。
>>115
あ、ごめん。全部わかる。じゃあputには過去形がないんだよね。まずその時点でおかしいよね。putの過去形を作ってsをなくせばいいんじゃない?
>>123
過去形がないんじゃなくてputが過去形なの。
おまえそんなことになんくせつけてるひまあったら日本語の活用のほうをなんとかしろ。「行った」と「行った」を表記上区別できない問題,「くる(来る)」→「きた」,「きる(着る)」→「きた」,「よう(酔う)」→「よった」,「よる(寄る)」→「よった」,「いる(要る)」→「いった」,「いく(行く)」→「いった」,「かう(買う,飼う)」→「かった」,「かる(狩る,刈る,駆る)」→「かった」を音声的に区別できない問題をなんとかしなさい。
>>126
車がきた
服をきた
酒でよった
そこまで来たからよった
要った?
略さなければ良いのではないかと思います
>>439
ARSってなんですか?まさかArs longa, vita brevis. のArs?
>>126
活用変化は他言語と同じで、基本は慣れです。割とどんな言語にもあるその言語特有の法則の一つなだけで、日本語が殊更特殊な訳でもありません。日本語は単語単体よりも文脈と行間から、書き出された文章以上の意味を読み解きます。また活用はこれに伴う変化が基本になるので、自己主張最優先で他者への配慮や、周囲との協和、空気を読む事が苦手な他言語圏の人や、英語表現を至上とする英語派の方には、活用変化を利用した言語的表現の理解が難しいのかもしれません。
さらに他言語を話せない日本人にとっては、英語の発音を聞き分けてついて行くのも、発声するのも容易ではありませんし、良くネイティブ・スピーカーに妙な発音を笑われますから、これは多分お互い様でしょう。
>>126
会話や文章は基本的には、単語一つで成立しないので。
それこそどうしてもの必要の無い区別ですね。
音声区分に拘ると言うのはそれだけ文盲率が高く、知的水準や民度の低い社会背景が在っての事。読み書きが十分にできない事が前提の社会における、言語的特徴の一つとも考えられる。
会話や文章から文意を汲み取るだけの精神的余裕や知性・教養も、周囲を慮る道徳性や社会性も、文章を読み解く為に必要な物理的環境も、その言語を育んだ社会の中で、一般的には存在していない証左に他ならないと思う。
そもそも情報量の多さとか言う前に音と文字が完全に一致しないのっておかしいよね。日本語は聞いたまま書けばいいけどわからない単語が出てきたら書けないのが英語というくそ言語。誰かが日本語は先進国の言語じゃないっていってたけど、よく考えたら英語の方がまじのくそ言語だったわ。knowとかnightとか覚えさせる気ないでしょ。不規則動詞とか作った奴イカれてる。
>>114
それ全部かなで書いたらという非現実的な仮定をした場合だろう?実際は漢字がわからないと聞いても書けないよね。
英語の不規則動詞程度でいかれてるってへたれかよ。おまえ英語以外の言語やったことないのか?
>>133
英語,ドイツ語,フランス語,中国語,スペイン語,イタリア語,国語学,英語学,言語学。博士課程修了です。
あなたは?
>>135
私は勘違い高校生だよ。
見当外れかもしれないけど質問するね。個人的な質問もあるよ。
①言語って結局どういうものなの?
②我々にとって他意を含ませることはよくないの?(これは人道的にも、学問的についても)
③あなたと私が対面したとして、優れた言語において、私はあなたを了解することが可能なの?
③優劣があるなかで、確かに減ってはいるけれど、多くの言語が未だ残っているのはなんでだと思う?
こっからはかなり個人的なものだけど、
④我々の存在は言語抜きで成り立ちうる?(言語が消滅したとき、少なくとも人間にとって、この世界は消滅してしまう気がする)
⑤博士課程は言語学?専攻は?(高校生だからよくわからない)
⑥大学でどんな人と関わってきたの?尊敬する教授とかいる?
⑦どうしてここには日本語を支持する人が多いと思う?
⑧どうしてあなたはずっとここにいるの?誰かを啓蒙するため?自分のため?
⑨これは⑦の焼き直しになるけど、結局このトピックが生み出すものはなんだろう?
⑩私はあなたにとってのテクストになれるの?
⑪大学受験のアドバイスを。
>>136
①A意味(概念)と物理的媒体(有限の音素や文字の連鎖=形態素(morpheme))の恣意的な結合。人類の言語の場合はAが文法規則によってさらに結合して高次の構造(句や文やパラグラフ)を生みだし(階層的構造),さらに複雑な意味と結合できる柔軟性を持っている。地球上で言語に最も似ている物は遺伝子だと思われる。有限の音素→単語→句→文→パラグラフ→スピーチ,小説,論文,etc. 4つの有限の塩基→コドン→アミノ酸→タンパク質→細胞→組織→器官→個体
②質問の意味がわかりません。私が英語を話してあなたがそれを理解するという意味ですか?そうであればあなたの理解力しだいでしょう。
③言語は,民族とおなじく,それ自体の優劣だけで生き残るわけではなく,ジャレッドダイアモンドの主張のように歴史的偶然に左右されるでしょう。
④言語は人類の種としての特性の一部で,本能的なものです(Steven Pinkerなど参照)。だから言語が消滅するということは人類が人類でなくなるということに等しいでしょう。
⑤英語学,対照言語学。
⑥池上嘉彦,Mark Johnson, 森山卓郎,山梨正明,etc。
⑦日本語以外の言語をあまりよく知らない人が多いからでしょう。
⑧ずっとここにはいません。私は今本を書いていてとても忙しいので。
⑨日本語の欠陥を客観視できる人が多くなれば,日本語の向上につながるかもしれないというかすかな希望でしょうか。
⑩すべての人のことばは,別のだれかにとってテクストになりえると思います。
⑪本当に興味があることはなにか考える→それを学べる大学と学部を見つける。
そうすれば勉強のmotivationが生まれます。これをおろそかにしてなんとなく受験勉強をやっている人が多いのではないでしょうか。それでは自分のpotentialを最大限に生かすことはむずかしいでしょう。「自分の偏差値で入れるところは…」とかいう考え方には疑問があります。
時間的制約で,これ以上のコメントはしばらくできません。
Good luck with your study!
>>138
ありがとう❗
ゆっくり咀嚼したいと思う。
私は全く未熟な者だけど、あなたは或いは優れた人なのかな?と思うよ。
でも、ここでの論争は結局のところナショナリズムを煽るだけな気がするよ。
あなたはここでは日本語派を啓蒙したいように見受けられるけど、むしろあなたの希望は遠ざかってしまいすらしそう(個人的な意見だけどね)。もちろん私みたいに考えが変わりつつある人もいるけど、一民族の重要で本質にも関わる(ていうか、本質?)言語を真っ向から否定されると、その文化そのものを否定されたと思う人もたくさんいるだろうからね。そうなると真実に盲目になって、感情的に反抗する。大半の人もそうなんじゃないかな。とりわけ、日本人は事実を二の舞に、努力とか真面目とかを無条件に評価する人が多いし(こういう発言は少し引っ掛かるけどね。私は世界の人も日本人でさえもよくわかってないかもしれないから)。
結局何が言いたいかっていうと、あなたはその目的から遠ざかっているかもしれないし、それどころか、真実に盲目な人をより誤った道へ導いてさえいるんじゃないかなってこと。もう一度言うけど、個人的意見だからね。
そういう人としぶとく付き合って、真実をねじ込むっていう目論見なら、何も言えないけど。
後、私の考えとか質問とかを言うね。答えるのは来年でも四半世紀後でもいいよ(笑)
仮に、動物の思考も言語に準ずるものでできているとするよ。そうすると、その言語やそれに包含しうるすべてのものが消滅したら、つまり生き物らしきものがすべて消えてしまったら、この世界もまた消滅しちゃうんじゃないかなって少し考えたりもするんだ。だって、この世界を分節しうるのは一重に言語だけなんでしょ(実際は浅学だから、よくわかってないんだけど)。差異がなくなった時、つまり認識するものがなくなったとき、世界は無いんじゃないかな。或いは有無以前のものなんじゃないかって時々考える。
逆に世界が消滅しえないなら生物らしきものもまた決して消滅しないんじゃないとも考えたり(これは世界が生物によって生かされる前提上だからメチャクチャだけど…)。でもこれはデカルト的な考えになってしまうんだけど。
>>139
ちょっと思ったこと話すね。
例えば日本語は、助詞一つでかなり意味が変わるよね。
だるまさんは転んだ←客観的な事実報告っぽい
だるまさんが転んだ←だるまさんの意志がみえる(まあ文脈にもよっちゃうけど)
こういう助詞のイメージの違いが短歌や俳句を成り立たせてるんじゃないかな。
「机のに向かいながらスマホいじる」のと「ベットにねっころがってスマホいじる」のとによって母親にあたえる印象がビミョーに違うみたいに(笑)
後、情報量が少ないっていってたけど、一定量に集約される意味の量が多い方が良いのかな。確かに時間がかかったり、展開に支障をきたしたりするかもだけど(表現の不統一による支障とかもね)、例えばそこにかけた時間が果たして無意味なのかな?例えば、バスをぼーっと待つ時間と、本を読んで待つ時間とに価値の差はあるのかな?
どこか近代的な時間の絶対性を感じるんだよね、端々に。あるいはオリエンタリズム的なものを。
適当にのべてきたけど、恐ろしいことに私は全くこうは思わないんだよね。時間は有効に使うべきだと思うし、検索だって表現の統一があった方がいいもんね。まあ、科学の記述には統一があるけど。ただ、一つ思ったのは、あなたの主張って或いは普遍性を持ち得ないのかなって。私はまだまだ未熟だから、井戸の中からの意見だけどね。大学にいったら大海を知れるのかな。
>>116
程度とかそういう問題じゃないよね。まず英語は音と表記が一致しないことを認めろよ。これ重要な問題だから
>>114
文字と音は一致していてほしいのは同意。まあ古の国際共通語な漢字がある時点で、実際には微妙に変則的だけど、一緒の方が解りやすくて便利。
>>131
①表現力:複雑な思考や抽象的概念を明晰かつ分析的にあらわせる。
②能率:同じ音節数で比較してより多くの情報を伝達できる。
③非あいまい性:A:語彙レベルのあいまい性:同音異義語、同形異音語、異表記(同じ語の表記がいくつもある)が少ない。B:構造(シンタックス)レベルのあいまい性が少ない。Bに関しては「日本語が欠陥言語だとわかる画像」を検索してください。
④学習の容易さ:文法や発音や表記法が外国人にとって学習しやすい。これは学習者の母語によっても変わるので相対的である。
なぜこれらが「すぐれる」の条件かといえば、少なくとも①③④はエスペラントなどの人工言語が作られる際には必ず考慮されることだから。
日本語は本来英語よりも優れていたが、今の日本語は変に略されて英語以下である事は間違いないでしょう
話された言葉を文字にしても感情が伝わる。小説やマンガを書くのだったら日本語の方が間違いなくいい。英語は言わなくてもいいことをいちいち言ってるのに対して、日本語はいい感じに省略できる。情報量が多いことが優れているとは限らない。パターンが多いことが悪いこととは限らない。
>>150
背景知識を共有するコミュニティーの中では「いい感じ」に省略しても通用するでしょう。でもだれにでも明確に情報を伝えるには「言わなくてもいいこと」を明示する必要がある。
>>164
日本語への理解が不十分で、上手く扱えない不得手を、日本語の所為にしているだけに見える。
>>151
そして争いと諍いが絶えず、個人は自己中心的で攻撃的、強者が弱者を喰い物にし、社会は常に不安定で民度は低く、凶悪な犯罪が横行し、ごく一部の富裕者と大多数の貧民で成り立つ、不均衡で不健全な社会が、大陸では当然な訳だが。必要の必然性により、優れている言語が世界を席巻して相互の意思疎通を助け、社会的集団の基礎と成っているハズなのに、この現実は何だ?
>>442
言語の話してるのよ。
頭だいじょうぶですか?
大陸ってどこ?
「必要の必然性」ってなに?
「優れている言語」って日本語を暗に指してるの?
日本語を世界に広げたいならまず正書法と明確な節構造とあいまい性が少ない修飾構造と整然とした人称代名詞と指示代名詞のシステムを構築するべきでしょうね。
無理だと思うけど。
>>472
大丈夫。言語の意義に関わる話をしています。
そして別に誰も、日本語を世界に広げたいとは言っていないけど…。よっぽど日本語を使う事に対する、劣等感でも常日頃から感じているのかな…。
確かに、繰り返されるコメントを見ると、一見論理的な事を述べている様に見えて、その実、日本語を読み解く能力が低目というか、意図を汲み取るのが難しいみたいに見える。
理解しようとして読んでいる、というよりも、理解する気が無いのか、理解したくないのか、理解出来ないのか。まあ、決して解り易く書いてはいないので仕方ないけども。
でも、どんなに優れた言語が開発されたところで、自らの未熟や無知を悟ろうとせず、端から自身に都合の良い意見にしか耳を貸す気が無い、利の無い他者と意思疎通を図る気の無い人には、全てが無意味だろうな。
言葉って、本当に何の為に在るんだろうね。
音と表記が一致しない英語っておかしいよね?みんな、これについて議論しようよ。英語って本当にくそだね。
>>158
熟字訓て知ってるよね?
英語をくそというなら熟字訓廃止してからね。
聖林 木耳 歩行虫
五月蝿い大口魚。
正書法も確立していない言語は現代の言語として問題外。
しめきり,締め切り,締切,締めきり,締切り,締め切,〆切 何とかしろよこれ。
>>162
フランス人に日本語の書き方教えようとしたけど,こういうのが出てきたとき「どれが正しいんだ?」ときかれて「どれでもいいんだ」って言ったら"Quoi?? N'importe quoi? "って驚愕されて笑われた。「今まで中国語を含め5つくらい言語を勉強したけど,そんな言語ない」って。
>>166
「固有性」ってなにがなにの固有性なの?
正書法がないというのは,言語の固有性などではなく,言語を共有のツールとして使いやすくするための規格化・標準化をおこたってきた結果にすぎない。
たとえるなら,太平洋戦争時の日本みたいに,ねじとか兵器や機械の部品の規格化もちゃんとできてないようなレベルだ。
>>162
表現の多様性なだけ。
本来はTPOに応じた正しい使い分けの厳密な決まりがあったが、家庭での躾や教育の質が低下し、時代の流れと共に、現在その方法論が急激に失われつつあるだけ。
特に30代以下の若い世代の、好き勝手な日本語乱用による言語崩壊ぶりはヒドイ。
そして社会が自浄作用を失っているので、誰もそれを是正しないだけ。
>>444
じゃあ締め切りのどの異表記がどのように厳密に使い分けられていたのか教えてください。
>>162
何でも明文法で縛ろうとするのは、民度の低い大陸社会の欠点であり常識。
ただ真似れば良いとは思わない。
>>445
「民度の低い大陸社会」こういういわゆる「ネトウヨ」が使うような言い回ししてる時点でだめですね。レベル低すぎますわ。
英語は26文字しか覚えなくとも構わない。無論、その極少数の文字を組み合わせ単語とし、それらを覚える必要性はあるがね。片や日本語は『ひらがな』の時点で記憶すべき文字は上回り『カタカナ』の他、漢字は常用漢字だけで小6までに1000を超える。まぁ覚えてねぇ阿呆もいるだろうけど、200は覚えるだろうさ。んで一応アルファベットも覚えさせられる。英語圏の奴等は『ひらがな』覚えるかい? そんなこんなで日本語を駆使する方が上なのは明白。世界の共通語だかなんだか知らんが、単一の母国語があるって事に誇りを持つべき。
>>169
「そんなこんなで日本語を駆使する方が上なのは明白。」そこまでわかっててなんでそんなあほな結論になる?
わずらわしい言語を使ってるから「上」なのか?
簡単な表記の言語で高度な内容を表現できるほうが「上」とは思わないのか?
>>170
簡単な言語で表現できる幼児の方が、複雑でより難しい言語表現をする大人よりも「上」と思うのか?
短絡的な思考でアホな結論を振り翳しているのは、どっちだ?
>>667
170は「簡単な表記の言語で高度な内容を表現できるほうが「上」とは思わないのか?」と言っている。
>>169
「英語は26文字しか覚えなくとも構わない」
日本語がすぐれていると言う人の日本語がいきなり不自然で笑える。
>>207
ずっと読んできたけど、日本語がすぐれていると言う人のコメントは変な日本語だらけだね。
>>171
日本語にも緊急時の短縮話法は存在する。
現実に英語には日本語の「危ない!!」に相当する単語自体や近似値の意訳はあっても、直訳でその儘通じる言語的言い回しは存在していなかったと思う。
日本語はだめだなと思わせる分の例(Wikipediaから)
南方熊楠は、周密などの書いた中国の文献に登場する「押不蘆」なる植物が、麻酔の効果らしき描写、犬によって抜くなどマンドレイクと類似している点、ペルシャ語ではマンドレイクを指して「ヤブルー」と言っているまた、パレスチナ辺で「ヤブローチャク」と言っている点から、これは恐らく宋代末期から漢代初期にかけての期間に、アラビア半島から伝播したマンドラゴラに関する記述であると指摘し[5]、雑誌『ネイチャー』に、その自生地がメディナであると想定した文を発表[6]した。
主語「南方熊楠」に対する動詞「指摘し」が読んでも読んでもなかなか出てこないのでわかりにくいことこの上ない。SVO言語ならこんなことにならない。日本語って複雑な内容を表現するには向いていない。
別に優れているから英語が世界で使われてる訳ではない
イギリスが世界制覇ぶちかまして植民地作りまくってメシウマした結果
更にアメリカが太平洋覇権を握りメシウマした結果でしかない
もっと前に遡ればキリスト教が流布→戦争植民を繰り返し世界を席巻した結果とも言える
フランスが世界制覇してればフランス語が軸となった世界があっただろう
言語的には英語は単刀直入すぎて日本人には合わないだろう
このコメ欄が良い例、憤慨してるじゃん
言われなくとも察っする文化なんだよ
これを日本人に聞く時点で悪意しか感じない
>>179
「英語は単刀直入すぎて日本人には合わないだろう」
もうこれだけで英語をしらんやつのコメントだとまるわかりだな。「英語はYes Noがはっきりしてる(笑)。」
いやー、日本語はいいよねー。漢字その物に意味が付いてるし、ひらがな50個覚えれば単語覚えなくったって、聞いたものを書けるんだもん。
日本語と英語だけを比べて主観的な議論をしてもあまり意味がない。
科学的な手順に従った定量的分析を見てみよう。
(以下引用)
単位時間における日本語の情報密度は英語の68%しかない
言語間における情報密度の違いついては、定量的な分析が存在しています。フランスのリヨン大学の研究チームが2011年に発表した「複数の言語におけるスピーチ情報密度の違い」(原題"A cross-language perspective on speech information rate")で、英語の全文がこちらで読めます。また、日本語でも分かりやすくまとめた記事がこちらにあります。この研究によれば、単位時間内に伝達できる情報量は、ベトナム語を1とした場合、以下のような差が生じます。
ベトナム語:1
英語:1.08
フランス語:0.99
スペイン語:0.98
イタリア語:0.96
北京語:0.94
ドイツ語:0.90
日本語:0.74
比較されている8言語の中では、情報密度において英語が頭ひとつ抜けているものの、他の言語では大きな差はなく、日本語だけが大幅に低いことが明らかになっています。日本語(0.74)は、英語(1.08)と比較して情報密度が68%しかない言語なのです。
>>182
あくまで一学説であり、以上でも以下でもないし、それが全てでも、正解でも、結論でもないんだがな。意図的な誤誘導は止めようよ、見苦しい。
We had to buy a pen.(6音節)
Watashitachi wa ippon no pen o kawanakerebanaranakatta.(22音節)
>>183
We had to buy a pen. (原文)
我ら 持った 為 買う お ペン 。(直訳)
私達は一本のペンを買わなければならなかった。(意訳)
>>184
きみは英語の文学作品をどれくらい原文で読んだの?
英語は形容詞と副詞の数が日本語よりはるかに多く,助動詞や叙想法[仮定法]が発達していて非常に微妙な命題態度を表現できる。感情を表す語彙や比喩表現もものすごく豊かだ。間接話法と直接話法が完全に分離して使い分けられている。システムとしての精巧さがまるで違う。
日本語のほうが勝ってるのは敬語とオノマトペの数くらい。でもオノマトペはレベルの高い文学にはそんなに使えない。
>>184
じゃあどこが具体的に優れているかいくつかあげてみてください。
できなければただの感情的コメントとみなす。
>>186
ホント、この具体例を上げろ!のどうしようもない感じ。
揚げ足取って屁理屈を捏ねたがる子供みたいに見える。
>>200
賞をいっぱい取れば言語的に優秀なの?あくまで一指標に過ぎないと思うんだが。
大体ノーベル賞自体が他言語圏の賞だし、選定基準に未だに人種差別的傾向があるって、巷で言われてるくらいなのに?
「氷が解けると何になる?」「春」
このなぞなぞが成立するのは日本語が構造的にゆるいからだな。
数を言うのが長い 千とか百とか億とか2音で言えるのに
129 ひゃくにじゅうきゅう ワンハンドレッドアンドトゥエンティーナイン 一目瞭然
>>201
日本語は情けないくらい音素の数が少ない。二重母音と長母音の区別もできない。
結果同音語だらけ。riteもlightもwriteも「ライト」。lawもlowもrawもroeもrowも「ロー」。「しこう」って言われても意味わからない。
>>204
音素がまずしくも音調もないのに文字見ればわかるからと大量の漢語を取り込んだ結果耳で聞いても区別できない単語が大増殖。
>>212
そして同音語を書き分けられずにこけまくり。
いまネットで「三密」がだめっていわれてるよね。
「三蜜」検索してみ。学校とかお役所が出してる文書に「三蜜を避けて」がいっぱい。なにそれ?甘いよ小沢さん。
「消化器をまきちらしてしまった」なにそれこわいスプラッター?
「昨日、消防団をしているメガネ屋さんとお話しをする機会がありまして
「私、病院での研修生時代に実際の硝子体(しょうしたい)を見た事があるで~」
と言ったところ、たいそう引かれてしまいました。
よくよく話を聞いてみると硝子体と焼死体を聞き間違えていた様です。」 なにそれ怖い。
劣等言語の具体例のほんの一部でした。
>>216
音素の少なさによって生まれたぼう大な同音異義語のせいで
日本語は表音文字化できないで非能率のままだ。
ベトナムも朝鮮もとっくに表音文字化した。
朝鮮語のハングルは同音語が多いとバカにしている無知なバカが多いが,朝鮮語はハングルでもやっていけるのだ。そのわけは「なぜ日本は漢字を廃止しないのですか? - Quora jp.quora.com」を画像検索して出てくる同音異義語の比較表を見ればわかる。朝鮮語は日本語より音素がはるかに多いのだ。
表音文字化していないのは中国語と日本語だけ。
中国語は漢字の元祖だからまあいい。
それに中国語はやろうと思えば表音文字にできる。
中国語やった人はローマ字表記の中国語知ってるよね?
>>219
だから非能率は飛躍しすぎ。
それに、本題には関係ないのにチラチラ、無理に絡めてくる半島推しの人が混ざっているのは、なんで?
>>219
表音文字が表意文字より能率的という論拠に成っていないし、そもそも表音文字自体が表意文字の描き崩しから派生した事実は無視か。
>>212
ぼくの知りあいが「さいきんちょっとじむやってる」っていうから「ジム」かと思ったら「事務」のバイトだった。
>>302
聞き取り間違いやすいと言うのはよく解る。
しかし、この一文だけで会話が成り立つワケで無し、この前後にも何らかのやり取りや、会話があったはずでは?
であるならば、会話の流れや文脈から相手の言いたかったことを的確に読み取れなかった、302コメさんの日本語能力があまり高くないか、相手の話を流してロクに聞いていなかった可能性は?
それともラインか何かの突発的なつぶやき?それなら汲み取れなくても仕方ない。
>>212
書き文字で区別出来ないのはいいのか?
なお、日本語は文脈から大意を読み取るので、複雑な音素・音調を失ったとの事。過去には、お隣の中国に倣ったのか、母音だけでも5~6は発音の違いがあったそうな。
祖父曰く、少なくとも大正時代までは、はっきりとした「い」「う」「え」の読み違いが各2,3種は残っていたという。言われても、聞き取りだけで発音が出来なくて叱られて泣いた覚えと、周囲の年配者に今の子だから出来なくても仕方がない、と庇われた記憶がある。
>>212
知的教養や民度が低く、文盲率が異常に高い社会と違って、会話や文章中の文脈から大意を汲み取り、理解出来る事が大前提であり、その習熟度によって個人の能力や為人が評価される、という文化的習慣があると言うだけの事。
日本語がある程度理解できても、その程度の社会常識も弁えていない君達は、日本人()?
>>204
単にどうしてもの必要性が無いから、発声の中から明確な区分が失われて来た、と言う言語的来歴があるだけだが。
現在進行形で失われつつある言語的アクセントも、未だに多数存在しているが、それが何か?
モノを知らないのに中途半端な知識で、全てを知った積りになるのは止めた方が良い。
>>201
英単語をわざわざカタカナにして不要な母音を入れまくって日本語と比べるこの頭の悪さ。くらべるなら発音記号使え。
>>203
とおあまりひとつ
eleven
hundredと「百」はどっちも2音節で発音されれば同じ長さだよ。
>>205
hundredが長いとかいってるやつは絶対英語話せないやつだろう。
「は・ん・ど・れ・っ・ど」って発音してるんだろうな。
>>217
単に舌が回らんのよ。話慣れている人間にとって短いって言うやつだろう。
言語的優劣に何の関係があるか聞きたい。
>>205
言語学者が良く持ち出す、その音節の基準が英語とか同大系語に基づく偏ったモノなので、日本語に当て嵌める事自体にあまり意味が無いと思う。
「日本軍の計画の厳格さ、そしてそれが予定通り進展しない場合に放棄するという傾向は、主として日本語の厄介で不正確な性格のためであったと思われる。日本語は信号通信によって即座に伝達を行うのが極めて困難なのであった。」
チャーチル『第二次世界大戦』より
あるブログ見ていたら
「現在の人類はネアンデルタール人の子孫ではなく絶滅してた?」っていう文があった。
「え?絶滅したなら現代人は存在しないんじゃないの」って思ったわ。
これを翻訳してみると
Has humanity been extinct,
not descendants of Neanderthals?
って出てきたけど,そりゃそう解釈されるわな。
別にこの文が特にひどいという気はない。このレベルの主語がよくわからん文がうようよあるのが日本語だね。
主語を省略する言語はいっぱいあるけど,たいてい動詞の人称変化で主語を復元できるし,日本語みたいに省略された主語を途中で勝手に変えたりする言語は見たことないよ。
>>535
言語の文法構造の優劣が個人の言語能力のほとんどを決定するんだよ。英語は主語を明示する構造だから個人は主語を省略しないんだろ?
いや,ぎゃくに英語はとにかくS+Vを書くという約束がしっかりしているから馬鹿が書いても曖昧な文にならない。
日本語は,人に情報を伝えるとき一番重要な「だれがだれをどうしたか」という意味があいまいになるのが致命的欠陥だ。
たとえば「AはBが好き」という文ではA likes BなのかB likes Aなのかもあいまい。
こんなニュースの見出しがあった。
「同居男性を殴り死亡させた疑いで男を逮捕『加害した人の意識がない』」
「加害した人」ってthe person who hurt somebodyなのかと一瞬思った。どうもthe person who was hurtの意味らしい。印欧語ではありえない構造的あいまい性だ。
>>220
きょうニュースを読んだら「パパはママが大好きな人だったから」という文があった。どっちがどっちを好きなのか今もわからない。
>>246
副助詞「は」をつけると格助詞が消えちゃうというのがよくない。それから~が愛情の対象のときは「 ~が好き」は「~を好き」に変えるとはっきりするのにね。
「パパがはママを大好きな人だったから」「パパをはママが大好きな人だったから」なら曖昧性は消える。まあむりだけど。
>>544
文脈がなければ意味は酌めないね。
おまえは文脈がなくても「パパはママが大好きな人だった」の論理的意味を酌めるの?
超能力者かよ。
>>682
基本それだけで会話しないし、文章も成り立たないから当たり前です。
当たり前の事も、一から十まで説明されないと解らないのは、子供だけで十分なんだが。
それにホントに上級者や、以心伝心レベルの身内・相方同士になると、その冗談みたいな超能力的なの、本気で発現、通用する時が結構あるからね?日本人には、現実に。
そういう経験無い?
スマホばっかり弄って、人と直接会話したがらない、今時の子かな?
>>739
そういうコミュニケーションの様式は
異文化間では機能しないんだよ。
すべてを明晰にするのがglobalな時代の常識。
>>741
いや、時と場合によっては機能してますが、現実に。
そもそも言葉が通じない人間同士の間でさえ、ジェスチャーやハンドサインひとつで、以心伝心する場合さえある現実を、一体何だと思っているんだ?
グローバル化って言っておけば、何でも誤魔化せると思ってるのが、モノ知らずの背伸び見栄っ張り、短絡思考過ぎる。
良く知りもしない付け焼刃の知識を、知ったかぶってヘンにひけらかすのは止めた方が良い。
>>682
スレッドを読み返したらどうだろう。似た様な疑問への答えは繰り返し散々書かれているぞ。
>>246
逆にソレをどちらに読むかで、その人間の人となりや真意を図るという、実に高度な裏技があってだな?
>>681
君や君の賛同者がそう考えるのは、君達の勝手。
正し、あくまで一見解であって、正解でも正論でもない事を忘れずに。
次の文を読んでみてください。
『「新型コロナウイルス感染症の主治医らから成る韓国中央臨床委員会でも、英化学誌「ネイチャー」などに掲載された論文を分析した結果、アビガンが新型コロナウイルスの抑制に効果がなく、副作用も深刻であることから「根拠不十分」とみているという。また、大韓感染学会・大韓抗菌要法学会・大韓小児感染学会の3学会も共同で「新型コロナウイルスの薬物治療に関する専門家勧告案」を発表したが、アビガンは含まれていなかったという。ただし、一部の専門家からは「万が一に備え、今後日本や中国で行われるアビガン治療や研究を中止すべき」との意見も出ているという。』(dmenuニュース)
どうですか? なにか違和感は感じませんでしたか?
ヒント:
論旨展開から言って「万が一に備え、今後日本や中国で行われるアビガン治療や研究を中止すべき」って変ですよ。どうして韓国が日本や中国で行われるアビガン治療や研究を中止する権限があるんでしょう?
解答
たぶん「中止すべき」は誤りでしょう。これが「注視すべき」なら完全に論旨の整合性が保たれますね。
社会にニュースを発信すべきメディアがこのざまです。不注意と言えば不注意ですが,日本語が同音異義語だらけの欠陥言語であることの一例です。
>>221
だからどうして半島…。あと個人の不手際が言語の優劣に繋がるって…針小棒大にもほどがある。
つぎは日本人の生徒が書いた英語です。
I really like B’z now!
Namie Amuro and Kenshi Yonezu don’t like that much.
こんな英語を書いてしまうのはSV関係があやふやな日本語の影響でしょう。
「ジャイアンと桐崎千棘はどっちが殴られたら死にそう?」
だれがだれをなぐりだれが死ぬのでしょうか?
英語ではこんなゆるゆるの文は書こうと思っても書けません。
>>224
AIを駆使したDeep Learning翻訳でその文を英訳すると
Who is going to die if Gian or Kirisaki Chisika gets hit?
となった(笑)。 そりゃそうだわな。
>>277
AIで言語の壁がなくなると思っている人がいるけど,外国語→日本語 の翻訳はOKだろうが,欠陥言語・日本語→外国語 はどんなにAIがすすんでもだめだな。224/277を見ればよくわかる。つまり日本語の文自体が文脈から独立した明確な意味を欠いているんだから。
>>278
英語が日本語を表現できないのが、日本語の欠陥ではなく、英語の欠陥である可能性は?
英語優秀派は殊更その事実を無視している様に見える。
>>224
そうでしょうとも!
その文章がどんなTPOで言われたかで、文意を汲み取るのが日本語ですから。
一文だけ挙げて騒いでいる英語すぐれてる派の、ズレ具合と言ったら。
①この映画はワクワクする。This film is exciting.
②私はこの映画見てワクワクする。I'm excited to see this movie.
こんな区別すらしないのが日本語。
だからZOZOの前澤が月旅行予約してI am exciting.とか言って恥かいてる。youtubeに動画あるよ。
>>235
いやだから、ちゃんと翻訳できてる時点で区別できるやん。日本人同士が面倒がって省略しても、互いに汲み取ったり流したりするから、普段多用せんだけで。
しないと出来ないは、一緒じゃないからね。
>>549
あなたは何を言っているんですか?
あなたのコメントは235と全くかみ合っていません。
優れるという価値観がそもそもおかしいんですけど、習得しやすいのは英語です。
日本語は不便な言語で文脈や声のトーン、表情で総合的にみないと意味が誤解されるので、習得の点では難易度が高いと思ってます。
>>241
それは「難易度が高い」というより劣っていると言えるような気がします。「難易度が高い」というと喜ぶ人が必ず出てきます。「そんな難しい言語使ってるおれらかっけー」みたいにね。
>>242
言語は第一言語なら誰でも習得できるのは当たり前だし、カッコいいと思うのも個人の勝手だと思うんですけど、言語に優劣を付けると国際社会では少し問題視されますね。それぞれ異なる特徴があるに過ぎないので、どれも貴重な文化として見なす態度の方が歓迎swれます。
>>245
政治的には問題視されるでしょうね。でも政治をのけて考えるなら,言語の優れた点や欠点を議論することは意味があると思います。
人種とIQの相関の研究に似ています。
>>242
じゃあ英語派は、「難易度が低い」から「そんな解り易い?言語使ってるおれらかっけー」なんですか?
日本語はpunctuationにも規範的なルールがなく,個人の自由にまかされている。たどえばドイツ語ではどこにカンマを使うかほぼ100%決まっている。英語はドイツ語ほどではないが,ある程度の規則化がなされている。日本語はどうか?
例:ある医者のブログ
「不安と恐怖が、ウィルスに対する愛と感謝に変わった途端、ウィルスは、目の前で、ブラックホールから、突然、喜んで、消え去ります」
世界の言語のほとんどは分かち書きを採用していますが,それをやらないもんだから読点[カンマ]を分かち書きのノリで使っちゃう人がいるという悲惨な言語が日本語です。一方全然読点を打たない人もいっぱいいます。
日本人は話すとき「えー」とか「まあ」とか「そのー」とか無意味な発声がやたら多い。英語を話す人間はそういうのが少ない気がする。それにいわゆる「かむ」回数も日本人のほうが多い気がするし,主語と述語が離れているせいか,全然主語に合ってない述語を言っている人がよくいる。
これは何が原因なのかな?もしかして言語の構造と関係があるのかな?
>>250
「涙も汗も若いファイトで 青空に遠く さけびたい」
「涙も汗も→さけびたい」? 主語(目的語かも)と述語があってない。
>>281
考えるな!感じるんだ!!の典型例。
マジメに考える自分は論理的、って言いたいのかな。
Let us help you help yourself.
この文を論理的情報を失わないように日本語で表してみてください。日本語の限界と非能率を実感できるかもしれません。
>>554
なぜこの文から英語の限界と非能率が実感できるのかな?言ってみて。言わなければただのはったりと見なす。
As his counterpart, the woman completes or fills out a man's life, making him a larger person than he could have been alone
こんな複雑なことをさらっと文にしてしまえるのが英語。
この文の意味を原文の意味を失わないように日本語で表現できますか? ほぼむりだと思います
Love is to life what blood is to body.
この構文習ったとき,まるで数式だなと感心した。
「不倫したい人妻」ってどういう意味でしょうか?
a wife who wants to have an affairにも思えるんですが,
「MAX Minaと雛形あきこはどっちが不倫したい人妻?」ってもしかしてa wife you want to have an affair withの意味なのか?
日本語は構造上こういう重要な区別ができないことがしょっちゅうあり,そのつど文脈から推定しなけれならない。
明晰性の点でダメすぎる。
「新潮社へお願いします」
と言ったら、都庁に連れて行かれたことがありました。当時、新宿区に出来た都庁はまだ新しく、
「新庁舎」
と呼ばれていた時代でした。
>>257
自己中心的思考による「当然解るでしょ」という発言で、見も知らない赤の他人には言葉が簡潔過ぎて、言いたい事がうまく伝わらなかったという好例。
そもそも相手が「新潮社」自体を知らなかった場合には、成り立たない笑い話だという事も丸無視だしな。
ここのコメントをずっと読んできたが、英語派のコメントが具体的であるのに対し、日本語派は具体的根拠のない感情的なコメントしか書いてないね。
>>258
一般に論争においては不利な側の人は抽象論にたよろうとするんですよ。具体的根拠がなければそうするしかないから。
>>271
一般に、自分の知識量を鼻に掛け、小知恵が回って他人の揚げ足取りと、屁理屈をいう事が得意な人ほど、具体的根拠にばかり拘るんですよ。
自分が頭が良いと誇示したがってね。でも、そういう人は誰からも、本当の意味で頭が良いとは評価されません。
頭が本当に良い人は具体例だけに拘らず、どんな人にでも柔軟に対応し、解り易い会話を心掛ける事が出来ますし、これほど自分本位で他者に対して攻撃的には成りません。頭の良さは人としての余裕や、他者への理解にも繋がる要素なので。
>>258
英語派も大差無いと思います。
具体的なのではなくただ、英単語や英文を並べて知ったかぶっているだけです。身内だけに解る言葉で話して、何の具体的根拠か。
>>258
英単語や英文をただ羅列して、個人の主観を並べただけの感情論では、そもそも何一つ具体的根拠には成っていないんだが。
何故、それらの単語や文章が、英語が優れている事の証明になるのかの、具体的論拠や詳細の説明には、全く掠ってさえいない事が、君達には理解出来ないのか?
君達一部の人間は「どーせ、お前ら英語が出来ないから、何が書いてあるのかだって、解かんねーだろ!これだから英語が出来ない奴は!!悔しかったら翻訳してみろよ!!!」と、一方的に喚いているだけの、説明にもなっていない様な暴論が、具体的根拠だの論理的説明と同等だのと、ひどい勘違いをしていないか?
仮に英単語や英文を正確な日本語に翻訳出来たとして、ソレの何が英語が優れた言語である事実の、説明になると思っているのか。日本語翻訳能力の優秀さの証明以外に、何も証明されそうもない話だが?
まさか元の英単語や英文が優れているから優れた日本語訳になったなんて、如何にも辻褄の合わない無茶を、後出しで言い出すつもりじゃあるまいな?
それとも日本語に翻訳出来ない事が、英語の言語としての優秀性を示すとでも?誰にも理解されない様な内容が?
異なる他者同士におけるもっとも原始的にして、世界で最初の発明であると思われる、相互理解の為のコミュニケーション・ツールとして生み出され、長い時間をかけて発展してきたハズの、言語そのものの存在意義に反する様な話だな?
異なる言語話者に理解されない事が、理解されない言語自体の優秀性の証明か?小学生の屁理屈か。三段論法にさえなっていないぞ。
「優れている」と言われると、判断に困る。
たしかに公用語として使われているのは英語。だけど、英語は英語でも、学校で普通習えるのはアメリカの英語。だとすると、イギリスやオーストラリアへ行った時の対処法がわからない。
それに対し、日本語は、海外の人から見たら、難しく思われがち。でも、だからこそ、しっかりとした日本語で喋れば、英語よりも複雑な表現ができる。さらに、「日本語」は日本でしか使われていないため、地域によっての言語の意味の違いが少ない。
だったら、日本語のほうが優れているのではないか。
>>259
牽強付会すぎ。
「しっかりとした日本語で喋れば、英語よりも複雑な表現ができる」
それはあなたが日本語のネイティヴだからですよ。
>>259
おれ仕事でたくさんのアメリカ人・イギリス人・オーストラリア人と話してきたけど,いつも日本人英語で何の支障もなかったぞ。たしかにオーストラリアの[ei]が[ai]になるのとか最初はわかりにくいけど,すぐ慣れるぞ。「シーユーライター」って意味わかるでしょ?
ロンドンのタクシーの運転手の英語だけはあまりにもなまりがひどかったけどな。「地域によっての言語の意味の違いが少ない。」おまえが無知なだけ。同じ日本語の意味が地方によりちがうことなんかいっぱいあるぞ。たとえば「しまう」「まくれる」「おなか太った」「これはみやすい」「ゴミ投げる」。これらは地方により全く違う意味になる。
>>259
ひとつでいいから具体例を書いてみ。
日本語優れている派の人は主張ばっかで具体例出さないから議論にならん。
>>286
ひとつでいいから、これと思う英文の的確な日本語訳文を書いてみ。
英語派の人は、英語が解る人同士の屁理屈ばかりで議論にならん。
>>311
具体例、具体例って。自分では論理的な心算かもしれないが、却って頭が悪く見えるから、止めた方が良い。
きょう私がWikipediaを読んでいたら次の文があった。
「1938年 ドイツのオットー・ハーンにより発見され、リーゼ・マイトナーによって核分裂反応と確認され、質量とエネルギーの等価性が実証された。」
うん?主語がない。なにが発見されたのかわからない。これ書いてた人の頭では主語がわかっているんだろうけど。
Wikiって一応百科事典なのに,このありさまです。
英語のWikiで主語がない文に出会ったことはないな。
日本人ばかりでこの問題を議論しても不毛なので,外国人の意見も見よう。ある言語学者の見解。高校レベルの英語なので読んでください。
The Japanese have no definite or indefinite articles corresponding to the English a, an, or the, and they do not distinguish between singular and plural as we do with, for instance, ball/balls and child/children.
It is harder to justify the absence of a future tense in Japanese. To them Tokyo e yukimasu means both "I go to Tokyo" and "I will go to Tokyo." To understand which sense is intended, you need to know the context. This lack of explicitness is a feature of Japanese ― even to the point that they seldom use personal pronouns like me, my, and yours. Such words exist, but the Japanese so often omit them that they might as well not have them. Over half of all Japanese sentences have no subject. They dislike giving a straightforward yes or no. It is no wonder that Japanese is so often called obscure.