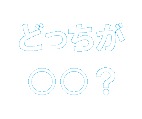日本語と英語はどっちがすぐれている?
日本語は主語を省略するって言われるが、目的語の勝手な(=ルール無しの)省略も多い。
「グリーンピースを箸で取って食べる」
これはどういう意味なのか?
次の例は知恵袋のある質問。
「グリーンピース
嫌いな人が結構いるのに何故シューマイは堂々と上にのせてるんですかね?
ハシで取って食べます」
変な改行をして句読点もないのはおいといて、「ハシで取って食べます」はどういう意味か?
たぶんこの筆者は「(グリーンピースを)箸で取り除いて(シューマイを)食べる」と言いたいんだろう。
こんなむちゃな目的語の省略を許容する言語はないだろう。そんな言語を知っていたら教えてくれ。
日本語は要は「わかるやろ、おれはわかる」というポリシーの言語なんだな。これでは必然的に誤解や不理解がおきる。
>>2356
『これでは必然的に誤解や不理解がおきる。』
文脈を正しく理解する能力があればそんな事は起きないね。
日本語は文脈頼りだが文を作るのはだいぶ楽。あと、表現の幅が大きい。
英語は確実性があるがまどろっこしくい。
あと、記号ばかりで読みづらい。
>>2366
実際は文脈を正しく理解する能力がない人が多いからそんな事がしょっちゅう起きるんだよ。
英語の記号ってなんだよ? 「?」とかか?
>>2358
それはあなたが日本語のnativeだからだ。
英語のnativeなら英文を2/3くらい隠してもけっこうよめるだろう。
ネイティブの日本人はいいけど日本語を覚えようとしたらあまりにも難易度が高すぎるからさすがに英語かなぁ
.日本は日本語使ってるのがネックだと思う。
「えーっとこの名前なんとよむんだろ、えーっとこの漢字どうよむんだっけ、えーっとこれどの漢字つかうのかな、えーっとこのわたなべさん渡辺・渡邉・渡邊・渡部のどれだっけ、えーっとこれ変換ミスじゃないのかな、えーっとこれ漢字でかくのかなかながいいのかな、えーっとこのおくりがなあってるかな、えーっとうちは締め切り、締切り、締めきり、締切、〆切、締め切どれつかってたっけ、えーっと、この人おれよりちょっと年上だな、どういう敬語使えばいいのかな、えーっと昭和47年から平成9年て西暦だとなん年からなん年だっけ、えーっと「スパゲッティ」、「スパゲッティー」、「スパゲティー」、「スパゲティ」うちはどれに統一するんだっけ、えーっと「シグナチャ」、「シグニチャ」、「シグネチャ」、「シグネイチャ」、「シグナチャー」、「シグニチャー」、「シグネチャー」、「シグネイチャー」、「シグネーチャ」、「シグネーチャー」、「シグナチュア」、…
こういうことを1億人以上がやってうしなわれる時間はぼう大です。言語ガチャはずれの国。
>>2376
日本はそんなバカなアメリカに学問も経済も軍事もボロ負けしていますね。なぜですか?
>>2425
アメリカには優秀なアジア人がいるから
あと政府が教育にお金を使ってるから
だからアジア人が頭良くなる
>>2376
文字表記とか、そんなくだらないことに脳を酷使しないでもっと創造的なことを思考できるほうが有利だろう。
>>2514
文字表記のために脳を酷使できるからこそ俳句や何でもひらがなと漢字の見かけの印象を表現技法として用いた詩を作れるのです
なので文字表記のために脳を酷使することは必ずしもくだらないことではありません
これだけの文字の種類があり、文字の種類で表現を変えることができる日本語は文学的な創造に優れていると言えます
>>2361
そしたらうちのALTが新しく来たALTの名前を聞いたときスペルを何度も書き直した挙げ句、本人に聞いてたよ
英語は少ない文法で話せるけど、語彙が多いほうが抽象的思考も広がるから合理的が必ずしも良いとは限らない
>>2362
「少ない文法」ってなに?英語のほうが文法的ルールは多いよ。日本語は単数とか複数とか未来完了とか過去完了とか冠詞とかないやん。そのせいで大ざっぱな表現になってしまうが。
なぜ文法の話をしはじめて、「語彙が多いほうが抽象的思考も広がる」っていきなりトピックがかわるの?
それはさておき「語彙が多いほうが抽象的思考も広がる」なら英語のほうがはるかに語彙が多いし、しかも抽象語の数が特に多いから、英語のほうが抽象的思考が広がるじゃん。その証拠に、イギリスやアメリカでは科哲学・論理学がすごく発展したけど、日本では世界的な論理学や哲学はほとんど発展してないね。
>>2363
捏造するなよ。
日本語の語彙数=英語の語彙数やぞ。
https://www.google.com/search?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E+%E8%AA%9E%E5%BD%99%E6%95%B0&rlz=1C9BKJA_enJP1056JP1057&oq=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%80%80%E3%80%80%E8%AA%9E%E5%BD%99%E6%95%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDk0NjdqMGo3qAIAsAIA&hl=ja&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
日本語は単数とか複数とか未来完了とか過去完了とか冠詞とかない代わり、活用があるやろ。
てか、単数、複数、未来完了、過去完了、冠詞は修飾詞でほとんど表せられるぞ。(確か)
欧米人は『個』や『自分自身』について古代ギリシャの頃からずっと考えている。
これが哲学の基礎だが、日本人は『社会』という『集団』を考えている。
(哲学や論理学は欧米発祥だし。)
このような違いで日本と欧米で差があるんだと思うよ。
>>2367
だれが個人の大人の語彙数の話してるんだよ。言語全体の語彙数の話にきまってるだろう。
それに「5万」とか切りのいい数字いいかげんに決まってるだろう。「言われている」ってだれに?
日本最大の『日本国語大辞典』(小学館)は50万語。
英語圏最大のOEDは62万語。
活用が何の役に立つ?ほとんど助動詞とかと接続するときの発音の変化みたいなもんだろう。
「単数、複数、未来完了、過去完了、冠詞は修飾詞でほとんど表せられるぞ。」
日本語派なら日本語を正しく使ってください。×「表せられる」⇒〇「表せる」
「修飾詞」って何すか? じゃ修飾詞で次の文の意味を表してください。
a) Is this what Dickens would have been going to write?
b) Here's the thing.
人が「確か」という副詞を使うときは発話内容が確かでないときである。
>>2368
表せられるで意味は合ってるぞ。
活用が何の役に立つかって?
https://ja.m.wiktionary.org/wiki/%E4%BB%98%E9%8C%B2:%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8
これを見れば分かるが日本語において活用は大事だね。
「修飾詞」は変換ミスです。「修飾語」でした。
>>2369
俺は「文脈を正しく理解する能力があればそんな事は起きないね。」
と言った。
『あれば』とあるから仮定形、英語ならifの文。俺は仮の話をしたに過ぎない。
ほぼアルファベットだけで分かりづらいやろ。(個人の感想)
>>2372
意味じゃない、「表せられる」という形が非標準。
作文に「表せられる」って書いてみればいい。
>>2373
ら抜き言葉がだめなのは下一段活用動詞の場合だけなので「表す」を可能動詞にする場合は五段活用動詞なので「表せられる」であってます
>>2448
日本語派のくせに『「表せられる」であってます』って、終わってるわ。「表す」の可能動詞形は「表せる」。国語の文法を勉強し直そうね。
>>2543
それは完全に私のミスです
動詞は苦手なもので
未熟者で申し訳ありません
>>2372
仮定するのは自由だが、実際には文脈を正しく理解する能力が十分でない人が多いからそんなことがおきるね。仮定ではなく現実の運用のほうが重要だ。
「ほぼアルファベットだけで分かりづらいやろ。(個人の感想)」
たぶんこの文の主語は「英語」なんだろう。アルファベットだけで分かりづらいなら世界のほとんどの言語はなぜアルファベットを採用しているのか?おおむかしはどこの国も表意文字を使っていたのに。
>>2372
「修飾詞」は変換ミスです。「修飾語」でした。
なぜ「しゅうしょくご」の変換ミスで「修飾詞」がでるんですか?
それは変換ミスではなくて、あなたの記憶違いでしょ?
>>2382
間違いを指摘されると「変換ミスだろ」って開き直るやつ多いが、やたらに変換ミスするのはバカだからだ。そして変換ミスなんてものが頻発するのは日本語というシステムの欠陥だ。
>>2541
言うても英語も一つでも足したり抜いたら意味が大きく変わるんで完璧な言語は無いってことですな
>>2542
君の言っていることは意味をなさない。
完璧な言語から一つ抜いたら完璧でなくなるのは当たり前だろう?
日本人なら全部正しく読んでね。読めない人は非国民。
大和証券 大和運輸 大和製罐 大和フーヅ 大和自動車 大和工商 大和ランテック 大和工業 大和企業 大和産業 大和書房 大和電器 大和精工 大和製衡
次の文はQuoraにあった質問だ。「兵士が部屋に侵入しても撃たれない方法は?敵は侵入の音を聞いてドアに向かって発砲し、すぐに兵士を撃たないようにすることはできないのでしょうか?」
日本語はこういう文が多い。「撃たれない」の主語が「侵入した兵士」なのか、侵入された側の部屋にいる兵士が省略されているのか不明だ。
この質問の答えでも回答者が「兵士が部屋に突入した時に「突入した兵士が」撃たれないようにするには、ってことで良いですね?」と聞き返している。この解釈がただしいかどうかもわからない。
英語ではこんなことはまず起きない。
さすがに英語でしょ
英語の方が難易度圧倒的に低いし世界中で通用する
後付けとかも効くし
日本語に入れてるのは無知かネトウヨかなぁ…
>>2392
出来ないとは一言も言ってないぞ
さすがに私も挑発的に言いすぎたのは謝るが現実を見た方がいい
言語としての習得難易度が圧倒的に高いとされていて、かつ通じるのが日本以外だとパラオが公用語になっているくらい。それに最近ではパラオの日本語話者の高齢化が進んでしまっているらしいし
国際的にも多くの国が英語を公用語としている
プログラミング言語なども英語が基準のことが多い。
ただ我々は日本列島に生を受けたから日本語が使えている。
英語の方が優れている
>>2392
ネトウヨとかサヨクとか、そういう低次元のののしりあいしないで言語学的に論争しろ。
>>2386
世界で通用するのは昔アメリカとイギリスが世界中で暴れまわり言語や宗教、政治体制を押し付けたからだろ
>>2463
だからこそ多くの地域と民族で話されるということは芸術性の発展の妨げとなるので芸術的観点から日本語と比べて優れているとはいえない
>>2464
「多くの地域と民族で話されるということは芸術性の発展の妨げとなる」このロジックが不可解すぎ。
>>2538
多くの民族の文化が混ざることでその言語が生まれた土地特有の文化と芸術的な要素が薄れていきます
言語にアイデンティティがなくなることで言語が生まれた土地独自の性質が現れにくくなるからです
しかし日本の文化とともに発展してきた日本語ではどうでしょうか
日本が持つ文化に対応した言い回しや、日本語自体が日本の文化としても発展してきました
>>2547
多くの民族の文化が混ざることで豊かな文化と芸術的な要素が増していくよね普通は。
そもそも日本語はやまとことばと中国語と英語やアイヌ語やオランダ語などの混合でできているよね。
日本語は相手を思いやり尊敬することを明確に表現でき、子音が少なく母音がよく出ているので美しく芸術的な言語であるため英語より優れていると思う。
詳しくはこれ見ろ
>>2395
日本人が「なぜ日本語は美しいのか」ってうちの子イケメンみたいな親バカメンタリティーで書いた本に価値はない。そういうのは韓国人に任せとけばいい。
優劣の付け方がよくわからない。例えば、日本語は習得するのが難しいってよく言われてるけど、それは人によっては優れてると思うし逆に劣ってるって思う人もいるかもしれないから。自分の基準で行くなら、世界中で通じることがデカいから英語かな〜
個人的には、
・文字が少ない
・パソコンで打ちやすい
・略している時は、'が付く
・述語が先に来やすい など
という点で英語は優れていると思う(日本語にも優れているところはあると思うが)
そもそもその地域で使われてる言語に優劣はないだろ。強いていうならそれを覚えたことで得られるメリットがどっちの方がいいか。つまりどっちか覚えるとしたらどっちがいいかみたいな。
>>2410
「その地域で使われてる言語に優劣はない」
そのとおり、だから言語を地域から切り離して考える必要があるね。
英語がすぐれていると言っている人たちには「英語はアメリカ人にとってわかりやすく細やかな感情も表現できるから優れている」なんて言ってる人はいない。
一方日本語派は「日本語は細かく表現できる」とか「わかりやすい」とか自己(日本人)中心的な意見が多い。
>>2416
それは日本人は日本語を芸術として発展させてきた過去があるため他の言語ではくどくなるような細かいニュアンスでも表現できるからである
>>2449
英語でもまったく同じことを主張できる。
「それは英米人は英語を芸術として発展させてきた過去があるため他の言語ではくどくなるような細かいニュアンスでも表現できるからである」
外国語は「何がどうした」とかはっきり言わなきゃだけど、日本語は「あれ」とかで伝わるし。めんどくさくないのは日本語だなぁって
>>2412
一度かなやローマ字で書いて、変換キー押して、分節が間違っていたら切るところを修正して、出てきた候補から正しいものを選ばねばならない日本語のほうがめんどくさい。英語ならキーを一度打ったらその瞬間に作業が終わっている。同じ内容の文打つのに日本語はへたすると倍の時間がかかる。
>>2412
伝わるとは限らないだろう。日本語のコミュニケーションで起きた誤解の例がこのトピックのコメント欄にいっぱい出てるよね。
>>2413
日本以外の国ならほとんど英語が勝つだろう。
よっぽど親日か反米反英の国以外は。
完全な言語は存在せず具体的な数値などで完全さを表すことはできないものとし、日本ははるか昔から日本語を芸術として発展させてきたことから他の言語と芸術的な観点から比べた時、日本語のほうが優れていると考えられる
>>2440
「日本は日本語を芸術として発展させてきた」
これが他の言語より日本語がすぐれている理由だということは、他のすべての言語はこれをおこなってこなかったということですね?
その具体的根拠はなんですか?
>>2450
外国の詩などは自分の思うことを韻などを意識して連ねたものだが日本の文学は色彩表現や擬音語及び擬態語、反復などの文を美しくする工夫が数多くあるため芸術的であると言える
他に言えることとして中国語の詩も日本語の詩と同様に美しくする工夫があるが、使用している文字は中共が生み出したものなので含めないとする
台湾の繁体字を用いたものを中国語とするならば日本語と同じくらい優れていると私は考える
>>2451
言語は5000以上あるのに「外国の詩などは」でひとくくりですか?
私はそんなに多くの言語を知らないので、日本語の詩の技巧が特に優れているかどうかなんて判断できません。あなたはそれができるのですか?
私は英文科で英語の詩を学び、英語の詩の技巧、脚韻、押韻、韻律はものすごく精緻で、オノマトペ、メタファ、メトニミー、シネクドキ、縁語、引用、反復、オマージュ、パスティーシュなど、修辞法もものすごく豊かだと思いました。
しかしそういう文学的なことは客観的な比較が難しいと思います。
>>2453
英語の詩にも二行連や四行連などがあり日本語と簡単に比べることができないことはわかるがそのような詩の形が出来上がったのは16世紀とされている。
これに対し日本の詩は8世紀の頃から今でも親しまれている俳句や短歌があるのでその分、日本語のほうが優れていると考えられる
>>2667
すごい前のコメントに返信なさるのですね
普通にその改良方法の質が低くても年数でそれは補えます
なので8世紀の頃から既に文化としての形がある場合も同じことが言えます
日本語は同音語をやたらに作ったため誤字だらけの言語になっている。
きょう見つけた誤字。
知恵袋より。
「質問者からのお礼コメント ありがとうございます。気持ちがのっているときだけ世話をして、興味がなくなると疎かにした結果と紳士に受け止めます。
ペット斎場にて丁重に供養しました。」
>>2436
知恵袋にこんなのあったよ
<お尋ねしたいのは
「何が楽しくて…」←私が指示した。
「何が悲しくて…」←他の人が指示した。(当時の神奈川育ちの友人)
国語に明るい方、一般論でどっちが正解か?両方とも正解か?>
なに言ってるのかわからないと思っていたら、「私が指示した」って「私が支持した」のつもりなんだな。
ためしに"指示する政党" "政党を指示する"ってググったらいっぱいあるな。
だめだこりゃ。
>>2436
きょう見つかった哀しい日本語
(個人のブログとかじゃなくて公式のニュース)
「ロシアのミサイル攻撃を受けた現場で、消火活動に当たる消防退院ら(21日、ウクライナ・ドニプロ) 」
音素のヴァリエイションが少なすぎるのは欠陥。
>>2439
If you wanted me comment in English, I would be happy to do so.
>>2439
I'm ready to write all my comments in English if you want. ー
「お酒は飲まないけど長生き・老後を健康に生きるために嗜好品を諦めるってのはなんだか寂しくないのだろうか」
これは全くありふれた日本語の文だが、この文では、「お酒は飲まない」の主語と、「生きる」および「諦める」の主語は異なりますが、どちらも省略されています。こんなことが許される言語が世界にいくつあるのでしょうか?
以下、引用記事
「頂き女子りりちゃんよりも、貢いだ男が15年は刑務所に入るべき」
「りりちゃんにしっかり対価もらって3800万あげたジジイ、りりちゃんに対して15年くらい刑務所入っててほしいとかインタビュー答えてて気持ち悪い。25歳と本気で結婚できると思ってお金欲しいとも言われてないのに困ってるって言われただけで大金あげちゃった愚かさを戒めてお前が施設に15年くらい行けば」
10:「貢いた男」ってホストの方かと思ったらそっちかーい
(引用終わり)
欠陥言語日本語にはよくあることだね。
日本語は関係代名詞がないうえに主語目的語を勝手に省略するせいで「貢いだ男」が「(女が)貢いだ(相手の)男」の意味なのか「(女に)貢いだ男」の意味なのか構造的に決定できない。十分な文脈的情報がないときは、意味が確定できないことになる。つぎのようにDeepLのような高性能のAI翻訳でも誤った解釈をしてしまう。
a)彼女は1000万円貢いだ男にだまされた。
→She was cheated by a man who contributed 10 million.
b) 彼女は1000万貢いだ男をだました。
→She cheated the man who contributed 10 million.
印欧語その他では名詞を修飾する関係節はそのもととなる文の格構造を完全に保持しているのでこのようなことにはならない。
日本語って使う国が少なすぎてプログラマーとしてはかなり欠陥だと思う日本語で商売なんてできやしねーよ😥
>>2494
かん国人教師がそれと全くおんなじことをyoutubeで主張していて笑いものになっていた。
>>2507
英語の種類ってなに?アメリカ英語とかイギリス英語とかのこと?そんなのどれか一つおぼえればいいんだよ。
>>2515
「英語のほうが優れている」の主語は「英語」ですが
「世間一般では英語のほうが優れているそう」という文章において
「英語のほうが優れている」ことを主張するのは「世間一般」なので
「世間一般」が主語ですね
>>2516
残念、「世間一般では」は主語じゃなくて「主題」を提示する副詞句だな。英語だとIn the world English is superior.だろ?英語が主語だな。
日本語しかできないやつって「主題」と「主語」の区別もできないんだよね。だからまともに外国語できないやつが多いんだよ。「ぼくは(=主題)今日仕事だ」をI (=主語)am work today.とか直訳しちゃってバカにされるんだわ。
>>2532
反論しないんですか?
無視ですかそうですか、じゃあ日本語のことなんてどうでもいいんだ、このまま日本語なんて消えちゃえって思ってるんだ、ふーん日本語は全て英語になっちゃえってそう思ってるんだ
>>2562
自分が反応ない時は煽るのに反応したらしたで返信しないのは自分勝手すぎるでしょ
>>2564
「自分が反応ない時は煽るのに反応したらしたで返信しない」
劣等言語のすばらしい例ですね。
述語が4つあるのに主語が1つしかない。
>>2690
伝わるのは日本国内だけ。いや、日本国内でも伝わらない例がこのトピックのコメントにもいっぱいあがっている。
>>2532
なんで返信してくれないの?日本語のこと嫌いになっちゃったの?
悪いとこ全部直すから、同音異義語とか数のあやふやさとか全部直すから返信してよねえ
>>2525
主語と主題の問題とは少し違うかもしれないが、おれの同級生で「私は病気です」をI am illness.って書いて×もらったやつがいた。日本語は「この魚はウナギだ」も「(おまえはさしみ食うのか?)おれはウナギだ」もおなじ構文にしちゃう言語だからどうしようもない。
>>2533
「マラリアは病気だ」Malaria is an illness.
「私は病気だ」 I am ill.
「お化けこわい」 Monsters are scary.
「私こわい」 I am scared.
>>2525
私の説明に根本的な間違いがあったのは認めますが、結局主語が小さくても馬鹿と言われるような人は主題が大きい場合がほとんどです
馬鹿と言われる人の多くは「一部」を「大勢」と捉え、自分の主張を正当化しようとします
>>2509
も資料の提示や標本調査等をしたわけでもないのに英語派の人たちを「世間一般」という「大勢」と認知しています
つまり>>2509
は「一部」と「大勢」の区別に問題があると考えられます
>>2525
二の丸庭園の滝にあった看板の"TODAY IS UNDER CONSTRUCTION"という英文が世界で笑いものになってるよね(知らない人は検索してください。)。
「きょうは工事中です」という日本語を直訳したらしい。
本当の主語は滝で、「きょうは」は主題にすぎないのに、それを英語の主語にしちゃったもんだから「きょう(の世界全体?時空全体?)が工事中」という壮大なスケールの意味になっているのに、劣等言語しか知らない人はそのナンセンスさに気づかない。
英語にも不合理に思える部分はあるが
日本語ほどではない。これ読めばわかる
【悲報】日本語、数字すらマトモに読めない欠陥言語だったwwww
平成の頃で最も有名になった
英会話教室は?NOVAだと思う...
※だけど...受講料問題、教師の給料問題が
色々と続いた騒動が起き、
教室は?ピークの半分まで減った...
最近のBIGモーター、BOOKOFFみたい...

日本語は同音異義語多すぎる時点で言語として終わってる。
さっき「newsランナー」を見ていたら、テロップで「小林製薬の紅麹サプリを接種して死亡」って出してた。
サプリ溶かして注射でもしたの?lol
>>2557
接種と摂取、確率と確立、消火器と消化器なんて平常運転だねえ。
音素少ないのに音素と声調がすごい複雑な中国語を取り入れた⇒同音異義地獄になった⇒漢字で書けば同じ音でも区別できるからOK⇒でもみんな漢字をまちがいまくるからいっそひらがなのほうがましかな?というのが日本語の現状。
きょうも豪快なのを見つけた。誤字と誤情報の宝庫「知恵袋」でね。
「英語で、as 原級 as any どれにも劣らずという氷原がありますが、
直訳すると どれとも同じくらいの方がしっくりきませんか??
なぜこのような訳になるんでしょうか」
>>2560
"同姓愛" って検索してみ(quotation marksつけて)。
もうひとつ。消化器の例。質問してる人も答えてる人もまったく誤りに気付いてもいないな。
質問「消化器とダンボールについて質問です。祖母宅で消化器の訪問販売業者が1本1万8000円の消化器を売りに来ました。
会社の方に電話をし、クーリングオフをする事になったのですが消化器を入れるダンボールがありません。郵便局を指定されたので郵便局の方にも訊きましたが、消化器に合ったダンボールは無く、業者の方も袋で持ってきたのでありません。業務用消化器なのですが、良いサイズのダンボールが売ってるお店とかありますか?」
答「ホームセンターで箱付きの消化器買ったら?
消化器買うって事は欲しかったんじゃないんですか?」
質問者「はい。家にある消化器が古いからと購入したようです。」
>>2561
漢字ばらばらならひらがなでいいよね。
「ストッキングがでんせんする」
これ「電線」「伝線」「伝染」とみんな好き勝手にかいてるよね。もうひらがなで統一しとけ。
「そっこう仕事にかかる」ってどうよ?
「速攻」に「即効」に「即行」。そんなばらばらなら
ひらがなにしとけよ。
英語とか他の言語は記号を組み合わせてるだけ。日本語は漢字一文字に意味があって、その組み合わせの多さと表現性は単一記号の組み合わせ言語と比較にならないくらい豊か。大人と子供以上の差がある。ITなんかが英語由来のものが多くてカタカナにして使ってる阿保がたくさん湧いてるが、それは英語でしか表現できないのではなく、業界と自分の国語力が足りないからだと自覚して欲しい。
>>2566
日本語派の人はなにかというと漢字をほめたたえるが、漢字を作ったのは中国人だね。
そんなに漢字が優秀なら世界中の人が漢字でITやればいいのにねえ。コードも漢字で書けば?
>>2566
じゃああしたから英語から来た外来語使わずにくらしてみなよ。
「スマホ」「AI」「セクハラ」「ドローン」「ホームセンター」「コンピューター」「エレベーター」「レストラン」・・・全部「日本語」で言うんだよ。
英語ではgenerative AIは1つのつづりで統一されているのに、日本語の表記はgenerativeがジェネレーティブ、ジェネレーティヴ、ジェネラティブ、ジェネラティヴ、ジェネレティブ、ジェネレティヴ、ジェネレイティブ 、ジェネレイティヴ・・・とみんな好き勝手に書いていて、私が原稿を書くとき、編集の人が「どれで行きますか?」って聞いてくるのよね。
外来語一つに10個ぐらいの形態が増殖するわけ。
これでいいの?
みんなこれでいいと思っているから日本語はこんな状態なんだよね。
1つの語に綴り方が何種類もあるって、英語なら近代英語のシェークスピアの時代以前だね。
つまり、日本語はまだ近代言語と呼ぶ価値がない。
クレオールとかピジンの表記のレベルなんだね。
日本語以外の先進国の言語のように一つに決めてくれたら迷うこともなく、検索を何度もやりなおす必要もなく、労働生産性も上がるのに。
質問が愚問だと思いますが、日本語を推します。一つ目の理由は、主題表示ですね。よく主語がないことが槍玉に挙げられますが、主題優勢言語にも良いところはありますよ。例えば、「象は鼻が長い」という文では、係助詞「は」で主題を表示して聞き手にイメージを促しています。そして主語の「鼻」が来ます。この「鼻」は「は」が作り出した世界の中での主語です。このように、主題優勢言語は柔軟です。二つ目は、複雑な筆記システムですね。英語は26種類のアルファベットでこと足るのに対し、日本語は仮名文字、そして数え切れない程の漢字を使います。日本語は英語とは違い、表音文字と表意文字の二つを持ち、与えたい印象によって使い分け出来ます。例えばひらがなでかくとやわらかくておさないいんしょう、カタカナデカクトケイカイサヤカタコトカンが出ます。この音節文字を誠実な印象を与える漢字と併用することで、分かち書きしない事による読みづらさを軽減したり、さらに見ただけで意味を推測することができるようになります。英語の場合も語根などの形態素を知る事で推測は出来ますが、一文字見ただけで分かるのが表意文字の良いところです。次に、英語の不満点を言います。語順が大体固定されていて表現の幅が狭い。孤立語の宿命かも知れませんが、簡潔であるために表現の幅を捨てたようにしか見えません。それに英語も所詮外来語まみれの極西の小さな島国の言語です。ほら、なんか日本語と本来の境遇が似ていますね(笑)。あらゆる分野で使われる世界覇権言語になれたのもイギリスとアメリカが成功したからであって、別に英語が簡潔で優れた言語であるからではありません。簡潔な言語が採用されるなら、今頃学生はエスペラントとかをやってますよ。日本語話者に言われたくないかも知れませんが、綴りと発音の不一致も困りどころです。表音文字オンリーなのに発音不一致なんですよ。最後は個人的な趣味ですが、不規則変化が少ないので嫌です。
>>2591
>表音文字オンリーなのに発音不一致なんですよ。
「五月蠅い」とか「蔓延る」とか「為体」とか「驀地」とかの頭おかしい熟字訓(=DQNネーム)をなんとかしてから批判してください。
一つ目
主題を表示するのはいいが、主題の助詞がつくと格助詞が消えるという欠陥のために、最も重要な情報である論理的主語や目的語があいまいになる。
「山田さんは田中が好きだ」→「山田が田中を好き」なのか「田中が山田を好き」なのか文脈がはっきりしないと不明。
2つ目
その非常に複雑な筆記システムを習得するメリットが「与えたい印象によって使い分け出来る」?コスパ悪すぎ。英語でも語彙レベルや法助動詞、仮定法などにより印象を変えられる。と「分かち書きしない事による読みづらさを軽減する」それは結果論。そんな回りくどい表記法にこだわらずに、他の大多数の言語のように分かち書きにすればいいじゃん。
>英語の不満点を言います。語順が大体固定されていて表現の幅が狭い。
日本語の不満点を言います。語順が大体固定されていて表現の幅が狭い。形容詞句形容詞節を絶対に名詞の前にしか置けず、文の述語(動詞、形容詞、形容動詞、断定の助動詞)がつねに文末に置かれなければならず、またそのあとには一切副詞句を置けないので表現の幅が狭い。
英語は述語動詞のあとにいくらでも副詞句を置けます。また長大な語句が文の前のほうにに置かれるのをさけるために形式主語・形式目的語の使用や外置変形が可能です。倒置構文も豊富です。SVO→OSVもSVC→CVSもSVOC→SVCOも可能です。
>日本語話者に言われたくないかも知れませんが、綴りと発音の不一致も困りどころです。
日本語話者に言われたくないですね。英語だとつづりの99%以上は一通りに統一されている。同じ音声に対する表記法は1つしかない。
一方日本語は、読み上げられた同じ文章を書き取っても10人10通りになりかねない。正書法が存在しない。漢字にするかかなにするか、送り仮名をどう書くか、どの漢字を使うか、なにも統一されていない。英語の表記法を批判するのは特大のブーメランですね。
>あらゆる分野で使われる世界覇権言語になれたのもイギリスとアメリカが成功したからであって、別に英語が簡潔で優れた言語であるからではありません。
英語派のだれかが「英語が簡潔で優れた言語であるからあらゆる分野で使われる世界覇権言語になれた」という主張をしているのですか?少なくとも私はしません。それを言い出したら議論が終わってしまうのでおもしろくも何ともありませんから。
>>2593
みたところ粗は有りませんね。少し無理矢理だったり、稀なものを例示しているけれど正しいのでいいです。言語帝国主義に対する嫌味の数行は単純に私の思想なので無視しても良かったんですよ。言語の優劣を考えるのは邪道ですが、筆記体系の面でかなり発音とスペルの不一致な英語に大きく負けていると見られるし、主題(反論の例が悪いと思う。後者の解釈は強引すぎる。)をしても差をつけて勝つのは難しい。この辺りが主戦場だと思っているので、英語の勝利という判断を下しました。お見事です。
いち日本人としての感性としては、日本人であるからこそだけれど、日本語の美しさを高く評価する。日本語の繊細で、無常の情を節々に○む文章は他の言語には真似できないし、あくまでも私自身の感想だけれど、英語を含め、他に学んでいて美しいと感じる言語と出会った経験がない。
自分が沿う主義や考え方は間違いなく接してきた文化に影響を受けてきたもので、絶対の価値観や物差しなど無いのだから、例えば「先進国が途上国より優れている」というように、特定の物差しを用いずに文化や言語に優劣をつけることはできないと理解している。特に「効率」や「利便性」といったものは帝国主義的な発想と切っても切れない関係にあるし、美学といったものは抽象的でこの手の討論遊びでは軽んじられがちだ。結局のところ、このような抽象的な主題の議論に関しては、自分が持つ意見が絶対普遍のものに昇華されるさだめなのだろうかと考えさせられる。
>>2596
基本的に言語学ではこのような話はタブーですからね。そもそもこう言った議論は簡潔な方が圧倒的に有利なんです。そりゃあ感情論も多発しますね。
>>2596
「日本語の繊細で、無常の情を節々に○む文章は他の言語には真似できないし、あくまでも私自身の感想だけれど、英語を含め、他に学んでいて美しいと感じる言語と出会った経験がない。」
そう、それはあなたの感想です。あなたの言語学習が美しさを感じるレベルに達してないだけ。
ここの投票結果のように、日本語が英語よりすぐれていると71%が考えているなら、この先も日本語はずっと欠陥言語のままだろうな。日本語派のコメントを読むと、英語もそのほかの言語のこともあまり知らないのに日本語を賞賛している人がいっぱいいる。
表記の統一をやらないと日本語ではまともな学問もできません。卒論書くとき、有名な精神分析学者の名前が文献によってバラバラで気が狂いそうだった。
「日本語には表記がいろいろあって豊かだ」とか言ってる人は、これでいいと思ってるわけだよね?
ジークムント・フロイト 、ジーグムント・フロイト 、シークムント・フロイト 、シーグムント・フロイト 、ジクムント・フロイト 、ジグムント・フロイト 、シグムント・フロイト 、ジークムント・フロイド、ジーグムント・フロイド、シークムント・フロイド、シーグムント・フロイド、ジクムント・フロイド、ジグムント・フロイド、シグムント・フロイド, etc.
言語って民族の精神の象徴だと思うけど、日本民族ってこんないいかげんな性格なのかな?だれもこういう状況をなんとかせねとは思わないってことだよね?
あと、細かいことかもしれないが、数字やローマ字を「全角」という変なモードで書くのやめるほうがいいと思う。
(以下産経のニュース記事より)
「歌手のaikoさんが代表取締役を務める芸能プロダクション会社「buddy go」(東京)に約1億円の損害を与えた」
aikoとかbuddy goとか字と字のあいだがあきすぎて気持ち悪いからやめてくれ。
むかしやったいじめのことでオリンピックの音楽担当をおろされた小山田圭吾の事件には、主語を明示しない日本語のいいかげんさが関係している。ネットには次のような記事があるね。
「小山田さんの件では、誰がいじめをしたのか主語が削られている可能性がある。」「日本語は主語が省略されがちですが、モーリーさんはその省略された主語を全て小山田がやったことにしていますよね。」「主語は不明ながら《『じゃあお前、ウ○コとか食べられるのかよ』と言っていた》とある」
私は小山田のインタビュー記事を読んだが、あちこち主語が抜けていて、いじめをやったのが小山田なのか、あるいは小山田の友人なのか不明なところがあちこちにある。小山田がすべてをやったという前提での批判が出てくると、彼は「全部を自分がやったのじゃない」と言いはじめた。インタビューで主語を明示していなかったからあとから何とでも言えるよね。
この事件を見ていると、日本語ならではの出来事だと思われる。英語・ドイツ語・フランス語のように主語が文法的に義務的な言語では、こんないいかげんなインタビュー記事も、またこんな責任逃れも起きないだろう。
あるテレビ番組で、「漸く」をアナウンサーたちがよめなかったというので、林先生が絶句したそうだ。
ちゃんと教育をうけたおとなの母語話者でもよめないことばがあるのいうのは、そのひとのせいではなく、その表記法の欠陥のせいだ。
スペイン語やイタリア語の表記法はまったくの初心者でも、1週間も練習すれば、すべての文章をなめらかに音読できるようにできている。
音韻論的にはこれらの言語よりはるかに単純な日本語の表記をおとなの日本人がよめないのはひとえにその表記法自体に根本的欠陥があるからだ。
英語の表記法はスペイン語やイタリア語のよりはかなりおとるが、日本語の熟字訓とかよりははるかにましだ。
お前ら日本人なんだから日本語使えよバカバカしい
西洋かぶれも大正までで終わっとけよ944人の朝鮮人
>>2644
君が惨めったらしく大っ嫌いな日本語使ってる時点でお察しなんだよなぁw
悔しかったら英語勉強しなよwww U are a fucking shithead lol
>>2646
I would use English anytime if you wish, but are you sure you can follow complicated arguments on linguistic issues in English?
>>2661
翻訳ニキチワっす
日本sageしたいならここより匿名掲示板のほうがいいっすよ
Bro, if you want to criticize Japan, anonymous message boards are better than this.
>>2643
で?おいらは嫌韓のネトウヨでもなければ君たちのように反日のパヨクでもないんでw
韓国ゲーだろうが日本ゲーだろうがエロかったら抜きますし面白かったらやりますねぇw
>>2647
嫌韓のネトウヨじゃなかったらまずまず英語派を煽る言葉として「朝鮮人」なんか用いないと思うんだけど…^^;
>>2649
ごめんね朝鮮人効いちゃったんだね許してちょw
一部の朝鮮人が日本嫌いなだけで日本好きな人もいるのは知ってるからね、まあ、こんなトピで英語に入れてるのは一部の方なんだろうなぁと思いましてw
>>2655
「日本嫌いな人→朝鮮人の一部」ってなってる時点で脳みそが短絡的な人って言うのが容易に想像つくから何言っても無駄なんだろうなってなったわ
普通に中国とか欧米の一部の国にも日本嫌いな人はそこそこいるぞ
>>2656
反論になってないぞw英語も日本語もできないとかもう動物園行けばwww
>>2658
反論というより逃走を加速させただけなんだけど^^;
日本語できないのはお互い様やなwww
>>2659
逃げたいならそっ閉じしとけよバカキッズ君www返信した時点で君の「反論したいよ〜!負けたくないよ〜!」って気持ち丸見えなんだよねw
お前みたいなクソバカお猿さんキッズがレスバに勝とうなんてwやっぱ動物園行けばw
「付いて来い言った家内に付いて行く」
これは川柳らしいが、これを「私が私の妻に『付いて来い』と言ったのに、私が私の妻に付いて行く」という意味に解釈しないといけないらしい。
AIに訳させると
I'm going to follow my wife who told me to follow her.
となる。
別にAIじゃなくても世界の人の90%以上はこの解釈をするだろう。
ま、日本語とはそういう言語。その場のノリで意味を考えなさいというポリシー。
むかしは日本にはやまとことばしかなかった。それから漢語をたくさんとりいれた。でも日本人は声調をマスターできず、かつ中国語の音素を発音できなかったのでたくさんの同音異義語がうまれ、文字を見ないと意味がわからないことばだらけになった(次のサイトを参照。「日本語、韓国語、中国語の関係性がよく分かる表」を解説する。)。
その上、中国語では各漢字の音が一音節なのに日本語にとりいれられると「国」→「コ・ク(ko・ku)」のように2音節になったので、情報密度が半分(同じ時間で半分の情報しか伝えられない)になった。
つぎに明治以後大量の英語などヨーロッパの語彙がとりいれられた。このときも日本語は音素がとぼしく、長母音と二重母音の区別もないので大量の同音語が生まれた(例 low, law, raw, row→全部「ロー」)。
また日本語は子音が連続できないのでstrike/straik/→「ストライク/su・to・ra・i・ku/」のように1音節が5音節になるなど長大な単語がたくさん作られ、情報密度がひどく低下した。
要するに
「日本語=やまとことば+劣化した中国語+劣化した英語」
とみなすことができる。
今日見つけたかなしい日本語
「除雪は本当に大変ですよね、私達が代わりに除雪致します。また法人様など敷地の大きい場所は、除雪/排泄業者を紹介致します。」「公道の雪や氷まで、市民が自分で排泄業者を雇って」「私の家も週1で排泄業者を頼んでいて、雪が降っても家の周りが綺麗な方なので」「大きなトラックでの排泄業者さんはもちろん雪をたくさんもっていってくれます」
これもひどい:
「数々の有名スポーツ選手を排出している早稲田大学スポーツ科学部」、「大手企業にIT人材を排出するインド工科大学」「 二年連続で早稲田大学合格者を排出」「近年検察官を排出している人数の多い大学院」「京都大学は文理両面において著名人を排出している」「多くの大学合格者を排出してきたプロの講師」「優秀なエンジニアを排出できる. 情報科学部」
スポーツ選手はCO2かうンこみたいなもんですか?
学校・塾のホームページに人間を排出してるの多いけど、そんなところにはいりたくないなー。
>>2680
こんなのあった
>>特番は20%超の高視聴率。今回ファイナルを銘打っただけに映画もメガヒットとなるのは必死でしょう。
外国人「『美味い』は何て読みますか?」
日本人「うまい」
外国人「『上手い』は何て読みますか?」
日本人「うまい」
外国人「『旨い』は何て読みますか?」
日本人「うまい」
外国人「『巧い』は何て読みますか?」
日本人「うまい」
外国人「I don't understand.」
>>2684
この人はいったい何を批判しているのか?
主語がないからよくわからない
>>2685
真のナショナリズムには自民族の文化や価値観を盲目的に肯定することではなく、高い視点から客観的に批評することが不可欠だね。
翼音さん
しょおん?つばね?よくと?
いいえ「はのん」さんです。
なんせ「聖林」で「はりうっど」だからね、なんでもあり。文字なんて好きなように読めばいいの。それが日本語。
だから「聖」で「こうき」。
日本人は外国語に対する敬意がたりない(単純にバカの可能性もある)。
(以下「知恵袋」から引用)
質問:映画「ジャイアンツ」は原題では「Giant」と単数形です。どうしてわざわざ複数形にしたのでしょうか?野球の巨人が有名で連想しやすいから「ジャイアンツ」にしたのでしょうか?
回答:その通りです・・・邦題付けるやつはアホばっかりだったんです((+_+))
'Giant'(1956)は「テキサス」を現す言葉で単数だったのに『ジャイアンツ』と野球チームと同じ複数にし、'Facing the Giants'はフットボールの対戦相手の強豪チーム名なので複数なのに『ジャイアント』と単数にしています。
モノを知らない馬鹿さ加減丸出しです・・・
(引用終わり)
A River Runs Through Itという映画の日本名は「リバー・ランズ・スルー・イット」とただの英語の劣化カタカナ発音だが、runsの3人称単数現在のsは「ズ」にしている。一方Dances with Wolvesの日本名は「ダンス・ウィズ・ウルブズ」だ。wolfの複数wolvesのほうは「ウルブズ」としているくせにdancesの3人称のsはなぜかカタカナにしていない。なぜなのか? 正当な理由などないだろう。要はその場のノリだけでカタカナにしているのだ。
「隣のヒットマン」 The Whole Nine Yardsにいたっては、その続編The Whole Ten Yardsを「隣のヒットマンズ」としている。「ヒットマン」とはなんなのか?hitmanの複数形はhitmenなのだが。
「私は小泉チルドレンです」と平気で言う政治家もいる。私は何人いるのだろう?
外国語の発音や文法をまったく考慮しない[考慮できない]このような事象がいくらでもある。
>>2691
日本人から見た優劣なんて最初からわかりきってるのに、日本人視点でごり押ししてる人多い。中立的な視点でコメントしないと。
「蓮生」くん という名前を見て、「はすお?はすき?れんしょう?」と思ったんだけど、「れん」だって。「生」はどうしたんだよ。
日本人の名前って、日本語を象徴してるね。名前は人に読んでもらってなんぼなのに、読めない名前ばかり作られる。要するにバカが多いんだね。
このまえ友達と物理の話しててなんか伝わらないなと思ってたら、こちらが「高速で運動する物体」と言ってるのに相手が「光速で…」と思っていたらしい。これでは話がかみ合わないわな。
同じ文脈で使われる語まで「漢字見ればわかるだろ」と、平気で同音語にするからこうなる。科学と化学、売春と買春とかもな。
>>2697
票数なんて日本語が勝つに決まってるからどうでもいいですよ。重要なのはコメントの内容。
やらかしちゃったフジテレビ
<10月11日から12日にかけて、佐賀県を訪問された天皇皇后両陛下の長女愛子さま。フジテレビのある番組が“とんでもないミス”をおかしていた。
「佐賀城ご訪問を伝える際の字幕で、本来『愛子さまが視察されている』と表示すべきところを、『愛子さまが刺○されている』と字幕を出してしまったんです。>
音素数がとぼしい同音語だらけの言語だからつねにこういうことが起こらないか気になって神経をすりへらすね。それでもやらかしちゃう。気にするな。日本人がダメなんじゃなくて日本語というシステムがだめなんだよ。
Youtubeの動画で自動生成の日本語字幕を表示して5分ほど読んでみれば、日本語の同音異義語のヤバさが実感できるだろう。
どちらの言語にも素晴らしい伝統と蓄積があり、その素晴らしさを味わい尽くせていません。そんな私には、どちらがよりすぐれているかなどと言うことは不可能です。
>>2705
いいところばっかり抽象的・主観的に述べてもだめ。
悪いところをちゃんと認識しないとだめ。
同音異義語については、たしかに日本語には同音異義語が多いのですが、これは母音の数が限られていることが影響しています。英語のように母音の数が多い言語では、同音異義語は少なくなりますが、その分母音の区別がより複雑になります。英語には20前後の母音がありますが、これらの音の違いが微妙であるため、母語話者であっても文脈がなければ聞き間違いが発生しやすいです。特に、速い速度で話される場合、母音が融合したり、あいまい母音になることが多くあります。また、地域により母音の音の種類がかわり、同音異義語が生じることも珍しくありません。
さらに、日本語の同音異義語の多さは、多彩な漢語が用いられる文章語と、和語を中心に、限られた漢語が用いられる話し言葉という二重構造に由来しています。口頭での確実な伝達を行いたい場合は、話し言葉として実績のある語彙を選択することで、日本語でも同音異義語による勘違いを起こりずらいようにできます。
コンピューターへの文字入力は近年発達した技術であり、言語そのものの魅力や有用性とは本来無関係です。そもそも、字幕の間違いが認識できるということは、同音異義語があっても人間には問題なく情報が伝わっていることを表しています。情報技術が発達することにより、コンピューターへの文字入力や字幕の書き起こしの正確さは向上していき、言語本来の魅力が問題となっていくでしょう。
外人『「可哀想」「可哀相」「可哀そう」「可愛想」「可愛相」「可愛そう」「かわいそう」のどれが正しいんですか?』
日本語教師『どれでもいいよー。欠陥言語に正書法とかないんすよ。』
外人「・・・・」
「日本の女は何してもいいよってか😫」
主語省略しほうだいで、副助詞「は」が名詞につくと格助詞が消える欠陥言語では、同じ文でa) Can Japanese women do anything they want?と b) Can you do anything you want to Japanese women?のふたつの意味が表せて便利ですね(笑)。
で、上の文はどちらの意味でしょう?これは「イベント中の小嶋陽菜さんに抱き着き、押し倒す…外国籍の40代男を逮捕」というニュースに対するコメントです。ああやっとわかった、b)の意味だったんだね。
>>2713
AIにその文を訳させたら
Japanese women can do whatever they want.になったわ。
「キムタクが無教養だ」という記事の下にあったコメント。
「zxm********1日前
昔、キムタクが同い年の一般人と対話する番組があってたまたま観ていた。
その時、相手は生涯学習の仕事をしていて、聞かれたからその話をしていたのだが、キムタクは最後まで障害の話だと思い込んでいて全く会話が噛み合っていなかった。
スターと呼ばれるような人に知識を求めないが、ある程度の常識は持っていてほしいかな。」
確かにキムタクはちょっとぬけたところもあるだろうが、「ショウガイ」と聞いて頭で誤変換することくらいだれでもあるだろう。そんなことでキムタクをたたくのはどんなものか?同音異義語の地雷ばかりの日本語が悪いんだろう?
そろそろ答えを出そう
結論は「両言語に優劣はない」
日本語で表現できることは、多少の語数の増減は伴うにせよ英語でも等しく表現できる。その逆も然りだ。
よく「日本語は曖昧である」と言われるが、日本語が曖昧なのではなく、日本語話者が曖昧な表現を好んで使うだけである。英語にも婉曲表現(euphemism)や暗喩表現(metaphor)は存在し、それらを駆使することで曖昧な表現を作りだすことは可能である。
似たようなもので「英語は論理的だ」と言われるが、英語が論理的なのではなく、英語話者が論理的な表現を好んで使うだけである。日本語でも主語を明示し適切な接続詞を使用することで論理的な文章を書くことができる。もし本当に日本語が非論理的な言語であるならば、日本の科学技術は今日のそれまで進歩していないだろう。
巷で議論される*言語優劣論*は言語の優劣ではなく翻訳技術や人種、民族の性格の優劣にすり替えて行われている場合が多い。いまいちど「言語の優劣とは何か」を考えてほしい。
そろそろ答えを出そう
結論は「英語のほうが優れている」
よく「日本語は曖昧である」と言われるが、日本人があいまい(vagueではなくambiguous)な表現を好むのではなく、主語も目的語も義務的でなく、所有の表現も随意的で、名詞に定不定単数複数の区別もなく、関係節が元となる文の格構造を義務的に保持できず、時制が貧弱かつ相対的である日本語の文法構造があいまいな文を大量に生成してしまうのだ。英語にもあいまいな文は存在するが、このトピックのコメントをすべて読めばわかるように、日本語のほうがあいまいな構造がはるかに多い。
「英語は論理的だ」と言われるが、英語を使う人々がとりたてて論理的なのではなく、英語の構造が無意識的に論理的に明晰な文を生成しやすくできているのだ。日本語でも、なみはずれて意識的になれば、すべての主語目的語を明示し、限定詞の代わりに適切な連体詞や接尾辞や、所有や数の表現をを使用することでなんとか英語レベルの文章を 書くことができるかもしれないが、そのような言語はもはや普通の日本語とは言えないのではなかろうか?そしてそのような日本語はおなじ情報をあらわした英文の何倍もの音節数となり、情報伝達の時間的効率はいちじるしく低下するだろう。
「もし本当に日本語が非論理的な言語であるならば、日本の科学技術は今日のそれまで進歩していないだろう。」というのは日本語を弁護しようとする人の常とう句だが、科学技術の中核は数学や物理や化学であり、それらの理論の中核は英語などヨーロッパの言語の文法構造を反映している数式や反応式などの人工的言語で表現されており、日本語とは関係ない。
そして最後に、このトピックのコメントによりくりかえし指摘されているように、言語の表記・正書法の体系性、統一性、整合性、能率などの多くの点において、日本語は英語のみならずほとんどの言語に劣っている。
巷で議論される*言語優劣論*は言語の優劣ではなく翻訳技術や人種、民族の性格の優劣にすり替えて行われている場合が多いが、このトピックで論じられるべきは、そのような低レベルの議論ではない。言語の形式や構造そのものの優劣である。いまいちど「言語の優劣とは何か」を考えてほしい。
>>2725
私のコメントに対しての批判だろうから答えさせてもらおう。
気になる点は主に2つ。
ひとつは、あなたの言う「普通の日本語」とは何かという話だ。日本人が日常的に話す日本語のことだろうと私は捉えたが、それは日本人を媒介してるため日本人の意識や思考による影響を受ける。言語の構造レベルで日本語が劣っていることを主張するならば、日本語そのものとその評価に日本語話者を媒介させてはならない。
もうひとつは、情報伝達の速度が速い言語は優れ、遅い言語は劣っているというあなたの考えについてである。たしかに情報伝達の速度(1音節の持つ意味の量)は日本語よりも英語のほうが大きい、というのはある程度理解できる。ただ、言語を使うのは機械ではなく、人間だ。伝達速度が大きいということは、逆に言えば、1つの聞き間違いが致命的な誤解に繋がりやすい、ということである。人間の単位時間における処理能力には限界がある。伝達の失敗の可能性の高い言語は、果たして優良な言語と言えるのだろうか。
この2点に関して、あなたの意見が聞きたい。
科学技術に関しては、あなたの意見も正鵠を射てると感じた。
次にあげるのはアインシュタインについて二人の人が対談しているのを記事にしたもので、ネットにあがっている。
『★逸話っていうか多分本当の話だと思うんですけど電気に書かれてたんで。
★12歳の時にユークリッド気化学を理解したと。このユークリッド気化学が何なのかすらも俺は分からないんだけど、
★26歳の時にこの交流史仮説とブラウン運動と特殊相対性理論っていうのを
3つの論文を発表して、奇跡の都市っていう業界では言われてるんですよね。
★ハリーさんも聞いたことあるかなと思うんですけどスピノザって人がいてるんですよ。この人もユダヤ人で哲学者でスピノザって人が入れて半信論っていう。
ハリー:半信?
半信じゃない。半信論ね。いや俺これねあの半信論で検索した時も何回検索しても半信に変換されるから違うって言いながら。神様の論ですね信論で半は反対の半じゃないんだけどこのまた違う漢字ですよ半って。でえっとね三随に本用の。
ハリー:あー半用的の半。
半用人型決戦兵器の半ですね。』
これは人間が書き起こしたのか、音声入力したのかわからないが、ひどいものだ。同音異義語の氾濫がいかに深刻かがわかる。すでに十分な教養がある人ならこれを読んでも誤りが何の誤りかわかるだろうが、知識がない人がこれを読んだらわけがわからないだろう。
ここへコメントしてる人たちは、日頃から日本語を話しているのだろう。それゆえ日本語への不満点が、他の言語に比べて頻繁に見つかるのだろう。英語だったらこんな誤解はなかったとか、日本人でも日本語がうまく使えないから日本語はダメだとか、意見は様々である。
そこで、英語の欠点といえるものを挙げようと思う。
そのうちのひとつは発音と綴りに規則性がない、ということだ。たとえばlock, phone, mother、この3つの単語に使われるoはそれぞれ発音が異なる。look, food, bloodもそれぞれ発音が違う。knowのkやislandのs, indictのcはいずれも発音しない。発音と綴りが対応しない例には枚挙に暇がない。初めて見る単語の発音を100%の精度で正しく発音するのは不可能である。逆に、初めて聞く単語のスペルを100%正しく書き取るのも不可能である。
その点日本語は楽である。「わ」「お」と発音する格助詞の「は」「を」を除いてひらがな1文字には必ず1音のみが対応する。漢字は知らないと読めないだろうという反論が予想されるが、漢字は表意文字だ。英語は表音文字なのに正確な音を表していないのである。
表音文字を使う他の言語も発音は規則的である。英語、中国語に次ぐ話者数のいるスペイン語は基本的にローマ字通りの発音であるし、ヒンディー語も文字通りに発音する。アラビア語は原則として母音を表記しない言語だが、1つの子音字が複数の子音を表すようなことはない。フランス語は文字と綴りに多少のずれはあるものの、そのずれは概ね規則的である。
発音と綴りに大きな乖離があるのは、世界の主要言語のうち英語にのみ見られる特異な現象である。
(続き)
もうひとつは、単語から品詞を特定できないという点だ。英語には動詞はこの形、名詞はこの形、のような決まりがない。たとえばスペイン語の動詞はrで終わるとか、日本語の動詞は「る」で終わり、形容詞は「い」で終わるとか、語から品詞を特定する規則があり、知らない単語でも文の構造は理解できる、という言語は多い。しかし、英語には、ある語が文中でどのような働きをするのかを示す規則はない。知らない語が文中に出てきたら語順や文脈からその働きを推測するしかない。そのような語が複数現れたらお手上げである。英語は文構造がしっかりしていると言われるが、それはあくまですべての語を理解してる前提の理想的な話であり、膠着語である日本語のほうがかえって文構造を理解しやすい、ということもある。
古代の 言語は 分かち書き する ものが 少なかったが、現代の 先進国の 言語では ほとんどが 分かち書きを している。
日本語は いまだに 分かち書きすら しない ぐーたらな 未開言語。もう終わりだ猫の国(笑)
下の例はネットの辞書の情けない例文。
「実用日本語表現辞典実用日本語表現辞典
はちま いわゆる「2chまとめサイト」の一つである「はちま起稿」の略称。
「はちま」の例文・使い方・用例・文例
山田さんはちまちました顔立ちの御婦人だ.」
それ 全然 関係ない やろ。ちゃんと 分かち書き しない から そんな ことに なる。
世界共通語だから言語が色々違う国でも英語勉強するかも。
日本語、韓国語、中国語、ロシア語、スペイン語、フランス語、ヒンディー語、ドイツ語、アラビア語等。全部英語以外の国でも英語勉強するし言語か違う人たちでも自分たちが楽するんじゃなくて皆で英語を話せばより伝わりやすいかも(ごめん説明下手で)
(遠くにいる男の子を指差して)「アレ 由貴が昔好きで告白した子だよ」
これはある有名な漫画に出てくるせりふ。この文の意味わかるかな?
文脈なしにはセンテンスの意味が確定できないことが多いのが日本語。
>>2747
文脈がなければあらゆる言語は意味が確定しない
英語の「i love you」も誰が誰に言うのかで意味が変わってくる
>>2749
そういう話ではない。文脈が必要なのはあたりまえ。文脈依存性というのは発話がどれだけ文脈に依存しているかという量的な問題。
「好きだよ」と「I love you」では情報の量がまったく違うだろ?
>>2768
日本語は助詞や助動詞で西洋諸語の主語にあたるものが推測できるという点を忘れてはいけない。
あなたの例では「すきだよ」が「i love you」に比べて情報量が少ないとのことだったが、断定の助詞「だ」によって自分の主張であること、呼びかけの助詞「よ」によってその対象が二人称であることが大方推測できる。
包含する情報量にあなたが思うほど差はない。
>>2780
一般的な日本人が第三者(あいつ)に対して「だよ」を使うだろうか。
ふつうは「好きらしいよ」ではなかろうか。
抑も「好きだよ」と"i love you"では使われる文脈が異なるから日本語と英語の違いを論ずるに不適切ではないか。なるほど「好きだよ」と"i love you"は意味は似ているし、或る文脈では相互に翻訳できるかもしれないが、あくまで「好きだよ」は"i love you"の翻訳の一例だということを忘れてはいないか。
英語は一文だけで解釈が一意に定まると主張する人は、かの有名な「to be or not to be, that is the question」の意味も文脈に依存せず一意に定まるということでよろしい?
>>2775
言語の陳述の単位は命題でしょう?Lyonsの意味論にも出てくる話。命題は数学の概念ではなく論理学の概念。論理学は言語に対する考察から生まれた。数学はそれを取り入れただけ。
>>2781
たとえば「富士山は綺麗だよね」っていう文があったとして、富士山が綺麗かどうかは人によって異なるから、これは命題にはなりえない。論理学が言語によって記述されるのは分かるが言語が論理学から生まれたとするのはおかしい。
>>2785
議論の前に命題の意味を説明しないといけないのかな?「命題」の意味も知らない人と議論はできない。
>>2787
めい‐だい【命題】 の解説
1 題号をつけること。また、その題。名題。
2 論理学で、判断を言語で表したもので、真または偽という性質をもつもの。→判断
3 数学で、真偽の判断の対象となる文章または式。定理または問題。
貴方が言わんとしてるのはおそらく2のことだろうが、真偽をつけられないものは命題ではない
>>2788
「真偽をつけられないものは命題ではない」
あんた完全に誤解しているよ。その辞書?の解説もへったくそだが。真か偽か確定しているものだけが命題なんじゃない。
「中居はうそつきだ」これは主語と述語を備えており、真か偽かという議論の対象になる。よって命題だ。
いっぽう「好きだ」は主語も目的語もないので、命題ではない。
>>2838
命題の意味を知らん人まで言語系の議論に参加されると、いろいろ説明する手間がふえてきついね。
>>2769
ではto be or not to beとはどういう意味でしょうかお答えください
>>2751
何を基準にして難しいと言ってるのかは分かりませんが、言語の習得難易度は基本的に母国語からどれだけ離れているかによって決まると言われています
ここで1つ言いたいのが、日本語が構造的に劣っていると主張する人たちは、ただ単に日本語を運用する能力に欠如してるだけではないでしょうか?
>>2754
「日本語を運用する能力『が』欠如してる」だね。
あと、「ただ単に」は重言。「単に」か「ただ」でOK。
日本語の運用能力に問題があるのはあんただね。
>>2770
前者は誤字。失礼。後者は強調のために重複表現を用いた。
わざわざそこを突いてくるとは、あなたは揚げ足取りしかできないのか。
>>2778
「揚げ足取りしかできないのか。」
いいえ。私は揚げ足取り以外にもたくさんの言語学的なコメントを書いている。
>>2782
反語のつもりで言ったのだが。論理学的知識には長けているとしてもコミュニケーションは苦手のようだ、あなたは。
どうもここでコメントしてる人たちは「SVOの文構造が一意に定まる」ことが「優れた言語」としての必要条件のように語っていますけれども、世間一般的に優れた言語とされているであろうラテン語でさえSVOの文構造が一意に定まらないことはあります
たとえば
rosa pulchra est
はrosa pulchraが主語なのか、rosaのみが主語なのか分かりません。
SVO構造が一意に定まらない言語は優れた言語ではないという前提を一度考え直してみるのはいかがでしょう
>>2756
どのコメントが「「SVOの文構造が一意に定まる」と主張しているのか具体的に言ってください。
「ラテン語でさえSVOの文構造が一意に定まらないことはあります」
なにが言いたいの?ラテン語は語順がかなり自由だが、デフォルトの語順はむしろSOVだよね。Rosae aquam do.みたいに。
それに、
rosa pulchra est はSVOでもSOVでもなくSCVだろ?
pulchraは形容詞だよね?
いずれにしろ、日本語と英語の比較が問題だよ。ラテン語は関係ない。
>>2771
語順の話はしていない。失礼。どの語が主語でどの語が動詞なのかが一意に定まるという意味で用いた。
>>2764
レスバって何?
日本語派なら変てこな略語使わないでちゃんとした日本語で議論してね。
>>2772
レスポンスバトル
喧嘩みたいなもんですよ
レスバをレスポンスバトルなんて言ったら引かれるんですよ
気になったから述べさせてもらうが、英語が日本語より優れていると言いたいならば、英語の良いところや日本語の悪いところを列挙するだけでは意味がない。比較する項目を定め、対照的に論ずる必要がある。
>>2779
語彙数 英語>日本語
音素の種類 英語>日本語
主語の明示性 英語>日本語
目的語の明示性 英語>日本語
名詞の数の明示性 英語>日本語
関係節の構造の明示性 英語>日本語
文脈からの独立性 英語>日本語
正書法の確立 英語>日本語
時間当たりの情報密度 英語>日本語
ついでにこれは言語自体の属性ではないが
話者数 英語>>>>日本語
インターネットにおける情報量 英語>>>>日本語
>>2784
つっこみたいところはたくさんあるが、まずその項目たちが言語の優劣と関係がある根拠を教えてくれ
語彙が少ないほうが意思疎通を図るのに支障が生じないでしょうし、文脈がなければことばもないわけだから文脈への依存度は言語の優劣の判断材料にはならないと思うのだが
>>2786
「文脈がなければことばもないわけだから文脈への依存度は言語の優劣の判断材料にはならない」
その手のレベルの低い反論に対してもう3回くらい説明してるが、これで最後にしてくれ。
ここで言ってる「文脈依存度が高い」というのは「主語とか目的語みたいな『事実関係・5W1H的な情報』がちゃんと言語に表されていないから、受け手が文脈を参照しないと状況がわからない」という意味なの。つまり言語表現の情報が欠けているから、受け手の推論的思考に大きな負荷がかかるということ。
だれも英語に文脈がないとか主張してないっつーの。
ものわかりが悪い人には具体的に説明するしかないな。次の例を見ても「文脈依存性が高い」の意味がわからないならあきらめてくれ。
(以下引用)
札幌・西警察署は2024年12月8日、住所・職業ともに不詳の男(75)を暴行の疑いで逮捕しました。男は8日午前11時ごろ、札幌市西区二十四軒2条3丁目の路上で、面識のない男性の顔面を手拳で殴った疑いが持たれています。
警察によりますと、男性が妻と道路上を歩いていたところ、正面から歩いてきた男と妻の肩がぶつかりました。肩がぶつかったことに気づいた夫が男と妻の間に入ったところ、男にいきなり拳で一度殴られたということです。
その後、妻が「夫を殴った男を捕まえている」と110番通報し、駆け付けた警察官が男を逮捕しました。 (STVニュース北海道)
(以下この記事に対するコメント)
3: やるな妻
4: 妻が修羅だった
5:取り押さえてたのは夫やろ
23: 嫁つよい
65: ジャガー横田夫婦みたいな夫婦か
82: 妻>犯人>夫
110: 嫁が強い
26. 妻が電話してる=取り押さえてるのは夫。夫は手がふさがってるということ。
41. 妻が捕まえてるって言ってる奴読解力なさすぎ
45. 母は強しw
事実関係を明確にすべきニュースの記事で「男を捕まえている」の主語が明示されていないために、受け手はそれを補おうとしてはいるが、文脈に依存しようにも文脈的情報も不足しているため、コメントが示すように、解釈が分かれてしまっているね?
この手の例はこのトークのトピックのコメントにもいくつもくりかえしあげられている。
英語のニュースではこんなことめったに起きない。上のケースでもmy husbandなりweなりIなり主語を書くから。
>>2794
言語の文脈依存度が低いということは、裏を返せばいつでも冗長で煩雑な表現を使っているということ。英語は文脈依存度が低いのだと主張したいのは分かったが、それが言語の優劣に果たして関係するのか。貴方の言うように、確かにデメリットはあるが、短い文で言いたいことが伝わるというメリットもあれば、主語に束縛されないぶん表現の幅が広がるというメリットもある。
>>2795
「短い文で言いたいことが伝わる」
もともと日本語は音節数が多いから「短い」と思っても実は短くない。情報密度が小さいとはそういうことだ。
例 「好きだ」su ki da
I love you.と同じ3音節だね。短くない。
そして情報量英語の1/3しかない。
「主語に束縛されないぶん表現の幅が広がる」
具体例がないので意味がわからない。
>>2800
主語がカットできれば文の量が減るということを言いたい。今は主語のあるなしを論じているのであって、そこに特殊な例を出されても困る。話の本筋ではないが「好きだ」の「su」の母音uはよく脱落する。
>>2800
私が欲してるのは日本語の情報密度が小さいなどという具体的な話でなく、「主語、目的語の明示を必要とする言語は優れている」に対する抽象的な根拠。もしそれが示せないのであれば、情報密度の話をしようが主語や目的語の明示性の話をしようが、決して英語の優位性を語ることはできない。
>>2804
「主語、目的語の明示を必要とする言語は優れている」
主語や目的語が不明だとこまることがあるのでは?
その具体的事例はすでにさんざん挙げられている。
>>2818
主語が明示されていないと困ることがあると言いたいのは分かった。私もそれには同意。ただ、主語が"必要"というのは、主語が必要でない場面や状況でも主語を用いる必要があるということで、それは果たして優れた言語といえるのか。
また、主語が必要な場面で主語を省いたことで意思疎通に支障が出た場合、その責任は言語ではなく発話者。言語自体は主語や目的語を明示する機会を与えている。
>>2819
「主語が必要でない場面や状況でも主語を用いる必要があるということで、それは果たして優れた言語といえるのか。」
「主語が必要でない場面や状況」だということをだれが判断するのか?
それはふつう話者や筆者だよね?
ところが話者や筆者が「主語が必要でない」と判断してもその表現を受け取る側には必要かもしれない。
このコメント欄には話者が「言わんでもわかるやろ」と思って主語や目的語を省いた結果、受け手はそれがわからなくて混乱したという事例がいっぱいあったよね? あなたはそれらをちゃんと読んだ?
結局、一見自明で冗長に思えても、主語や目的語は明示をデフォにしておくほうがあとから困らないんだよ。たとえば数式を書いてる人が「さっきからxの値を計算してるんだから、もうxは省略してもいいよね?わかるやろ?」とか言い出すとめちゃくちゃになるね。だからxを省略したりしないんだよ。
しかも英語やその他の印欧語は、その音韻構造と、代名詞や動詞の人称語尾などの短さとのおかげで、何も省略しなくても、省略だらけの日本語に伝達時間の短さでより優れている。
>>2795
主語や目的語を明示することを「冗長で煩雑な表現」と感じるのは日本人くらいだろう。世界の圧倒的多数の言語では必要な情報だとかんがえるからそれらを明示しているのであって冗長とか煩雑とか思ってはいない。
>>2801
「世界の圧倒的多数の言語」?そうかい。英語、中国語に次ぐ話者数を誇るスペイン語、これは主語を必要としない。それに次ぐヒンディー語は専門外なのでパスさせてもらう。さらにそれに次ぐアラビア語。これまた主語を必要としない。フランス語、イタリア語、ロシア語もまた主語を必要としない。時代はさかのぼるが、昔多くの地域で使われていたラテン語や古代ギリシャ語も主語は必須ではなかった。
圧倒的多数の言語とはなんのことなのか、どこから引っ張ってきた情報なのか、ご教示願いたい。
>>2803
言語学の基本知識もない人間に同じことを何度も説明させられるのはかんべんしてほしい。
ロマンス系の言語のように動詞の人称変化がある言語は、空の主語人称代名詞と動詞の一致があるとみなされるので、主語があるとみなされる。INFLを代名詞の一種と考えてもいい。
これらは日本語のような言語とは全く違う扱いになる。
>>2811
今は形式の話をしている。
「空の主語」?分かっているじゃないか。形式的に主語は語として文中に現れない
>>2812
主語が音声形式として現れるかを議論しているのではなく、「主語がなにであるかの明示」を何らかの方法でするかどうかが問題だろ?
>>2803
ご教示しましょう。
言語学の世界ではほとんどの人が知っているソースです。
The World Atlas of Language Structures (WALS) is a large database of structural (phonological, grammatical, lexical) properties of languages gathered from descriptive materials (such as reference grammars) by a team of 55 authors.
Feature 101A: Expression of Pronominal Subjects
代名詞主語の表現の仕方の違い
主語位置の代名詞によって、通常義務的に明示される(英語タイプ) 82
動詞の接辞によって表現される(イタリア語タイプ) 437
様々な語に付属する接語で表現される(Chemehuevi 語タイプ) 32
名詞句の主語とは別の位置に置かれる代名詞で表現される(Longgu 語タイプ) 67
上記の二つ以上の手段で表現されるが、いずれかが基本的ということがない 32
主語位置の代名詞で表現可能だが、通常明示されない(日本語タイプ) 61
計 711